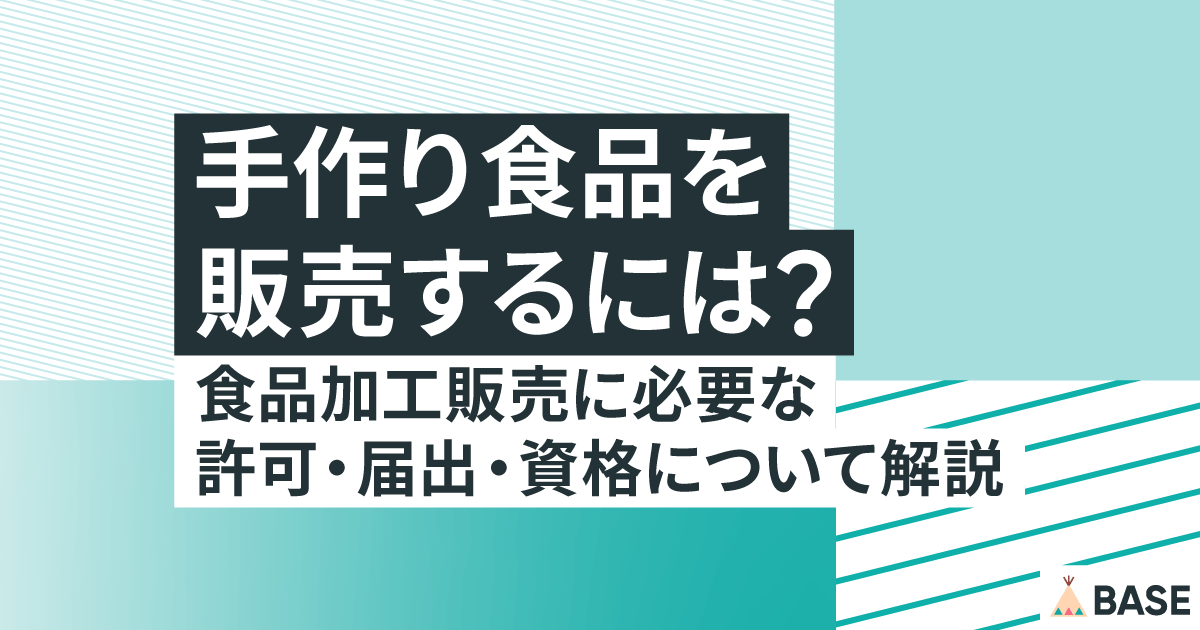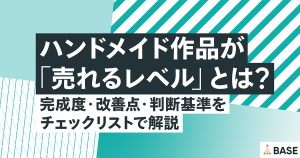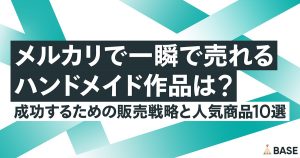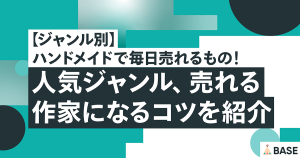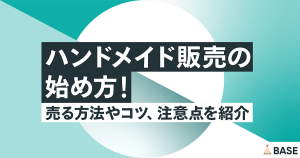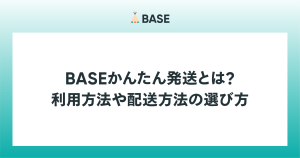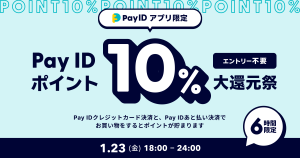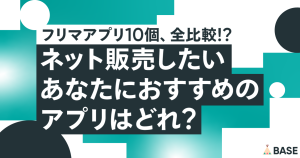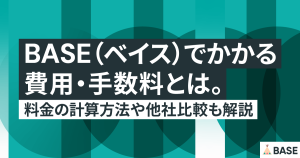お取り寄せやテイクアウトの需要が増すなか、加工食品の販売を検討している方が増えています。
事業に参入する前に、許可や届出の必要の有無について、しっかり確認しておきましょう。
この記事では、加工食品のネット販売を検討している方に向けて、どのような許可が必要になるのか、具体的な条件や手順にはどんなものがあるのかを解説していきます。
【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ
- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです
- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます
- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています
- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています
手作り食品を販売するには許可や届出が必要
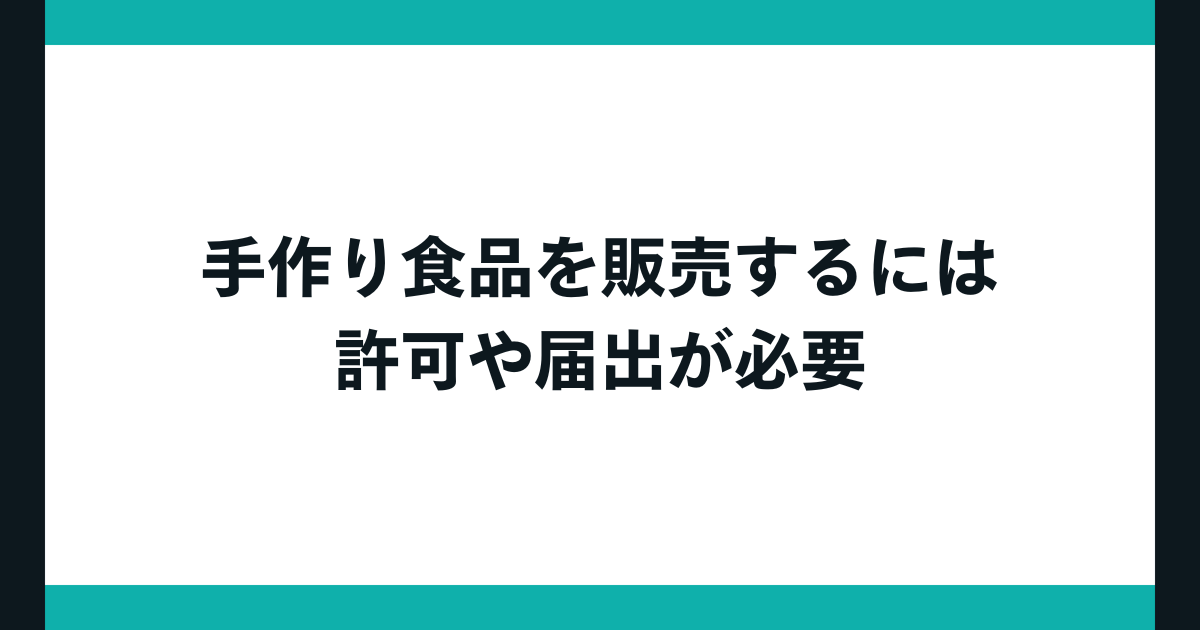
食品を加工して販売するには、保健所・自治体などに許可や届出を申請する必要があります。
たとえば、以下のような場合です。
- 八百屋で惣菜を作って販売したい
- 農家であまった野菜、果物をジャムにして販売したい
- 自宅で作った手作りお菓子を販売したい
営業許可と届出の違い
厳密には、食品の種類や調理・製造・処理・販売の工程と地域によって、届出だけでいい場合と、許可まで必要になる場合とにわかれます。
営業許可を得るには、要件にあわせて食品を製造する施設を整備した上で、保健所の監査を受ける必要があります。一方で届出は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などを提出するだけです。
大半の加工食品は、保健所、自治体の許可が必要になります。そのため、食品を加工して販売したい場合、まずは施設の所在地を所轄する保健所に問い合わせましょう。
もし、許可を得ないまま販売してしまった場合、法律違反や条例違反となり、罰せられる可能性もあるため、注意が必要です。
営業許可が必要な手作り食品
食品の営業許可は全部で32業種あり、そのうち手作り食品に関連するのは16種類です。
営業許可の名称と当てはまる手作り食品の例を紹介しますので、販売したい食品がどれに当てはまるのかチェックしてみましょう。
|
業種 |
食品の例 |
|
菓子製造業 |
パン、洋菓子、和菓子など |
|
アイスクリーム類製造業 |
アイスクリームなど |
|
食肉製品製造業 |
ハム、ソーセージ、ベーコンなど |
|
乳製品製造業 |
ヨーグルトなど |
|
水産製品製造業 |
魚介類その他の水産動物もしくはその卵を使用したそうざい |
|
冷凍食品製造業 |
冷凍したそうざい(菓子・水産製品・麺類などは除く ※魚肉練り製品はここに分類される) |
|
複合型冷凍食品製造業 |
冷凍した菓子・水産製品 |
|
食用油脂製造業 |
食用油、マーガリン、ショートニングなど |
|
豆腐製造業 |
豆腐、焼豆腐、油揚げ、生揚げ、がんもどき、ゆば、凍り豆腐、豆乳(密封・密栓された清涼飲料水たる豆乳を除く)、おからドーナツなど |
|
納豆製造業 |
納豆 |
|
麺類製造業 |
うどん、そば、そうめん、中華麺、パスタ など |
|
そうざい製造業 |
煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物など ※パンや米飯とあわせた弁当形態での販売もここに分類される |
|
複合型そうざい製造業 |
食肉処理、菓子製造、水産製品製造(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造をともなう手作りそうざいの製造 |
|
密封包装食品製造業 |
常温で流通するレトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰、ソース類など ※冷蔵流通するもの、はちみつ、酢は届出のみの対応 |
|
みそ又はしょうゆ製造業 |
みそ、しょうゆ、粉末みそ、調味みそ、つゆ、たれ、だし入りしょうゆなど |
|
漬物製造業 |
漬物、漬物を主原料とする食品 |
※参考:営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報|厚生労働省
営業届出が必要な食品
製造するための営業許可を得たうえで、追加で販売するための届出も必要な食品もあります。また、一部の食品は届出のみで製造可能な場合もあります。
厚生労働省のホームページを参考に、届出が必要な食品を一覧表にまとめました。
|
区分 |
業種 |
|
販売業 |
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
|
食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) |
|
|
乳類販売業(アイスクリームをのぞく) |
|
|
野菜果物販売業 |
|
|
米穀類販売業 |
|
|
氷雪販売業 |
|
|
弁当販売業 |
|
|
コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
|
|
自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗 浄・屋内設置)を除く) |
|
|
通信販売・訪問販売による販売業 |
|
|
コンビニエンスストア |
|
|
百貨店、総合スーパー |
|
|
その他の食料・飲料販売業 |
|
|
製造・加工業 |
添加物製造・加工業(第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く) |
|
いわゆる健康食品の製造・加工業 |
|
|
コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く) |
|
|
農産保存食料品製造・加工業 |
|
|
調味料製造・加工業 |
|
|
糖類製造・加工業 |
|
|
精穀・製粉業 |
|
|
製茶業 |
|
|
海藻製造・加工業 |
|
|
卵選別包装業 |
|
|
その他の食料品製造・加工業 |
|
|
上記以外のもの |
行商 |
|
集団給食施設 |
|
|
器具、容器包装の製造・加工業 |
|
|
露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの |
|
|
その他 |
営業許可・届出ともに不要な食品
販売する食品によっては、営業許可も届出も不要な場合もあります。
厚生労働省によると、以下のケースは公衆衛生への影響が小さいため許可も届出も不要です。
- 食品または添加物の輸入業
- 食品または添加物の運搬のみをする営業(ただし冷蔵・冷凍倉庫業はのぞく)
- 常温で長期間保存しても腐敗・変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
- 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
- 器具容器包装の輸入または販売業
※参考:営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報|厚生労働省
このように、仕入れた食品を加工せず販売する場合は、許可なく行えるケースもあります。しかし、仕入れた食品であっても、一度開封して小分けにした上で販売する場合は営業許可が必要になります。
そのため、手作り食品の製造には、基本的に営業許可もしくは営業届出が必要だと考えておきましょう。
そもそも、手作り食品(加工食品)の定義とは?
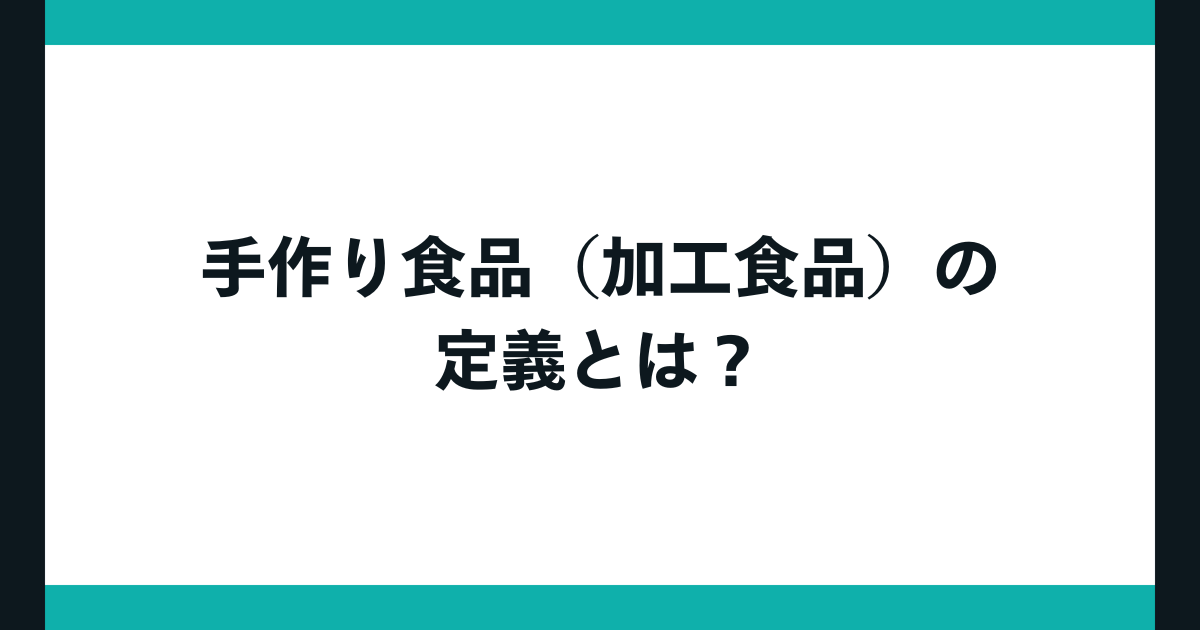
大半の加工食品の販売は保健所、自治体の許可が必要となりますが、そもそも、加工食品の定義とは、どのようなものなのでしょうか?
かんたんにいうと、加工食品とは、「食品になんらかの加工をした食品」のことです。
たとえば、自分の畑で作った野菜は、直売所などで自由に販売できますが、野菜は加工食品ではないので、許可が必要ありません。
ところが、カットした複数の野菜を混ぜ合わせた「サラダミックス」や「炒め物ミックス」などの野菜の場合なら、どうでしょうか。
じつは、これらは、それ自身がひとつの調理された食品である、という見解で、加工食品とされています。
そのほか、単品の刺身は生鮮食品ですが、複数の種類の刺身を盛り合わせたものは加工食品となるなど、判断に迷うケースが多いのも事実です。
はっきり判断できない場合には、消費者庁のQ&Aが役立ちます。消費者庁のQ&Aによると、農畜産物や水産物のうち加工食品にあたるものとして以下の例が挙げられています。
|
農産物 |
複数の野菜を切断した上で混ぜ合わせたもの(サラダミックス、炒め物ミックス) |
|
ブランチングした上で冷凍した野菜 |
|
|
畜産物 |
合挽肉 |
|
複数の部位の食肉を切断した上で調味液につけて一つのパックに包装したもの |
|
|
複数の種類の食肉と野菜を切断した上で、調味せずに一つのパックに盛り合わせたもの |
|
|
スパイスをふりかけた食肉 |
|
|
たたき牛肉 |
|
|
焼肉のたれを混合した食肉 |
|
|
パン粉を付けた豚カツ用豚肉 |
|
|
水産物 |
複数の種類の刺身を盛り合わせたもの |
|
尾部(及び殻)のみを短時間の加熱(ブランチング)により赤変させた大正エビ |
|
|
短時間の加熱(ブランチング)を行い殻を開けてむき身を取り出したアサリ |
|
|
鍋セット |
|
|
蒸しダコ |
|
|
塩蔵ワカメを塩抜きしたもの |
※参考:食品表示基準Q&A | 消費者庁
手作り食品を販売する上で、必要な条件一覧
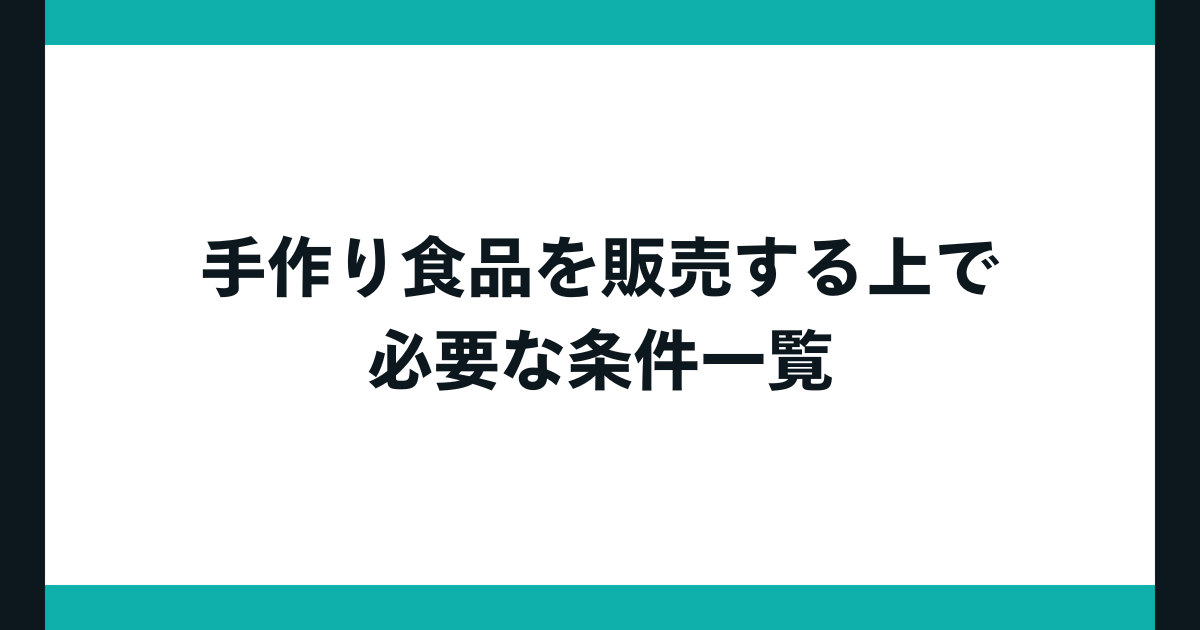
加工食品を販売するには、保健所からの営業許可をもらう必要があります。そして、許可を得るためには、「設備」と「人」に関する2つの条件をクリアする必要があります。
<加工食品の販売に必要な条件>
▶︎保健所からの営業許可の取得
↓
<営業許可の取得に必要な条件>
▶︎設備要件が整っているかどうか
▶︎食品衛生責任者が最低1人必要
それぞれどんな条件なのか、解説します。
保健所からの営業許可の取得
くわしい流れは後述しますが、許可を取得するには、まず施設所在地の保健所に問い合わせることになります。
どのような製品を、どのくらいの量、何人くらいの従業員で、どんな施設でつくるのか。
事前に計画を立てたうえで、専門の職員に相談するとよいでしょう。
相談から、実際に許可が下りて営業を開始できるようになるまでには、半月~3週間程度の日数が必要になります。
スケジュールを確認して、計画的に取得しましょう。
営業許可の取得に必要な条件①設備要件が揃っているか
設備要件とは、加工食品を作る作業場となる施設が満たすべき要件のことです。営業許可を受けるためには、2種類の施設基準を満たさなくてはなりません。
|
共通基準 |
自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準 |
|
特定基準 |
業種ごとに定められている基準 |
共通基準では、床の材料や明るさといった「営業設備の構造」、冷蔵庫などの「食品取扱設備」、「給水及び汚物処理」、という3つの要素について、こまかく満たすべき基準が定められています。
たとえば、「床と壁が交わる隅は、丸みをつける」「明るさは50ルクス以上」といった決まりがあります。
特定基準は、「飲食店営業」「喫茶店営業」「菓子製造業」といった、業種ごとに満たすべき基準が定められています。
※参考:施設基準(一般営業) | 食品営業はじめてナビ(東京都福祉保健局)
営業許可の取得に必要な条件②食品衛生責任者が最低1人必要
加工食品を販売するために営業許可を取得するには、人的要件として、食品衛生責任者1名を置くことも必要です。
食品衛生責任者とは、食品衛生上の管理運営をおこなう上で必要な資格を持つ人のことです。
食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、営業者が自主的に施設の衛生管理をおこなうために設けられた制度です。
食品衛生責任者になるためには、各都道府県の養成講習会を受講する必要があります。ただし栄養士や調理師、製菓衛生師など、一定の資格を持っている場合、受講が免除されます。
食品衛生責任者は、営業許可施設ごとに、1名必要です。複数の営業許可施設を兼任することは、認められていません。
食品表示ラベルの貼り付けも必要
手作り食品を販売する場合、食品表示法の規制対象にもなります。食品表示法とは、食品のパッケージについている原材料やカロリーなどが記載された「食品表示ラベル」を規定する法律です。
飲食店のイートインやテイクアウトのお弁当のように、製造場所で食品を直接手渡す場合は食品表示が必要ありません。しかし、製造場所と販売場所が異なる場合や、ネットショップで販売する場合、仕入れた食品を販売する場合には食品表示が義務づけられています。
食品表示ラベルへの記載が義務付けられている項目は、営業許可の業種によって変わってきます。たとえば手作りお菓子であれば、以下のような項目の表示が必要です。
<菓子製造業で必要な食品表示の項目>
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 製造者
- 製造所
- 栄養成分情報
営業許可を取るまでの流れ
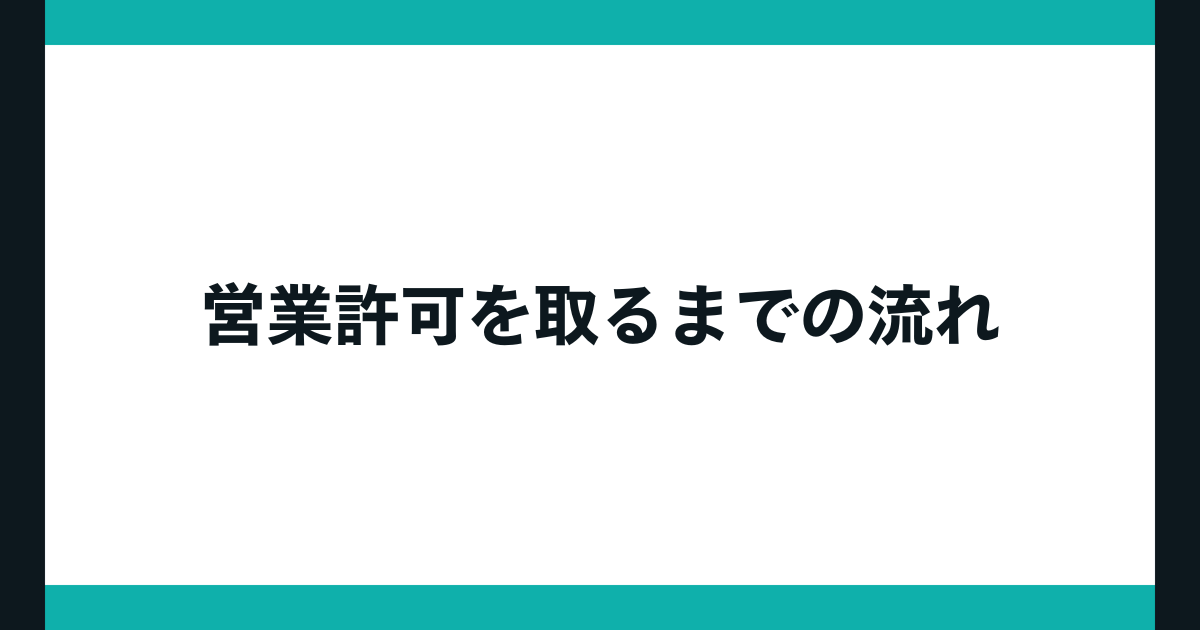
営業許可を得るための、具体的な流れについて説明します。
- 保健所に事前相談に行く
- 営業許可を申請する
- 施設検査をおこなう
- 営業許可書の発行
- 営業開始
まずは、保健所に事前相談に行きます。
販売施設や製造設備の工事を検討している場合には、かならず工事をはじめる前に相談しましょう。図面などを持参すると、話がスムーズです。
事前相談の時点で、施設や設備の確認、食品衛生責任者の選定、表示作成の準備、申請手続き方法の確認をおこないます。
表示作成の準備とは、販売のさいに商品に貼り付ける食品表示ラベルの準備のことです。
事前相談後、食品営業許可申請書を保健所に提出します。すくなくとも、営業をはじめたい1週間前までには提出しましょう。
申請後、書類審査がおこなわれ、施設検査日程の調整がおこなわれます。
保健所の食品衛生監視員による施設検査がおこなわれ、施設が基準に適合していれば、後日、食品営業許可書が交付されます。
万が一、施設検査で不適事項があった場合は、改善後に後日再検査を受けることになります。
取得にかかる所要時間の一例としては、事前相談に2日程度、営業許可申請から施設検査の実施まで7日程度、検査から許可書の交付まで7日程度です。
手作り食品のネット販売についての疑問Q&A
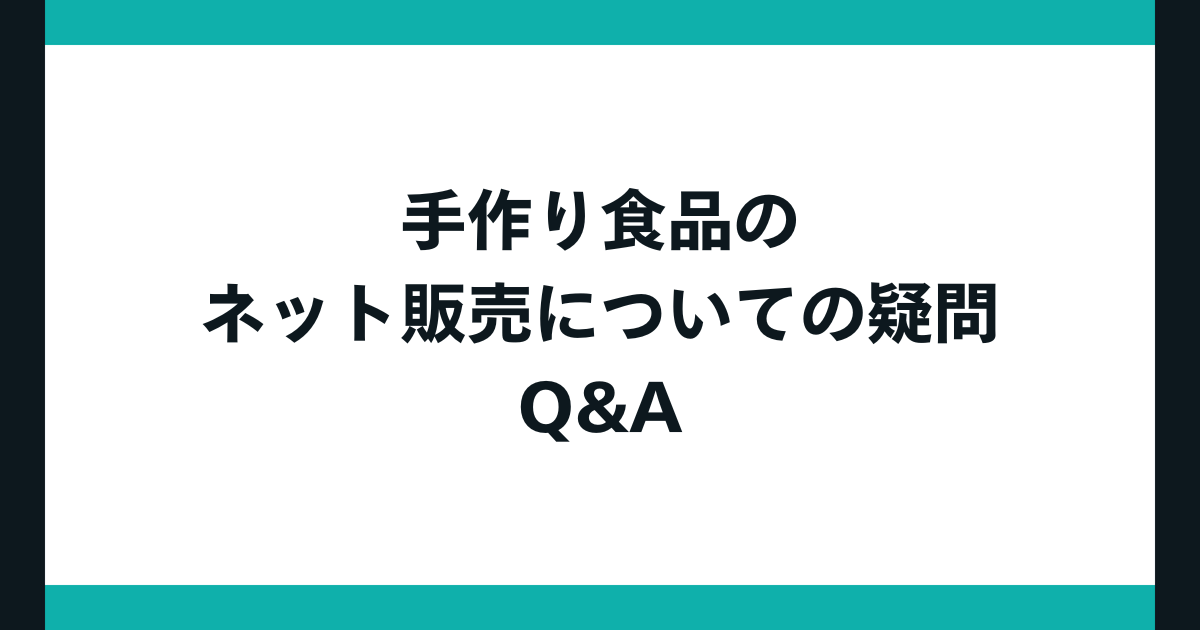
食品の加工販売に関する、よくある疑問を紹介します。
オンラインショップで販売するさいに必要な条件は?
基本的には設備要件を満たすこと、保健所からの営業許可をもらうこと、食品衛生責任者を置くこと、の3点です。
ただし、食品を作る場所と、作った食品の保管場所が異なる場合、それぞれの拠点に、販売する食品の種類に応じた営業許可が必要になるケースがあります。
かならず、施設の所在地を管轄している保健所に相談しましょう。
また、カフェや飲食店など、すでに店内での飲食の提供に対する営業許可をもらっている場合でも、オンラインショップで新たに食品を販売するケースでは、追加の営業許可が必要になることがあります。
この場合も、保健所に相談して判断を仰ぎましょう。
仕入れた加工食品を販売したい場合はどうする?
仕入れた加工食品を販売するのみであっても、許可や届出が必要な場合があります。
たとえば、乳類、食肉、魚介類など、保存方法に徹底した管理が必要となる食品の場合、販売するのみのケースでも、保健所の許可が必要です。
また、チーズの場合は、温度管理が必要なナチュラルチーズでは許可が必要になりますが、常温可能な粉チーズは、許可の必要がない、とされています。
基本的に、次の条件に当てはまれば、許可が不要となるケースが多いです。
- 販売時における、温度管理が不要
- 容器包装に入れられた食品である
- 仕入れた状態のままである
このように、食品の販売に関して、許可がいるかいらないか、は複雑です。
仕入れた加工食品であっても、販売したい場合は、必要な条件の有無について、管轄の保健所に相談することをおすすめします。
手作り食品の営業・ネット販売にあたっての注意点
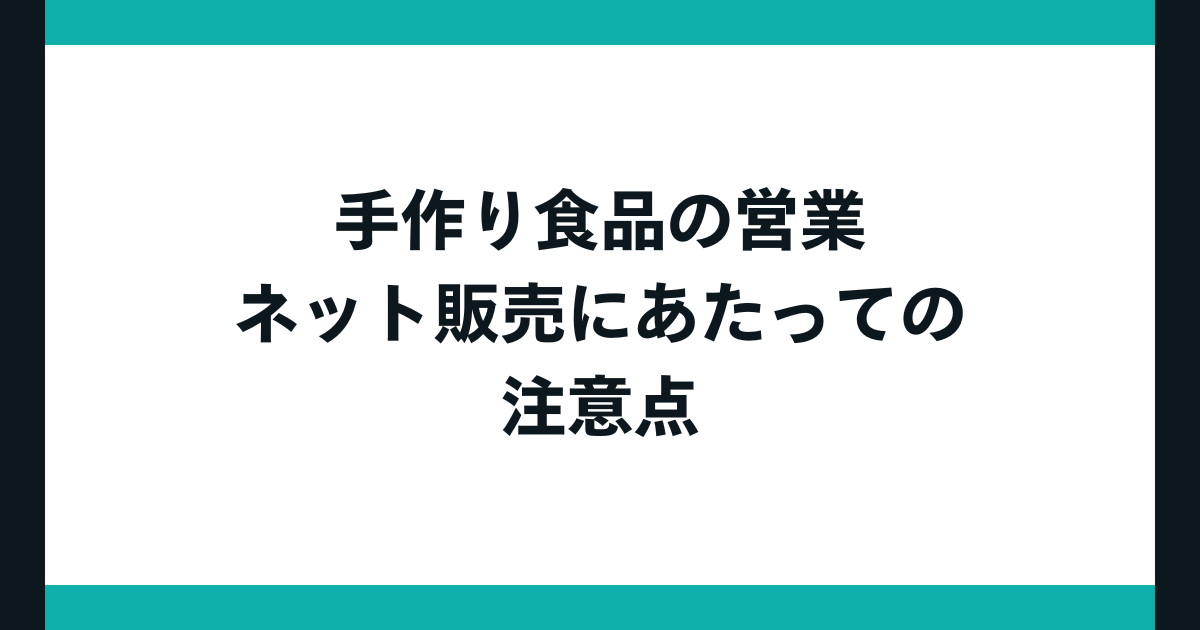
加工食品店の営業・販売にあたっては、いくつかの注意点があります。
専用の厨房が必要
ネットショップの普及で、個人で手作りした商品を販売したい、という人が多いですが、食品の場合、販売のハードルが高くなります。
たとえば、自宅で手作りしたケーキをネットショップで販売したい場合、自宅の台所ではない、専用の厨房を用意しなければなりません。
食品表示の義務もあり
また、営業許可の取得の流れでも触れましたが、加工食品の販売にあたっては、食品表示の義務があります。
営業するうえで、かならず知っておくべき食品表示について、くわしくは以下の記事をご覧ください。
手作り食品を販売するネットショップの事例
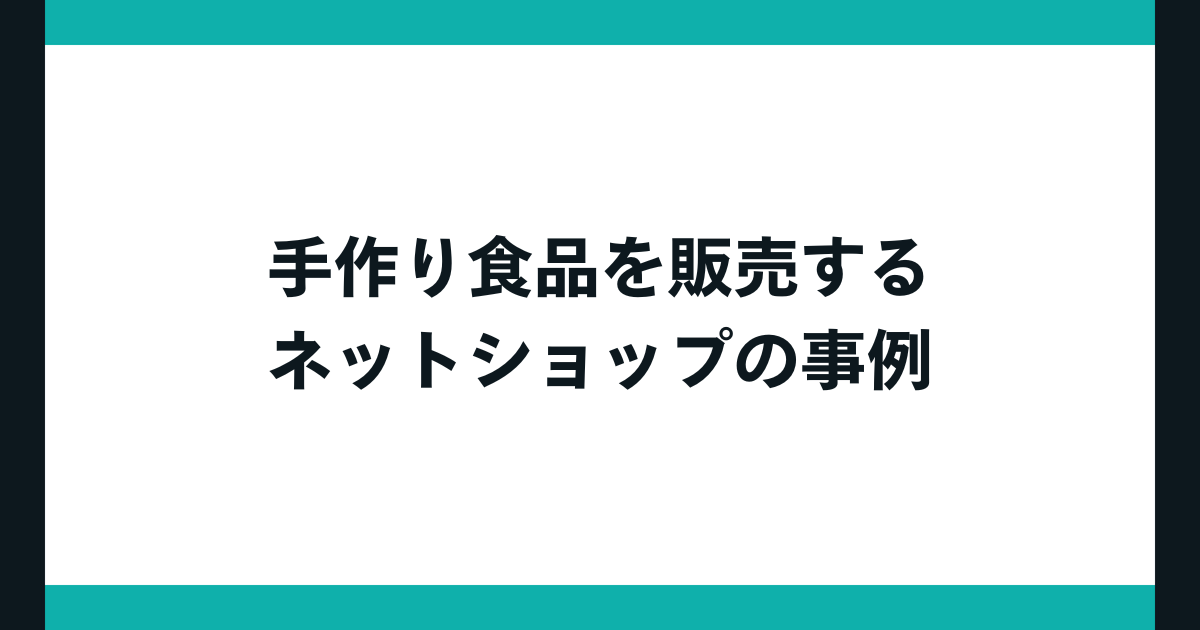
さいごに、BASEのネットショップで加工食品を販売する事例を紹介します。
Gypso(ジプソ)
卵や乳製品にアレルギーを持っている人や、ヴィーガンの人に向けたヴィーガンカヌレやクッキーをオンラインのみで販売するショップです。大学で栄養学を学んだオーナーが、月に一度のタイミングで販売しています。発送時はチルド便を使って、品質を保ちながら顧客に商品を届けています。
東京御吉兆
ショップ立ち上げのきっかけは、大学生がインターン先の税理士とともにうずら農場と、うずらの卵を使った名産品販売事業をはじめたことです。クラウドファウンディングで資金を募って実店舗を立ち上げて、うずらの卵を使ったプリンを製造しています。現在は月2〜3回の実店舗での販売を軸に、ネットショップやポップアップストアなどでの販売を通して、販売層を拡大しています。
まとめ
今回は手作り食品の販売を検討している方に向けて、製造・販売に必要な許可・届出の種類や、取得方法、必要条件について紹介しました。顧客の口に入る食品を取り扱うためには、衛生管理に最大限気を配る必要があります。
営業許可に関わる詳細な要件は、食品の種類や、施設のある都道府県によって異なるため、かならず所轄保健所に問い合わせるようにしましょう。
手作り食品販売の準備が順調に進んだなら、ぜひオンラインでの販売も検討してみてください。
遠方に住む顧客に自社の商品を知ってもらえるきっかけになるうえ、BASEのように固定費用が無料でネットショップを運営できるサービスもあるため、金銭的なリスクも心配ありません。
また、BASEは「売上を伸ばしやすいネットショップ開設サービスNo.1(※)」にも選ばれていますので、初心者でも安心してネットショップを運営できます。手作り食品をオンライン販売する際は、ぜひBASEをご活用ください。
※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)
売れるお店を作る機能とサポートが豊富
BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。
ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。
また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。
プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。
さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。
ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。
個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。