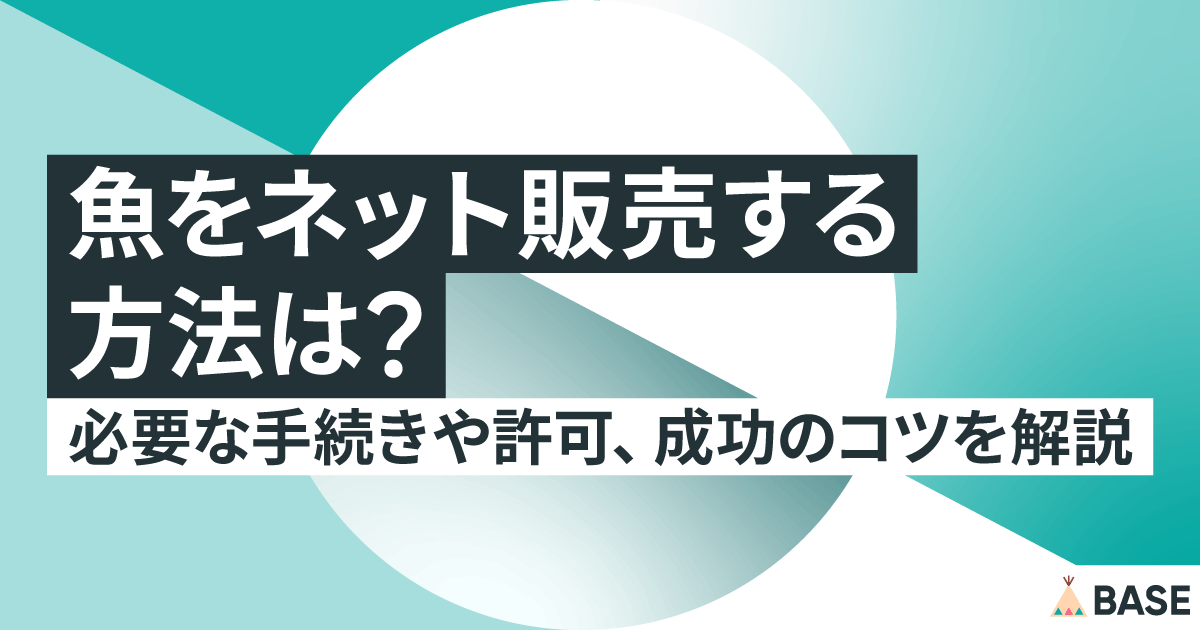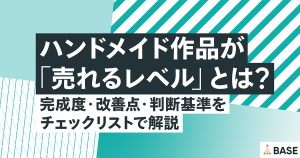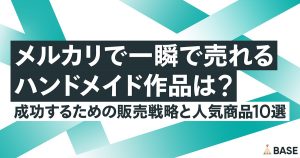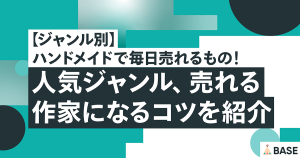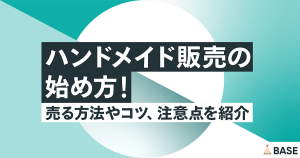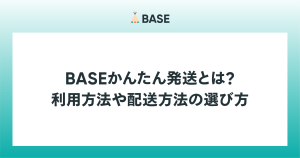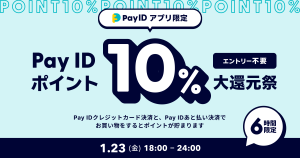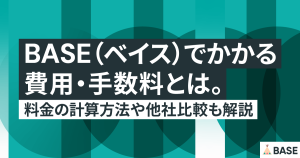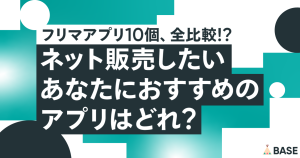漁師の方や鮮魚の加工事業を営んでいる方などで、「もっと利益を増やしたい」とお考えであれば、「ネット販売」という選択肢もありえるかと思います。
とはいえ、未経験の分野である場合、そもそも許可が必要なのか?どこでどうやって販売するのがいいのか?など、いろいろと不安もあるでしょう。
そこで今回は、ネットで魚を販売する場合の許可などに加えて、おすすめの販売方法や成功のコツなどを解説します。
【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ
- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです
- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます
- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています
- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています
ネットで魚を販売する方法は、大きく3つ
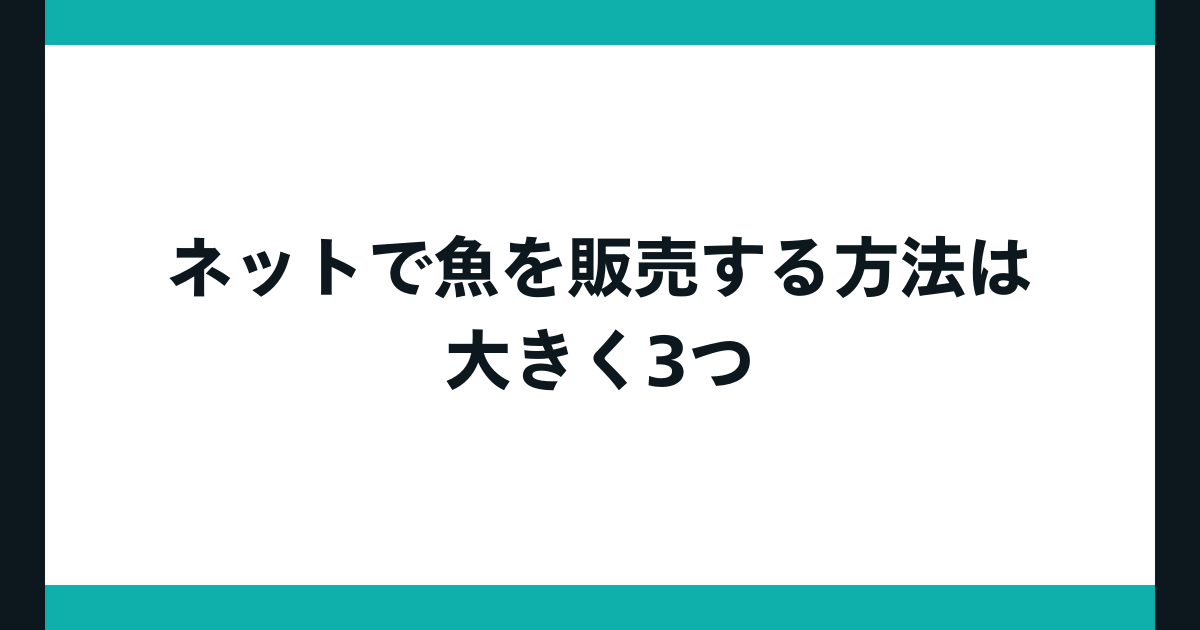
ネットで魚を販売する方法は、大きくわけて3つあります。それぞれのメリット・デメリットなどについて、見ていきましょう。
方法1. モール型ネットショップで販売
一つ目の方法は、Amazonや楽天市場Yahoo!ショッピングなどの、オンラインの大手ショッピングモールに出店する方法です。
これらの大手モールは、知名度が抜群に高いため、集客はしやすいです。
その代わり、出店費用や月額費用、販売手数料が高く、その分のコストが経営を圧迫する可能性もあります。
|
楽天市場「がんばれ!プラン」の出店にかかるコスト |
|
|
初期費用 |
60,000円 |
|
月額出店料(税別) |
25,000円/月(年間一括払い) |
|
システム利用料(税別) |
月間売上高の3.5〜7.0% |
|
楽天ポイント |
楽天会員の購入代金(税抜)×付与率(通常1.0%) |
|
モールにおける取引の安全性・利便性向上のためのシステム利用料(税別) |
月間売上高の0.1% |
|
楽天スーパーアフィリエイト(税別) |
アフィリエイト経由売上の2.6~5.2% |
|
R-Messe(税別) |
会話数に応じての従量課金+月額固定費:3,000円〜 |
|
楽天ペイ(楽天市場決済)利用料 |
月間決済高の2.5〜3.5% |
たとえば、楽天市場の場合では、上記のとおり、さまざまな項目で課金されるため、そこそこの売上高を達成しなければ、利益が出ない、という可能性もあります。
また、大手モールには、競合店も多く、そのなかでいかに自分のショップの商品を見てもらい、購入させるかのノウハウを学ぶ必要もあります。
とはいえ、集客力は圧倒的に高いので、人気が出れば大きな売上も狙えるでしょう。集客の手間を極力減らして、仕入れなどの業務に集中したい方におすすめです。
方法2. 自分のネットショップを開設して販売する
もう一つは、自分でネットショップを作成できる「BASE」などのネットショップ作成サービスを使い、自分のネットショップを開設して販売する方法です。
魚は収穫時期がある程度決まっているため、年間を通して販売するのは難しいケースも多いでしょう。そんなとき、モール型ネットショップのように月額費用が高額なサービスだと、収穫ができない期間は赤字が続いてしまいます。魚のように供給量が安定しにくく、不定期販売になりやすい商品を扱う場合は、月額費用が無料のBASEがおすすめです。
BASEは初期費用や月額費用がかからない「スタンダードプラン」を用意しています。商品が売れるタイミングでしか費用が発生しないため、収穫時期以外にも無理なく継続できるのも魅力です。
一方で、ショップへの集客は、自力で行わなければなりません。SNSや広告などによる集客をしながら、ショップを運営する必要があります。
自分でやらなければならないことは増えますが、地道にリピーターを増やしながらブランディングができれば、利益をしっかり上げることも期待できます。ショップデザインのオリジナリティを追求したい方や、ブランディングの確立に力を入れたい方は、ネットショップの開設にチャレンジしてみましょう。
BASEでは、スタンダードプランとグロースプランの2種類を用意していて、どちらでも同じ機能が使えることも魅力です。月商50万円以上のショップであれば、グロースプランの方がランニングコストを抑えやすくなります。
|
スタンダードプラン |
グロースプラン |
|
|
初期費用 |
0円 |
0円 |
|
月額費用 |
0円 |
16,580円 |
|
販売手数料 |
3.6%+40円 |
2.9% |
|
決済手数料 |
3% |
0円 |
そのほかのネットショップ作成サービスに関しては、下記の記事を参考にしてみてください。
方法3. 食べチョクなどの販売サイト
モール型ネットショップはハードルが高い、ネットショップで集客するのもおっくうだ……という方には、食べチョクやポケットマルシェなどの販売サイトもおすすめです。
どちらも、全国の生産者と消費者をつなぐオンラインマルシェです。基本的に、農産物や魚などを販売することを念頭にサービスが作られているので、使い勝手や機能は問題ありません。
ただ、問題は手数料です。これらのサービスは、固定費自体は無料となっていますが、たとえば食べチョクの場合は、販売時の手数料が8~18%となっています。
さきほど紹介したBASEと比べると、非常に高い設定となっているので、そのあたりも踏まえながら、自分に適した手法を考えることが重要です。
|
食べチョク |
ポケットマルシェ |
|
|
初期費用 |
無料 |
無料 |
|
月額費用 |
無料 |
無料 |
|
販売手数料 |
8〜18%(2021年5-7月の実績値) |
23% |
フリマアプリでの販売はNG
近年は、メルカリやラクマなどのフリマアプリを活用して、食料品や飲料品を販売する方も増えてきています。
しかし、フリマアプリでは、衛生上の理由から生物の販売は禁止されています。残念ながら魚のネット販売には活用できないので、ここまで紹介したモールやネットショップなどの手段を選びましょう。
魚のネット販売でおさえておきたいこと|許可や法律は?
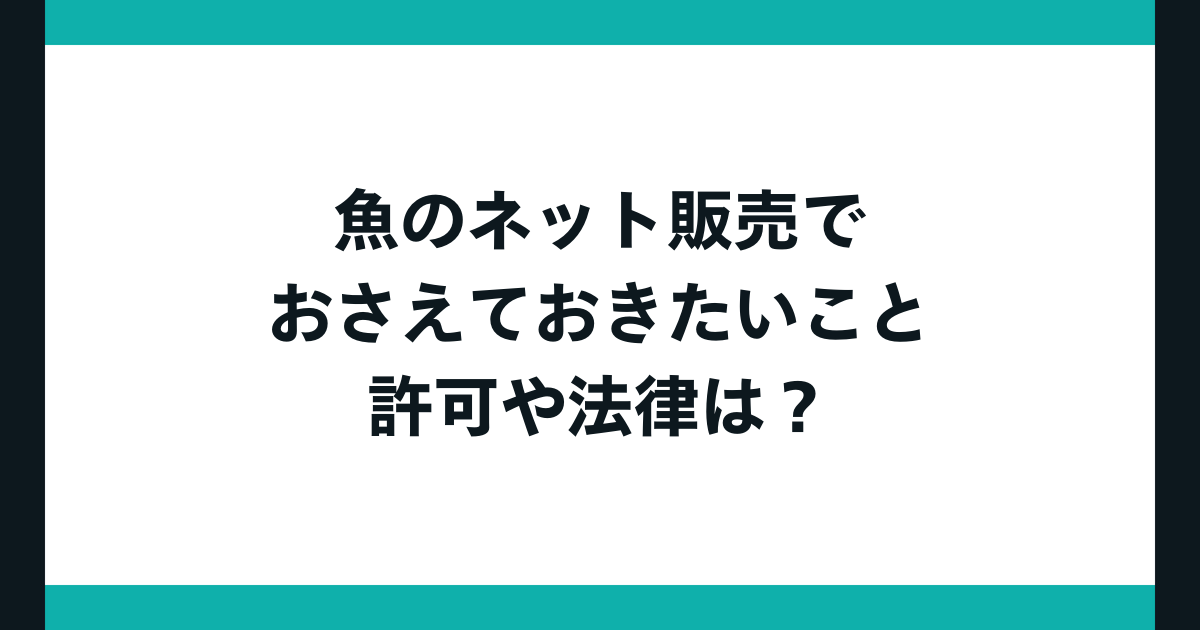
ネットショップで食品を取り扱う場合には、ネットであったとしてもリアルであったとしても、どちらも食品衛生の観点で、必要となる許可や知識が必要です。
どのようなことをおさえておくべきなのか、見ていきましょう。
保健所の許可は必要?
魚介類に限らず、食品を扱った営業を行う場合には、かならず保健所に確認のうえ、販売をはじめるようにしましょう。
基本的には、食品衛生法にのっとって「営業許可」が必要になります。許可を受けるには、「食品衛生責任者」の資格を持つ人を1名以上配置しなければなりません。
また、設備要件として、保管施設のチェックも入ります。
飲食店や実店舗で魚介類の販売をしている場合には、すでに食品衛生責任者がいるはずですが、はじめてネットショップを運営する場合には、まずは管轄の保健所に相談してみましょう。
なお、一口に魚介類の販売と言えど、鮮魚なのか加工したものなのかなど、その販売形態によって「魚介類販売業」「魚介類加工業」「食品の冷凍または冷蔵業」「そうざい製造業」などの許可が必要となることが考えられます。
参考までに、東京福祉保健局の営業許可種類一覧を見ると、食品の種類や加工方法などによっても、必要な許可がこまかく分類されています。
例として、保健所に魚介類の販売許可を得るために必要な要件をまとめました。
各自治体の条例によっても、必要な許可や手続きなどが異なるため、かならず管轄の保健所に問い合わせて、必要な手続きを行ってください。
食品衛生責任者
魚に限らず、食品を販売する場合は食品衛生責任者の資格が必須です。食材の管理だけでなく、食中毒を起こさないように設備や従業員の衛生管理、健康管理を担います。
なお、食品衛生責任者は、都道府県知事に指定された養成講座を受講することで取得可能です。
魚介類販売業の許可
食品販売では、食品衛生責任者の資格に加えて、販売するものに応じた営業許可が必要です。魚を切り身などにして売る場合は、「魚介類販売業」の許可を得る必要があります。
生きた魚や魚介類を売る場合は不要ですが、ネットショップは魚をさばいて販売するケースが多いので、基本的には必須となります。
水産製品製造業の許可
干物や練り物、イクラのしょうゆ漬けや明太子など、水産物を加工して販売する場合に必要な許可です。
冷凍食品製造業の許可
魚の切り身やイクラなどを冷凍食品として販売する場合は、冷凍食品製造業の許可を得る必要があります。
なお、冷凍食品製造業の許可が不要な冷凍食品も、「冷凍冷蔵倉庫業」の届出が必要になる可能性があるため注意しましょう。
開業届は必要?
法人またはすでに開業届を提出済の個人事業主、としてネットショップを開設する場合には必要はありませんが、はじめて事業としてはじめる場合には、開業届を提出しておきましょう。
仮に提出しなかったとしても、罰則規定はありませんが、節税面でのメリットが受けられないなど、デメリットもありますので、出しておく方がいいでしょう。
賞味期限や消費期限の表記は必要?
食品を販売する場合には、食品表示法により「食品表示ラベル」を貼ることが義務付けられています。
東京都が公開している「食品表示 食品表示法 食品表示基準手引編<統合版>」によると、切り身になっている状態もふくめた魚介類の場合には、次のような表示が必要です。
原産地・・・原産国や採取水域名などを表示します。(例:「しじみ(荒川)」、「さけ(石狩川)」、「【輸入】ブラックタイガー(ベトナム)」)
解凍・・・冷凍したものを解凍した場合には表示します。
養殖・・・給餌を伴う養殖の場合には表示します。給餌を伴わない場合には表示の必要はありません。養殖だからと言って必ず給餌を伴うわけではありません。
加工者氏名や加工所在地
生食用(刺身用)の旨
消費期限・・・期限が短い場合には時間まで表示することがあります。
保存方法・・・例:「10℃以下で保存しなければならない」、「4℃以下で保存」
加工してある旨・・・干ものなどの加工をしてある場合には表示します。
このほか、もし加工した魚介類を販売する場合には、栄養成分やカロリー、アレルゲンの有無、添加物などについても、表示する必要があるようです。
魚の賞味期限・消費期限はいつまで?
魚は傷みやすいので、賞味期限ではなく消費期限が設定される場合が多いでしょう。賞味期限は食品をおいしく食べられる期限、消費期限は食品を安全に食べられる期限を指します。
万が一、お客さんが傷んだ魚を食べてしまうと重篤な健康被害を招きかねないため、経験則などの主観による設定は適切ではありません。理想としては 微生物試験や理化学試験などの客観的な検査項目について、安全係数を設定したうえで消費期限を設定するのがよいでしょう。
ただし、食品一つひとつに対してそれを行うのは難しいので、類似する食品の検査結果を参考にして設定することも可能です。
詳しくは、厚生労働省と農林水産表が公表している「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を参照してください。
魚のネット販売を成功させるコツ
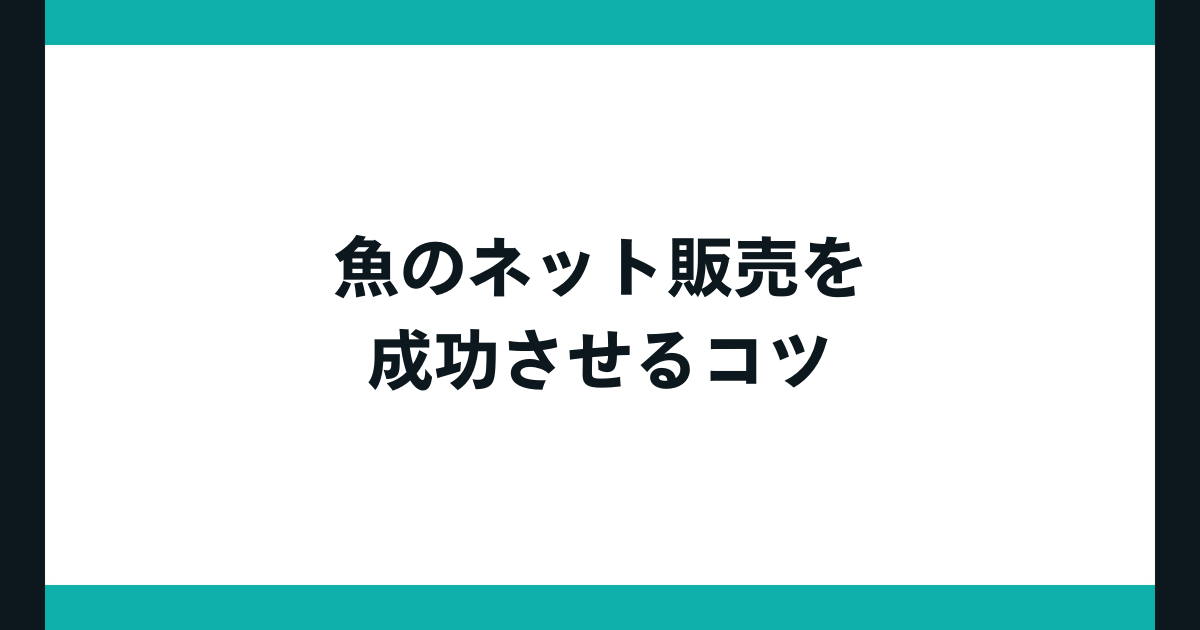
魚のネット販売を成功させるためには、以下のポイントをおさえることが重要です。
スーパーとの差別化を図る
魚のような生鮮食品は、自宅近くのスーパーで買うという人が大半です。スーパーとの差別化を図るために、ネット販売では一般的にはあまり見かけない、少し珍しい魚を取り扱うとよいでしょう。
地元の人しか知らないようなローカルな魚や、知名度が高くブランド性のある魚をラインナップに加えるのもおすすめです。
人柄や流通までの過程を伝える
生産者の顔が見える商品は安心感につながり、消費者に手にとってもらいやすい傾向があります。
とくに、ネット販売は商品の実物を確認できない分、顧客に安心感を与えることが大切です。ネットショップや商品ページなどで魚が流通するまでの過程を伝えれば、ネットで生鮮食品を買うことの心理的ハードルを下げられるでしょう。
お得に買えるB級品を用意する
ネットショップで生鮮食品を購入する人のなかには、「近所のスーパーよりもお得な商品」を求めている人が多くいます。
通常よりもリーズナブルに買える商品を用意することで、そういった層にもアプローチしやすく、売上アップにつながるでしょう。
ネットショップ運営を成功させる一般的なコツは、こちらの記事が参考になります。
ネットショップを作るなら「BASE」。操作もかんたん!スマホでの販売も可能
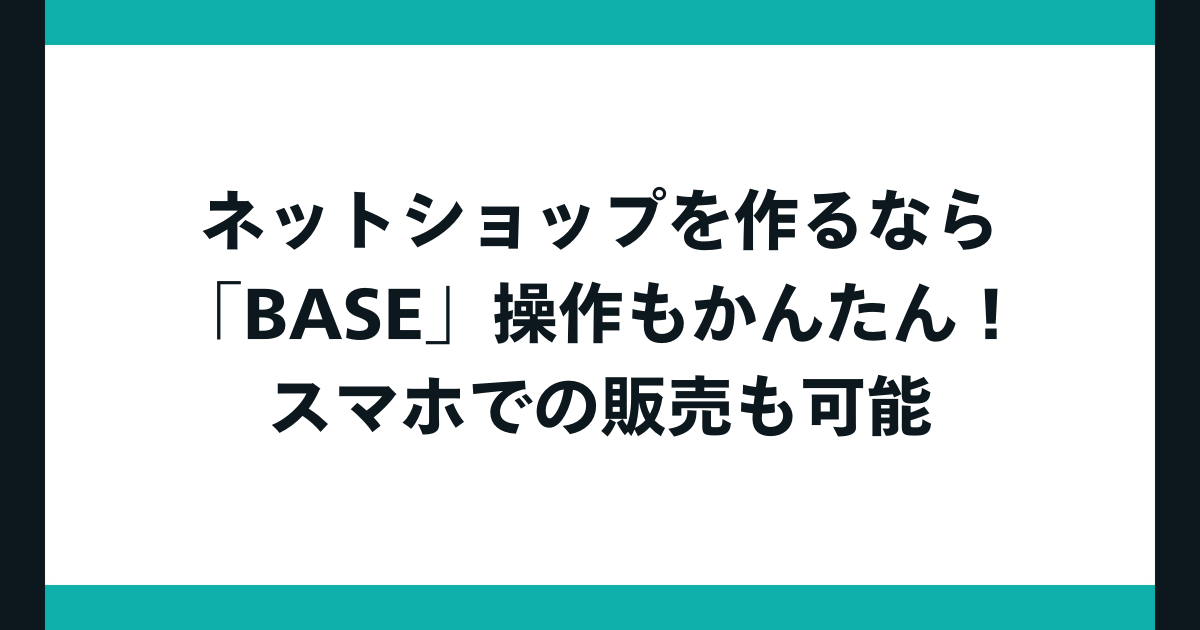
さて、ここまで魚のネット販売についてお伝えしてきました。
販売方法は大きく3つありますが、もしネットショップを作ってみたい、という場合は、7年連続ネットショップ開設実績No.1(※)の「BASE」をおすすめします。
※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)
BASEの特徴は、とにかく操作がかんたんであること、そして初期費用・月額費用ともに無料で利用できることです。
また、BASEは、スマホだけでも操作が行えるので、パソコン操作に不安がある方も安心です。
魚は鮮度が命です。商品を収穫・調達・入荷してから、商品写真を撮影し、ネットショップ上に商品情報をアップロードするまで、この一連のプロセスをスピーディーに行う必要があります。
BASEはスマホから商品登録ができるので、SNSに写真を投稿するような感覚でかんたんにサクッと商品情報をアップロードできるのが強みです。
テイクアウトという手法も
すでに実店舗を持っている場合は、ネット通販ではなく、テイクアウト販売という選択肢もあります。
実際にBASEでショップを開設している海鮮ふじ様では、BASEのテイクアウト機能を利用して、販売を行っています。
魚のネット販売についてのよくある質問
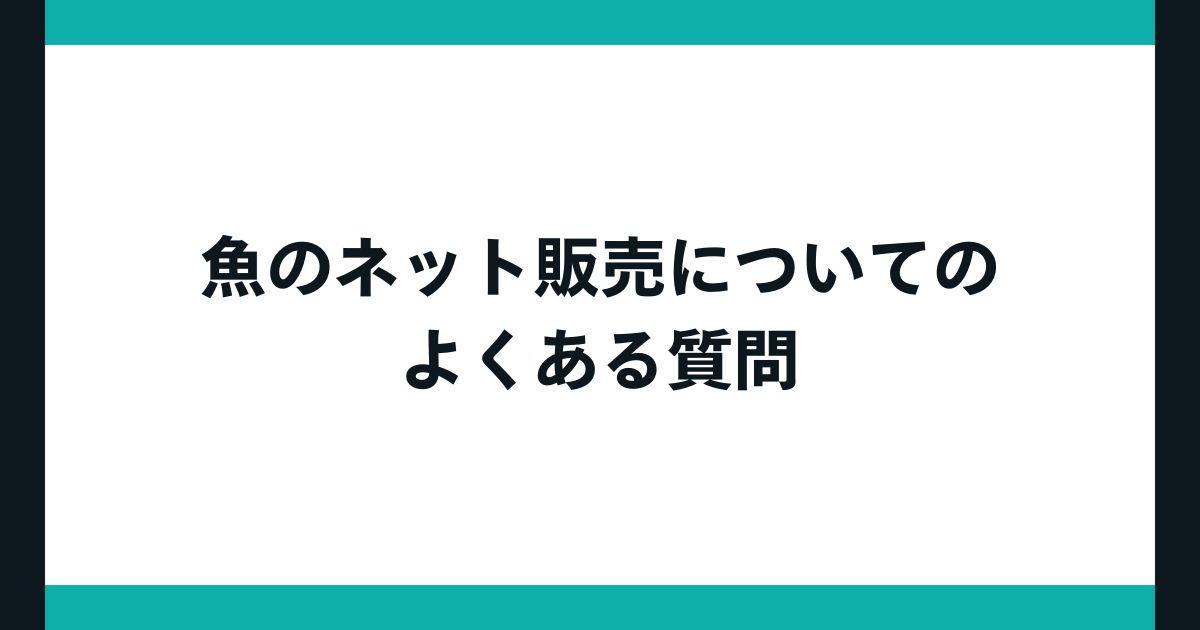
最後は、魚のネット販売に関するよくある質問にお答えしていきます。
配送方法はどうすればよい?
魚は生ものなので、配送方法にはくれぐれも注意が必要です。配送中に商品が傷むことのないよう、クール宅急便や冷凍便を利用しましょう。BASEならヤマト運輸との連携が可能なうえ、クール便にも対応しています。そのため、販売から発送までをシームレスにつなげられます。
▶関連記事:あんしん・かんたん・べんり。発送にかかる手間をなくす、ヤマト運輸連携サービス
また、魚の鮮度を保ったままお客さんに届けるには、梱包方法に気を使うことも大切です。やり方はいくつかありますが、ヤマト運輸が紹介している梱包手順が参考になります。
- あらかじめ品物を以下の温度・時間保存しておく
- 冷蔵品:10°C以下で6時間以上
- 冷凍品:-15°C以下で12時間以上
- 品物を取り出し、ジップロックに入れて密閉する
- 緩衝材で品物を保護する
- 緩衝材を敷き詰めた段ボールに品物を入れ、緩衝材で動かないよう固定する
詳しい手順やポイントは、ヤマト運輸のページからご確認ください。
趣味で釣った魚を売る場合も販売許可は必要?
趣味で釣った魚であっても、ネットショップで販売する場合は保健所の許可が必要です。ただし、釣りに関しては採ってはいけない生き物の種類や、釣りをしてはいけない場所などの厳格なルールがあるので、十分注意しましょう。
まとめ
今回は、ネットで魚や海鮮系の食品を販売するために必要なことについて、説明してきました。
ご覧いただいたとおり、ネットショップで食品を取り扱う場合には、営業許可や食品衛生責任者資格を取る必要があります。また、食品表示法で定められた食品ラベルの貼付など、知っておくべきことも多いです。かならず管轄する保健所へ問い合わせて、必要な届出などについて、確認するようにしましょう。
BASEなら、初期費用0円で気軽にネットショップを開設できます。配送日設定や販売期間設定など、食品のネット販売に役立つ便利な機能も満載です。
魚や海鮮系の食品をネットショップで販売するなら、ぜひBASEをご検討ください。
売れるお店を作る機能とサポートが豊富
BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。
ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。
また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。
プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。
さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。
ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。
個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。