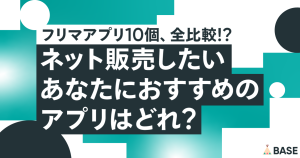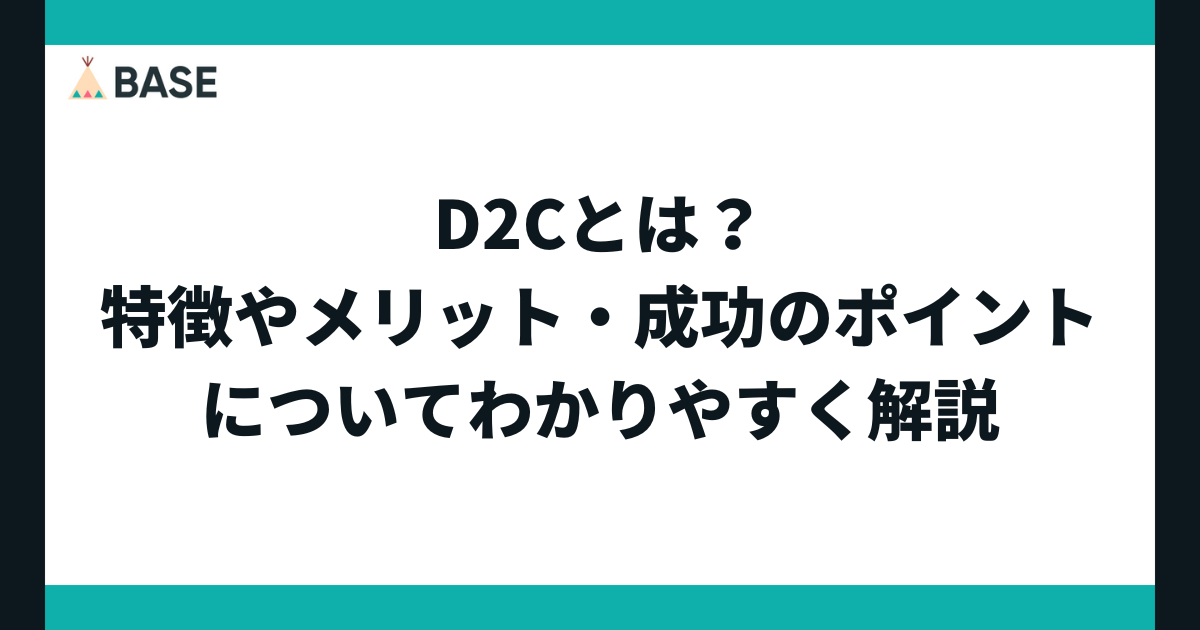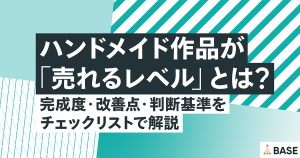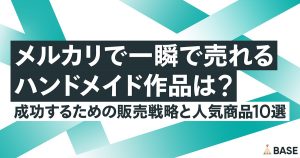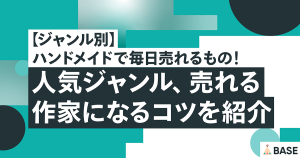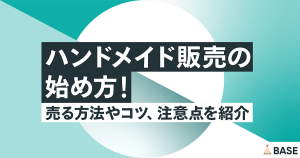近年よく聞かれるようになった販売形式である「D2C」。
「D2C」は、2000年代後半から登場したビジネスモデルです。D2Cの市場規模は、2025年に3兆円に達すると予測されており、注目の販売形式といえます。
(参考:「デジタルD2C」の市場動向調査|売れるネット広告社@Press)
今回は、D2Cの基礎知識から、メリット・デメリットなどについて解説します。D2Cを成功させるためのポイントもご紹介するので、参考にしてみてください。
D2Cとは?意味と特徴について
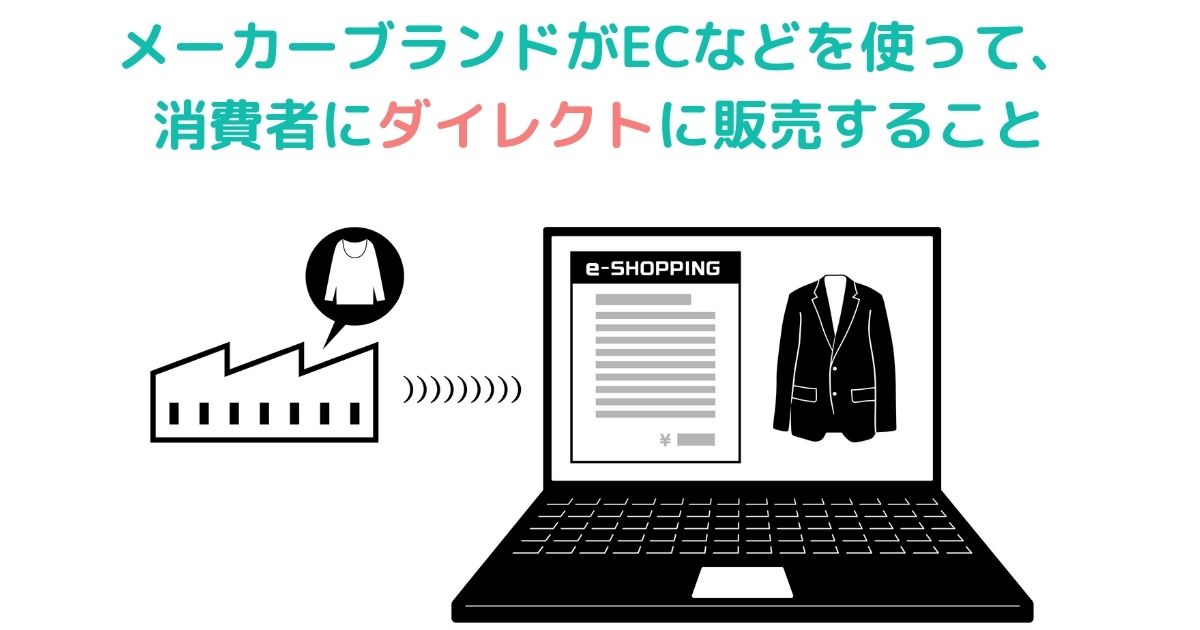
D2Cとは、「メーカーやブランドが自社で企画・製造した商品を、自社が運営するECサイトを通じて、直接消費者に販売するビジネスモデル」のことです。
「Direct to Consumer」を略した言葉で、他にも「DtoC」や「DTC」とも略されます。また、日本語で「消費者直接取引」とも呼ばれます。
D2Cにおいて、消費者と直接つながり製品を届けるためには、一般的に EC サイトが用いられます。一方で、中には自社で運営する実店舗での販売を行う企業も存在します。
つまり、販売手法であるECの中のひとつの業態が、D2Cであるといえます。
企業が直接消費者にサービスや商品を提供するモデル自体は、それほど目新しいわけではありません。
しかしながら、D2Cでは卸や流通、小売といった中間業者を介さず、メーカーが商品の企画製造から、あらゆる自社メディアを通じての販売、アフターフォローまでをする点が大きく異なります。
また、EC市場の拡大にともない、ネットショップ作成サービスも数多く普及してきたことで、誰もがECに参入しやすくなってきました。
このことによって、これまではモノ作りに特化してきた企業にとっても、自社ECに取り組みやすくなったことが、D2C市場の拡大を後押ししています。
D2Cのメリット
D2Cならではのメリットについて、説明していきましょう。D2Cには、企業だけでなく、顧客にとってもメリットがあることがわかります。
6つのD2Cのメリット
- 収益性を向上させる
- 顧客との接点を直接持てる
- LTVを高め、事業を安定化させる
- コストが削減可能に
- 販売方法の自由度が高い
- 顧客データを蓄積しやすい
メリット1. 収益性を向上させる

1つめのメリットは「収益性を向上させる」です。
D2Cは、販売ルートに卸や流通、小売などの中間業者を挟まない分、中間マージン費用を大幅に削減することができ、企業の収益を増やすことができます。
たとえば、開発から販売までのすべてを自社が行い、販売は自社で管理するEC サイトで行っているとします。
その場合、流通のコストカットだけでなく、代理店などへの手数料も削減することができ、企業の収益が増えます。
メリット2. 顧客との接点を直接持てる
メリット2は「顧客との接点を直接持てる」ことです。
D2Cでは、顧客とのやりとりを企業が直接おこなうため、コミュニケーションを取る機会も多くなり、顧客と企業との間の心理的な距離感も自然と近くなります。
そのため、従来よりもっと身近なコミュニケーション手法を取り入れることも可能になります。
たとえば、SNSなどを使えばインタラクティブなコミュニケーションも可能になり、これまで直接聞くことがなかった顧客の本音を拾う機会も増えます。
顧客にとっては、自分の声を直接伝えることができ、企業にとっては顧客の声を商品やサービスの改善につなげることができます。顧客満足度や顧客ロイヤリティ向上といった相乗効果を得られる可能性が高まります。
メリット3. LTVを高め、事業を安定化させる

メリット3は「LTVを高め、事業を安定化させる」です。
顧客ロイヤリティを高めていくことができると、LTV(Life Time Value)を最大化することも可能になります。
LTVとは、日本語では「顧客生涯価値」と訳されます。
顧客が、ある企業との関係を持つ間に使った(もしくは使う予定の)金額の合計のことです。
新規顧客を獲得し収益を得るためには、既存顧客から同じ額の収益を得るのと比べて、「5倍のコストがかかる」と言われています。
一方で、一度築いた顧客との関係性を、良好に維持することができれば、何度も同じ顧客から商品やサービスを購入してもらえる、優良顧客を育てることができるようになります。
いわゆる「リピーター」を創出することができます。
LTVを最大化することで、新規顧客獲得のためのコストを低くおさえ、収益性を改善することができるだけではなく、優良顧客化することで、中長期的に継続した売上を見込めます。
さらに、優良顧客の声を商品やサービスに反映させることで、さらに満足度を高めて、継続期間を長期化することもできるようになれば、事業の安定化が期待できます。
メリット4. コストが削減可能に

メリット4は、「コストが削減可能に」なることです。
D2Cでは、中間業者を介さず、自社のメディアを使って販売するため、従来の販売方法と比べて、さまざまなコストを削減することができます。
D2Cでは、卸や流通、販売代理店などへ支払っていた中間マージンだけでなく、ショッピングモールなどへの出店費用、販売手数料なども不要となります。
また、基本的にD2Cでは小売店を必要としないことから、店舗の家賃や人件費といった固定費も削減できます。
こうして削減されたコストは、商品の価値向上や販売価格の引き下げなど、顧客へのメリットとして還元したり、マーケティング施策の改善に使って売上を伸ばしたりなどに使うことができます。
メリット5. 販売方法の自由度が高い

メリット5は「販売方法の自由度が高い」ことです。
たとえば、代理店や卸など、販売ルートに他社が介在している場合、メーカー側が実施したいキャンペーンやポイント制度の導入ができない、といった販売方法の自由度が低くなりがちです。
D2Cでは、こうした他社の事情に左右されることもなく、自由に自社のサービスや販売方法の改善をおこなうことができます。
そのため、販売方法に顧客の声を反映するまでのリードタイムやコストも小さくなります。
また、メーカーや商品の独自色を出した施策もおこないやすく、インフルエンサーやアンバサダーを起用したキャンペーンなども可能となります。
こうした独自性を出すことで、競合との差別化をはかり、価格競争になることも避けられます。
メリット6. 顧客データを蓄積しやすい

ショッピングモール型サイトで販売する場合、販売データ以外の顧客情報は、ショッピングモール運営者のものとなり、販売者へは提供されません。
自社ECサイトなら、顧客の属性や購入履歴、サイト内の導線など、あらゆる情報を活用することができます。
たとえば、顧客データを分析セグメント化することで、効果的な情報配信の方法や頻度を変えて優良顧客化していくことや、サイト内の行動データを分析することで、ECサイトの改善や潜在的な顧客のニーズを拾うこともできます。
また、D2Cではあらゆるメディアを活用して、商品の販売機会や顧客との接点を作る活動をおこなえるので、顧客データの蓄積方法も多様です。
D2Cのデメリット
D2Cにもメリットばかりではなく、デメリットもあります。これからD2Cを検討している企業やオーナー様が注意すべき点について、説明します。
デメリット1. 集客コストがかかる

デメリット1は、「集客コストがかかる」点です。
顧客が商品を購入してもらうためには、まず自社サービスや商品を認知してもらうことが必要です。どんなに素晴らしい商品があっても、認知されなければ購入してもらえません。
すべて自社で自由にできるD2Cは、購入してもらうための集客も、すべて自社でおこなう必要があります。
大手のショッピングモール型サイトなら、似たような商品が売られていることも多く、口コミなども豊富なので、顧客の方から商品を探しに来てくれます。そのため、出品すれば、すぐに知ってもらうことができ、集客の労力はさほどかかりません。
一方、D2Cの場合には、認知度も信頼度もほぼゼロからのスタートです。
顧客に認知してもらうための広告出稿や魅力的なコンテンツの作成、SNSの運用など、集客のためのコストや計画を立てておきましょう。
デメリット2. 商品の魅力が問われる

デメリット2は「商品の魅力が問われる」点です。
D2Cに限らず、大々的なキャンペーンや、マーケティングにコストをかけても、そもそも商品に魅力がなければ購入してはもらえないのは、どの販売手法でも同じです。
売上を獲得するには、他社にはないオリジナリティ溢れる商品が必要です。そのためにも、消費者の口コミやレビューを見ながら改善し続け、商品の魅力を磨き続けることが必要です。
デメリット3. 商品が売れるまで時間がかかる

デメリット3は「商品が売れるまで時間がかかる」点です。
D2Cでは、販売するためのECサイトが完成してからも、ファンを育てていくための時間が必要です。
まずは、見込み客の集客をおこない、商品を買ってもらうために信頼関係をつくり、自社商品やサービス、あるいは自分の企業や会社自身を好きになってもらわなければなりません。
そのためには、商品やブランドのヒストリーやアイデンティティ、魅力などを十分に伝えられるような優良なコンテンツを、提供し続けていく必要があります。
このように、見込み客を顧客にするためには、ブランド力を高めながら、じっくりと時間をかける必要があります。
そのため、商品が売れて、ビジネスが軌道に乗るまでは、どうしても時間がかかりやすく、コストも必要です。
D2Cを成功させる3つのポイント
ここまでD2Cのメリット・デメリットを見てきました。メリット・デメリットを踏まえて、D2Cを成功させるポイントを3つ見てみましょう。
ポイント1.競合に負けない商品力・ブランド力
D2Cを成功させるためには、他の企業にはない商品力・ブランド力が必要です。
ありきたりな、競合他社と似たような商品では、自社サイトでの購入はむずかしいでしょう。
自社商品の購入につなげるためには、独創的な世界観で、自社ブランドのファンを作る必要があります。
また、一定のブランド力がなければ、お客様がリピーターになってくれる可能性は低くなります。そのため、商品力とブランド力の両方が重要です。
ポイント2.マーケティングによるコンテンツ力
自社ECを立ち上げただけでは、顧客が集まることはありません。
そのため、有益なコンテンツや商品への想いを発信するなど、コンテンツマーケティングを行い、集客をおこなう必要があります。
どれだけすばらしい商品を持っていても、ユーザーに認知してもらわなければ、商品が売れることはありません。
オウンドメディアなどを活用して顧客にコンテンツを訴求し、商品やサービスの認知度を高めることが重要です。
ポイント3.SNSを活用し顧客と交流する
D2Cを成功させるためには、SNSの活用が必要です。
InstagramやTwitter、TikTokなどで、新商品情報の発信やライブ配信をおこない、顧客と交流を図ることは、D2Cを成功させる重要なポイントと言えます。
また、顧客と交流することで新たなニーズを掴むこともできます。
自社ブランドを成長させるためにも、SNSを活用した顧客との交流は積極的に行う必要があります。
D2Cを成功させるための、顧客とのコミュニケーションなら「BASE」がおすすめ!

ここまでD2Cの成功ポイントについて、解説してきました。
成功までの近道は、やはり「顧客との関係を築くこと」にあります。
新しい商品やサービスにあふれている現代では、「新規顧客の獲得コストより、既存顧客の維持の方がはるかにコストがかからない」とも言われています。
マーケティングコストをおさえつつ、安定した事業継続をおこなうためには、既存顧客のロイヤリティを高めてLTVを向上させる、CRM(顧客関係管理)施策が重要です。
そこで、D2Cのメリットでもある顧客との接点を活用し、関係性を深めるコミュニケーションが大事なポイントになります。
「具体的にどうしたらいいのかわからない」、そんなECサイト責任者の方もいることでしょう。
ネットショップサービス「BASE」(ベイス)なら、D2C成功のポイントとなる顧客とのコミュニケーションも、次のような連携ツールで簡単におこなうことができます。
「BASE」で使える、顧客との関係値を高めるおすすめ機能
Instagram販売 App
「Instagram販売 App」を使って、Instagram / Facebookにショップの商品情報を連携することで、Instagramの投稿に商品をタグ付けして、「BASE」の商品販売ページへ直接リンクさせることができます。
Instagramの商品情報を強化することで、より多くのInstagramユーザーに向けてショップをアピールでき、新たなお客様を獲得につながります。
TikTok商品連携・広告 App
「TikTok商品連携・広告 App」を使えば、BASEに登録している商品の広告をTikTokに出稿することが可能です。
10〜20代の若年層を中心にしながらも、近年は20代以上の利用率も増えている「TikTok」。自社のターゲット層に合わせて、導入を検討してみましょう。
メンバーシップ App
「メンバーシップ App」は、かんたんにショップ独自のメンバーシップを作成でき、会員のお客様とのつながりを深められる拡張機能です。
会員のお客様に専用のクーポンを配布できるなど特別な体験の提供が可能となっており、さらに多くのファンを獲得するのにぴったりの機能です。
どの機能も、かんたんに導入可能となっています。ぜひ導入してみてください。
まとめ

自由度が高く、中間コストや店舗などの固定費を削減することができるD2Cモデル。商品の機能性に加えて、ストーリーやアイデンティティなどの付加価値を顧客に提供し、コミュニティを醸成することが成功のカギになります。
SNSやコミュニティサイトなどを使い、顧客とのコミュニケーションを深めながら、顧客ロイヤリティを高め、LTVを最大化していきましょう。
「BASE」なら、コミュニケーションツールとの連携もかんたんなので、おすすめです。
気になる記事を探す
よくあるお悩みから探す
- 何からはじめればいいか不安
- 商品の準備方法がわからない
- サービス選びを失敗したくない
- 販売開始までの手続きがわからない
- 売上が伸び悩んでいる
- 集客のやり方がわからない
- デザインや商品の見せ方に自信がない
- ショップ運営がうまく回らない
キーワードから探す
商品・ジャンルから探す
関連記事
人気記事
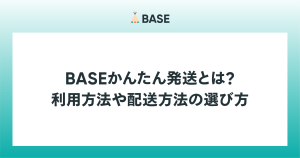
BASEかんたん発送とは?利用方法や配送方法の選び方
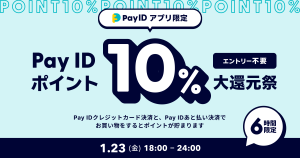

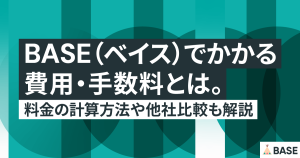
BASE(ベイス)でかかる費用・手数料とは。料金の計算方法や他社比較も解説