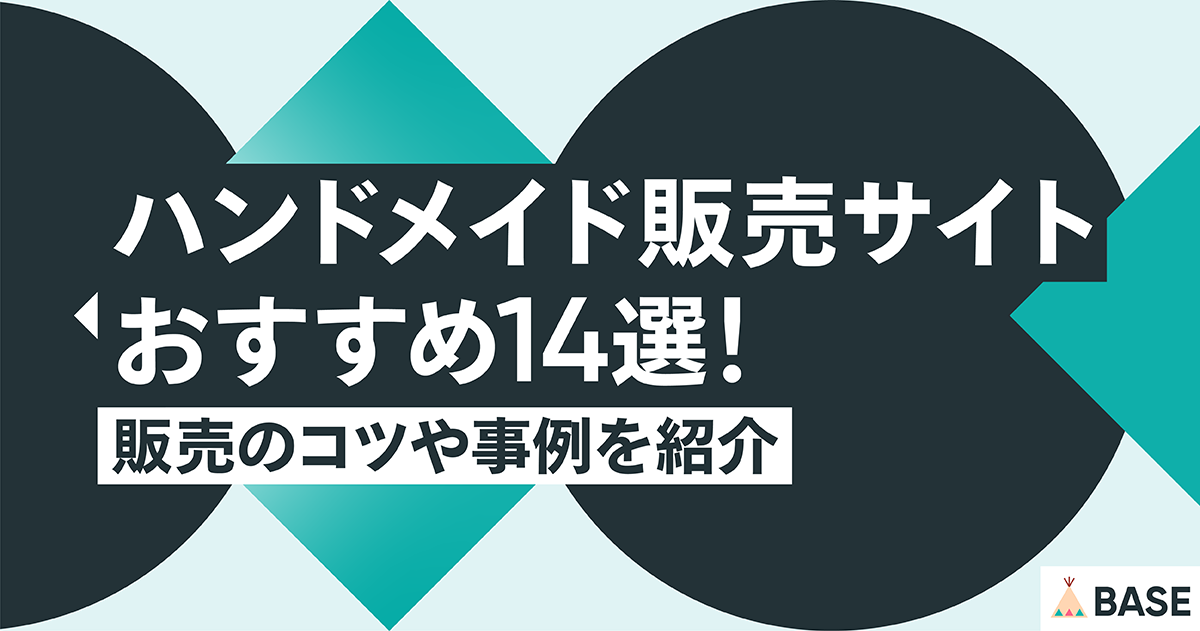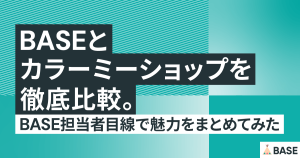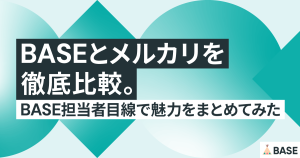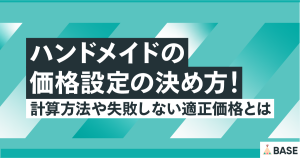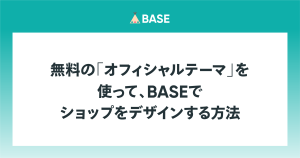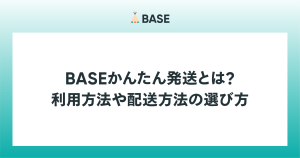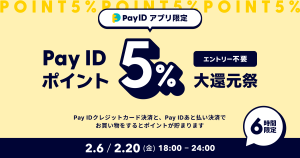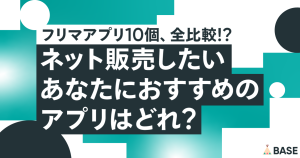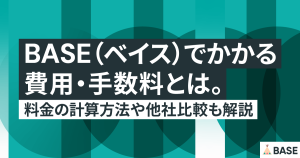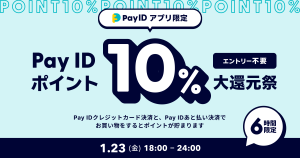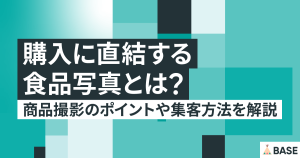
ハンドメイド作品を販売したいけれど、「どうやって売ればいいの?」「たくさんあるサービスの中からどれを選べばいいかわからない」と悩んでいませんか?
ハンドメイド販売には、イベントや委託販売などさまざまな方法がありますが、最も手軽に始めやすく、多くの人に作品を届けられるのがネット販売です。ハンドメイドを販売できるサイトは数多くあるので、自分にぴったりのものを見つけるのは大変かもしれません。
本記事では、ハンドメイドの主な販売方法、おすすめの販売サイトを厳選して紹介し、売上を伸ばして稼ぐための具体的なコツもお伝えします。
【この記事でわかること】
- ハンドメイドの販売方法は、ネットでの販売、イベントでの販売、委託販売、実店舗での販売の4種類。
- ネットでハンドメイドを販売できるサービスは、ハンドメイドマーケット、ネットオークション、ネットショップ、フリマアプリが代表的。
- ハンドメイドで稼ぐためには、ブランドコンセプトとターゲットの明確化、リピーターを獲得しやすい販売方法の選定、InstagramやTikTokなどのSNSを駆使した集客、材料費以外のコストの抑制などの工夫が必要
ハンドメイドの販売方法は大きく4つ
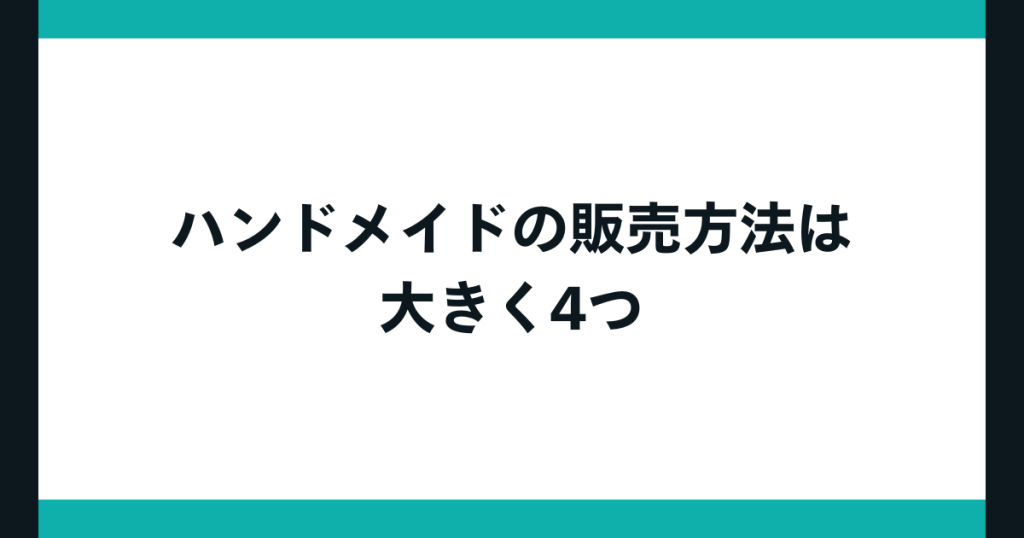
ハンドメイド作品を販売する主な方法は、大きく分けて以下の4つがあります。
- ネットでの販売
- イベントでの販売
- 委託販売
- 実店舗での販売
それぞれにメリット・デメリットがあるため、作品のジャンルや販売スタイル、かけられる時間や費用などを考慮して、最適な方法を選びましょう。
ネットでの販売
場所や時間に縛られず、全国の顧客に作品を届けられるのがネット販売の最大の魅力です。自宅にいながら販売活動ができ、販売サイトによっては初期費用0円ではじめられるため、最も手軽でリスクが少なく始めやすい方法と言えます。
主な販売先としては、ハンドメイドマーケット(minne、Creemaなど)、フリマアプリ(メルカリ、ラクマなど)、ネットショップ(BASE、STORESなど)があります。いずれもインターネットを通じて幅広い層に作品をアピールできる利点がありますが、集客力やブランディングの自由度など、サービスによって特徴が異なります。
| メリット | デメリット |
| 場所・時間に縛られない初期費用や在庫リスクを抑えられる全国(国内外問わず)の顧客に届けられる | 実物を手に取って見てもらえない多くの競合に埋もれやすい商品撮影、説明文作成、集客などを自分で行う必要がある |
イベントでの販売
フリーマーケットや展示即売会、クラフトフェアなど、オフラインでのイベントに出店して作品を販売する方法です。
顧客と直接コミュニケーションを取り、作品の魅力や制作への想いを対面で伝えられるのが大きなメリットです。顧客の反応をダイレクトに知ることができ、今後の作品制作や価格設定のヒントにもなります。
ただし、出店料や交通費、設営費用などがかかるほか、イベント当日の天候や集客状況に売上が左右されることが懸念点です。
| メリット | デメリット |
| 顧客と対面で交流できる実物を手に取って見てもらえる作品の魅力や想いを直接伝えられる | 準備に費用と時間がかかる天候や立地に売上が左右されやすい販売機会がイベント開催時に限られる |
委託販売
雑貨屋・カフェなどの実店舗やネットショップのオーナーに作品を預け、販売を代行してもらう方法です。
販売や店舗運営をプロに任せられるため、作品制作に集中できるのが魅力です。集客力のある店舗やネットショップを通じて多くの人に作品を見てもらえるチャンスもあります。
しかし、売上から委託手数料が差し引かれるため、自己販売に比べて利益が少なくなる点や、そもそも委託販売先を見つけるのが難しい点が懸念点です。
| メリット | デメリット |
| 販売・在庫管理の手間がかからないプロの集客力を利用できる作品制作に集中できる | 委託先を見つけるのが難しい手数料が高額になり、利益率が下がりやすい販売価格や陳列方法などを自由に決められない |
実店舗での販売
テナントを借りたり自宅の一角に販売スペースを設けたりして、対面販売する方法です。自宅の敷地内に余裕があれば、手軽に実店舗販売をはじめられます。
ただし、マンションや賃貸物件などで、自宅に不特定多数を招き入れたり、管理規約により事業を行ったりすることが難しい場合は、テナントを借りる必要があります。人通りの多いエリアにテナントを借りられれば集客力を期待できますが、そのぶん家賃が高額になります。また、営業時間には常駐する必要があるので、制作時間が持てなかったり、販売スタッフの人件費が別途必要になったりすることも懸念点です。
一方で、実店舗という自分だけの空間が持てるのは、他の販売方法にはない魅力でしょう。また、作品を実際に手に取ってもらえますし、接客しながら作品の魅力を直接伝えることも可能です。ポップアップストアのように期間限定で実店舗販売する方法もあるので、他の販売方法からのステップアップする際は検討してみてください。
| メリット | デメリット |
| 自分だけの空間が作れる商品の魅力が伝わりやすい立地によっては集客しやすい | 家賃や光熱費、人件費など、ランニングコストが高額実店舗に作家自身が常駐する場合、作品制作に集中しにくい販売時間が限られる |
ハンドメイド販売におすすめのサイト
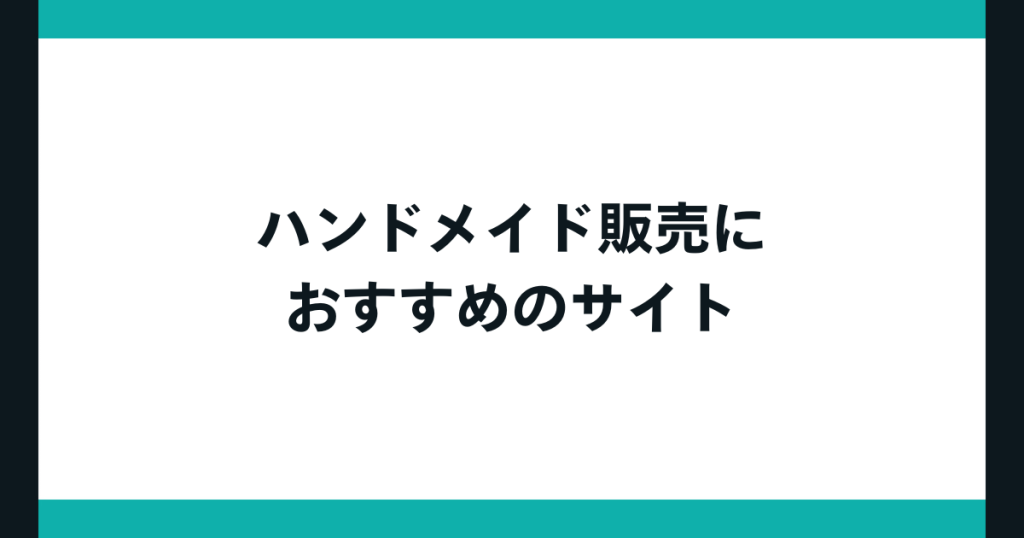
ネットでハンドメイド作品を販売できるサービスは数多くありますが、大きく4つに分類できます。
- ハンドメイドマーケット:ハンドメイド作品の売買に特化したプラットフォーム
- ネットオークション:入札形式で価格が決まる仕組みで、希少性の高い作品などを競り形式で販売できるプラットフォーム
- ネットショップ:個人が独自ブランドのオンラインショップを開設できるサービス
- フリマアプリ:中古品・新品など幅広い商品を取引するプラットフォーム
どのサービスを選ぶかで、集客力、利益率、ブランディングの自由度が大きく変わってきます。販売方法ごとのメリット・デメリットを紹介しつつ、おすすめのサイトを厳選して紹介します。
| 販売方法 | 主なサイト例 | 費用相場 | メリット | デメリット |
| ハンドメイドマーケット | minne、Creema、Iichi、Etsy、Pinkoi | 販売手数料10% | ハンドメイドに興味があるユーザーが集まるため集客しやすい | 他の作家と比較されやすい独自のブランドを打ち出しにくい |
| ネットオークション | ヤフオク! | 販売手数料10% | 希少性の高い作品は高値がつきやすい | 希望価格で落札されるとは限らない |
| ネットショップ | BASE、STORES、Shopify、カラーミーショップ | 販売手数料3〜5% | ショップデザインの自由度が高くブランドの世界観を表現しやすい手数料が比較的安い | 集客を自分で行う必要がある |
| フリマアプリ | メルカリ、楽天、ラクマ | 販売手数料6〜10% | ユーザー数が非常に多く幅広い層に作品を見てもらえる | 中古品や既製品に埋もれやすい値下げ交渉される可能性がある |
ハンドメイドマーケット
ハンドメイドマーケットは、ハンドメイド作品の売買に特化したプラットフォームです。
ハンドメイド作品に興味があるユーザーが多く集まるため、集客に力を入れなくても、作品が多くの人の目に触れるチャンスがあるのが最大のメリットです。初めてネット販売に挑戦する方や、まずは手軽に作品を販売してみたい方に向いています。
一方で、多くの作家の作品と並んで表示されるため、価格やデザインなどで他の作家と比較されやすく、InstagramやTikTokなどのSNSのショップ機能と連携できないことが、ブランド構築やリピーター獲得を目指す上での懸念点となります。
minne
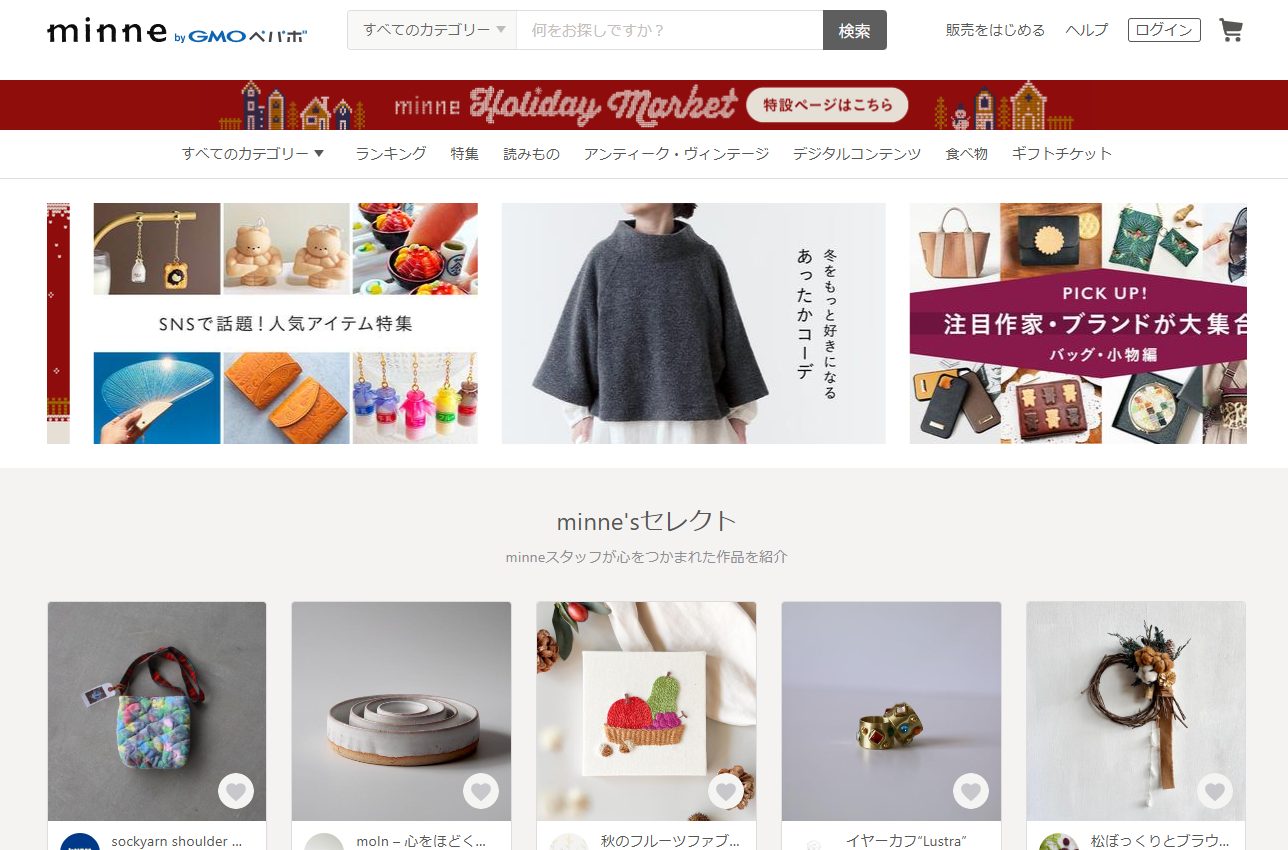
minne(ミンネ)は、GMOペパボ株式会社が運営する、国内最大級の規模を誇るハンドメイドマーケットです。ハンドメイド作品を購入したい顧客に限定して商品をアピールできるため、高い集客力が魅力です。
販売手数料は送料を含めて10.56%と明確で、初めての方でも安心して利用できます。また、販売者の負担ゼロで海外発送にも対応しているため、海外進出の足がかりにもなります(一部の国と地域限定)。
Creema

ハンドメイドマーケットの先駆けであるCreema(クリーマ)は、国内大手ハンドメイドマーケットにおいてクリエイター1人あたりの売上・商品単価がNo.1のサービスです(参考:公式サイト)。minneと比較すると、家具のように大型の作品も多く出品されています。
成約手数料は11%で、オンライン、オフラインともに販売を促進するサポートが充実している点が魅力です。具体的には、大規模イベントやポップアップストアなどオフラインでの販売サポートのほか、商品をプロモーションできる広告配信機能や、クーポン・キャンペーンなどを自由に設定できる機能が提供されています。
iichi
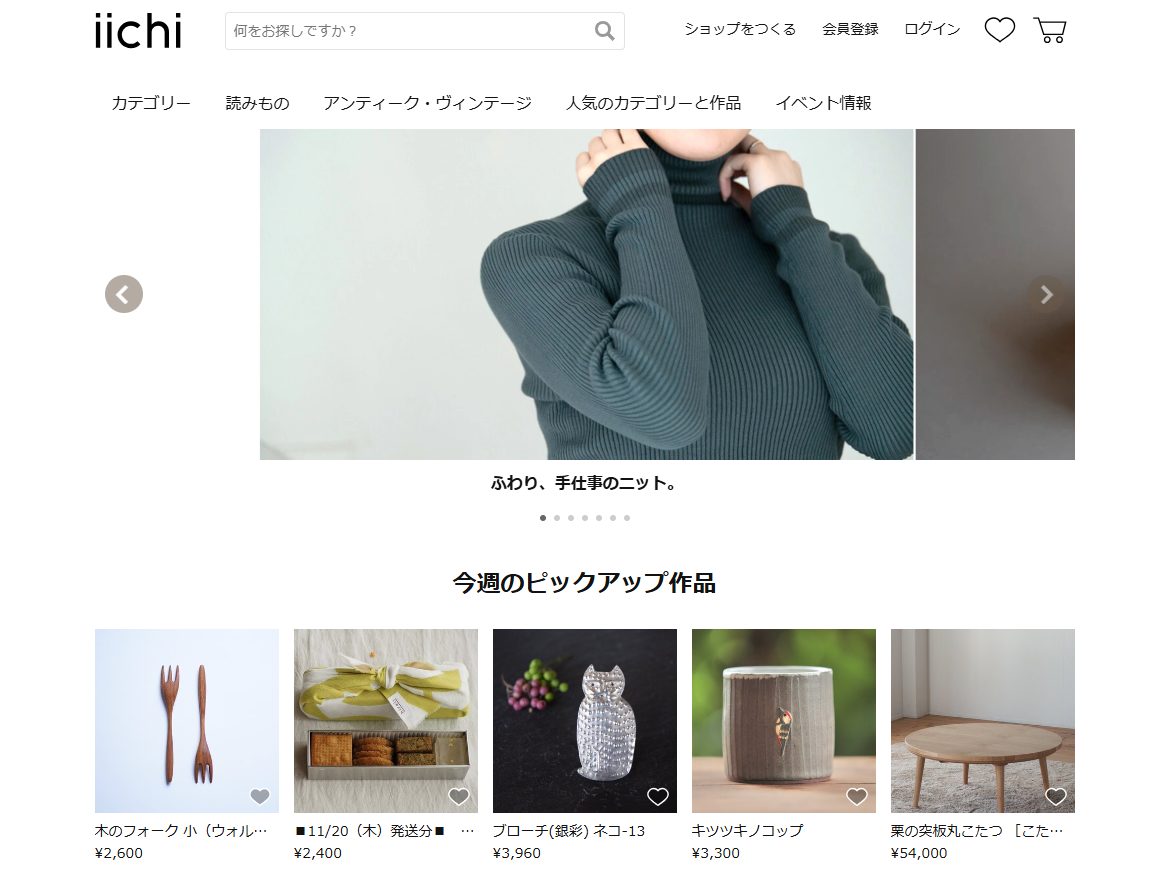
iichi(イイチ)は、個人や小規模な作り手による「ものづくり」を大切にしているハンドメイドマーケットです。プロが作るハイクオリティな商品や、工芸品、アンティークなど、オーナーの技術が光る商品が多く販売されており、単価の高い商品やアートを販売している人におすすめです。
注文から取引完了までを「取引ナビ」がサポートしてくれるため、安心して取引を進められます。商品への反応がわかる「お気に入り」や「アクセス解析」機能も。また、商品販売だけでなく、イベントやワークショップなどの告知も可能です。
Etsy
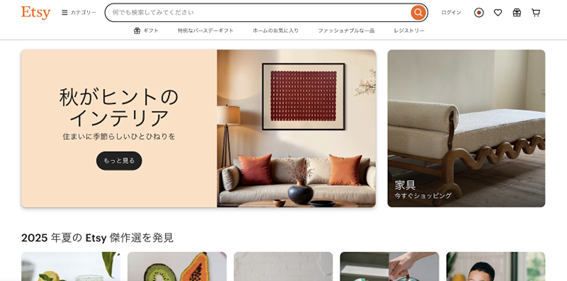
Etsy(エッツィー)は、アメリカを中心に世界中で利用されているグローバルなハンドメイドマーケットです。世界中にユーザーがいるため、国内だけでなく海外顧客への販路を広げたいクリエイターや、グローバルブランドを目指す方に向いています。
サイトや出品画面は日本語に対応しており、ショップの開設もスムーズです。海外販売を成功させるには、商品タイトルや説明文を英語表記に対応するのがおすすめです。
手作り作品に加え、ヴィンテージ品やクラフト素材の販売も可能で、越境EC(海外向けのオンライン販売)の実績やノウハウが豊富に蓄積されています。
Pinkoi
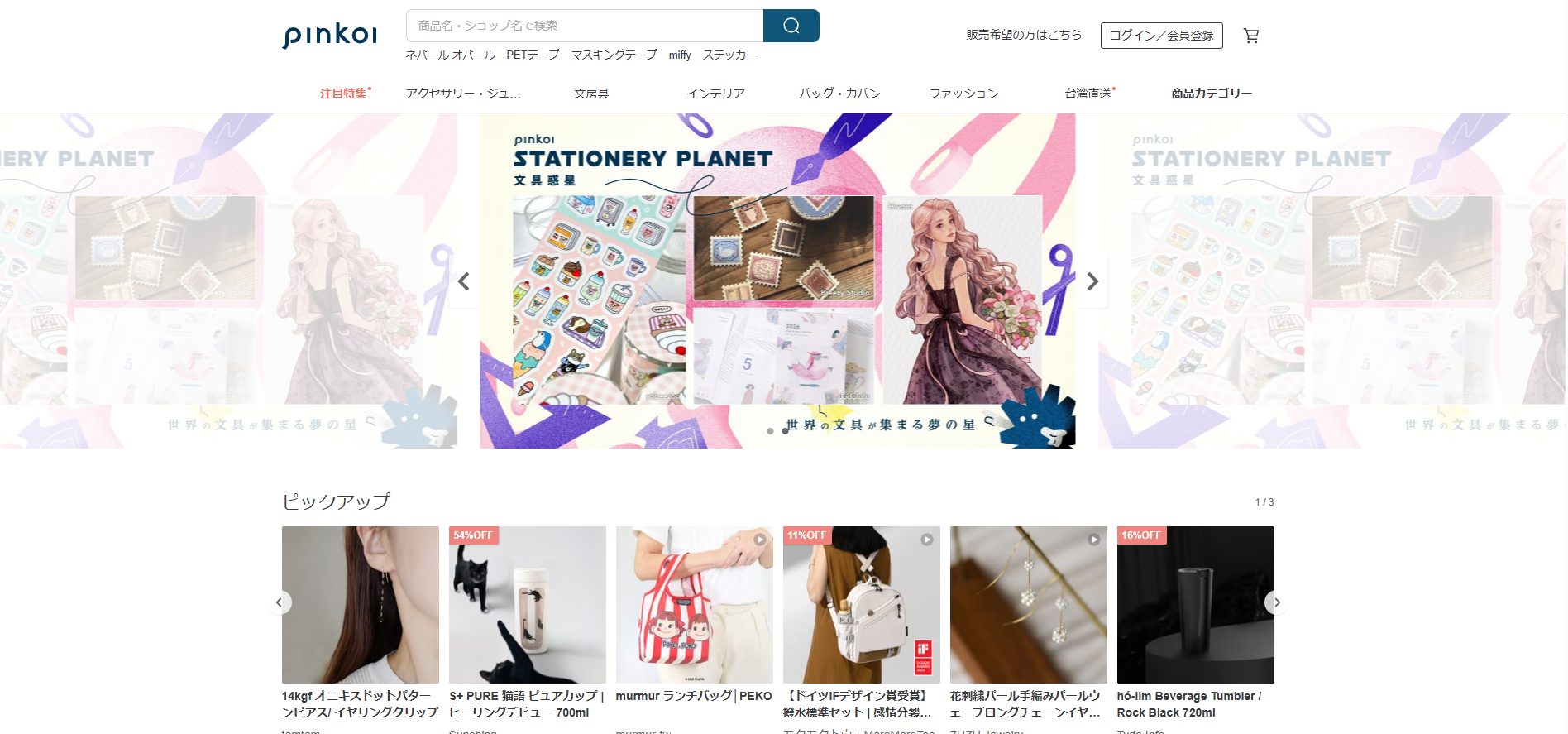
Pinkoi(ピンコイ)は、台湾発のアジア最大級デザイナーズマーケットです。アジア圏に多くのファン層を持つため、海外販売の中でも特にアジア市場に強い越境ECプラットフォーム(海外向けのネットショップモール)です。ハンドメイド作品だけでなく、デザイン性の高い雑貨やヴィンテージ品など幅広いカテゴリに対応しています。
出品には、著作権侵害や出品禁止の商品でないかなど、事前審査があります。この審査をクリアした商品のみが販売されているため、プラットフォーム自体の信頼性が高く、出品者も自身のブランド価値を損なうことなく販売できます。
また、日本語サポートが充実しているため、アジアを中心にブランド認知を広げたいクリエイターや、デザイン性の高い商品を展開している方もスムーズに出店手続きを進められます。
ネットオークション
ネットオークションは、一点もののハンドメイド作品や、希少性の高い作品を、競り形式で販売するのに向いています。
ヤフオク!

ヤフオク!は、Yahoo!が運営する国内最大級のネットオークションサービスです。ハンドメイド作品も多く出品されており、特に希少性の高い一点ものや、入手困難な作品であれば、競りによって高値で販売できる可能性があるのが魅力です。
販売手数料は原則10%で、プレミアム会員は8.8%です。必ずしも希望の価格で落札されるとは限らず、希少性のある商品でないと売れにくいのが懸念点です。
ネットショップ
ネットショップは、個人が手軽に独自のオンラインショップを開設できるサービスです。
販売手数料が比較的安いケースが多く、ブランドの世界観を自由に表現できるのが最大の魅力です。ショップのデザインや決済方法、独自のクーポン発行など、自由度が高く、リピーターを獲得するための戦略も立てやすいのが特徴です。
一方で、集客は自分で行う必要があるため、InstagramやTikTokなど、SNSでの積極的な発信が成功の鍵となります。
BASE
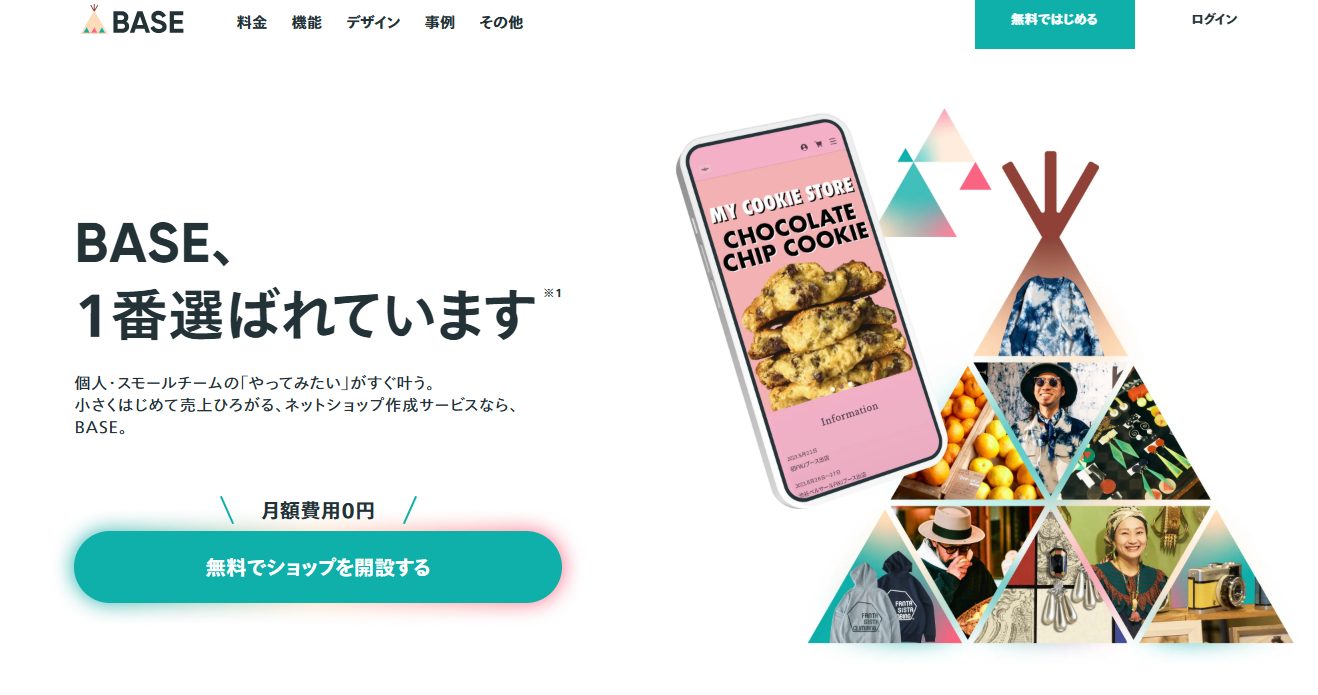
BASE(ベイス)は、国内におけるネットショップ開設実績8年連続1位(※)を誇るネットショップ作成サービスです。240万以上のショップ(※2025年6月時点)が作成されており、ハンドメイドを扱うショップも多数あります。
BASEのメリットは、コストを抑えて販売できることです。月額費用無料のスタンダードプランでは、商品が売れた場合にのみ、サービス利用料3%と決済手数料3.6%+40円が発生します。
直感的な操作でかんたんに独自のショップを開設できるほか、決済機能が豊富で審査による待ち時間がなく利用可能なので、すぐに販売開始できることも強みです。
また、各種SNSとの連携機能、豊富なデータ分析機能も備えており、不定期でBASE負担のクーポンを顧客に配布するなど、販売を促進するサポートも行っています。
※5年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービス調査(2025年2月調査委託先:マクロミル)
STORES

STORES(ストアーズ)は、ネットショップの開設から実店舗との連携まで幅広くサポートするサービスです。ショップデザイン機能の評価が高く、48種類以上のデザインテンプレートが利用でき、HTML編集にも対応しています。
料金体系は、無料プランと月額2,980円の有料プランから選択できます。販売手数料は無料プランで5%、有料プランで3.6%です。
直感的な操作でショップ開設ができ、予約販売、デジタルコンテンツ販売、定期販売など多様な販売形態に対応しています。また、実店舗向けPOSレジや在庫管理システムとの連携も可能なため、実店舗とオンラインをシームレスに運営したい人に適しています。
Shopify

Shopify(ショッピファイ)は、世界175か国以上で利用されているグローバルなネットショップ作成サービスです。高い拡張性と豊富なアプリ連携が強みで、マーケティング、在庫管理、SNS連携などをアプリで自由に拡張できます。デザイン面でも、テーマやコード編集による自由度の高いカスタマイズが可能です。
料金は月額約33米ドル(ベーシックプラン)〜で、決済手数料は3.4%+0円(国内カードの場合)です。多言語・多通貨に対応しているため海外販売に強く、POSレジ機能があるので実店舗との連携にも強みがあります。国内外での販売を戦略的に展開したい事業者に最適です。
カラーミーショップ

カラーミーショップは、GMOペパボ株式会社が運営する国内老舗のネットショップ作成サービスで、コストパフォーマンスの高さに定評があります。
カラーミーショップの特徴は、利益率が高い運営を目指せる料金形態です。月額料金は低価格(フリープラン〜プレミアムプランまで選択可能)で、スタンダードプラン以上で販売手数料が0円(決済手数料のみ)となっています。初期費用を抑えながら本格的なネットショップ運営が可能です。
デザインテンプレートの種類が豊富で、HTML・CSS編集にも対応しています。独自ドメインや常時SSL対応によりセキュリティ面でも安心で、モール連携やSNS連携機能も充実しています。
easymyshop

easymyshopは、在庫連動や複数店舗管理に強いネットショップ作成サービスで、販売業務の効率化を重視する事業者に人気です。販売手数料が無料(決済手数料のみ)で、コスト面で優位性を確保しやすいのが特徴です。リアルタイムでの在庫連動・受注管理が可能で、実店舗や他モールとの在庫一元管理に対応しています。
また、デザイン編集機能でブランドに合わせたサイト構築ができるほか、予約販売や定期販売など多様な販売形態にも対応しています。効率的な運営とコスト面を重視しつつ、オリジナル性の高いショップを構築したい方におすすめです。
Squareオンラインビジネス

Squareオンラインビジネスは、決済サービスで有名なSquareが提供するネットショップ作成機能です。SquareのPOSレジと連動することで、実店舗とオンラインの在庫・売上を一元管理できます。そのため、実店舗との連動がスムーズに行える点が強みです。
無料プランがあり、低コストでネットショップを開設できます。販売手数料は無料(決済手数料のみ)で、テンプレートから簡単にショップを作成でき、モバイルにも自動で最適化できます。デジタルの商品やサービスの販売にも対応しており、実店舗を持ちながらオンライン販売も展開したい小規模事業者や個人向けです。
フリマアプリ
フリマアプリは、中古品や既製品の売買がメインですが、ハンドメイド作品の出品も盛んです。
ユーザー数が非常に多く、幅広い層に作品を見てもらえるチャンスがあるのがメリットです。特に若い世代を中心に、気軽にネットショッピングをする場として広く利用されています。
ただし、中古品や既製品に混ざって表示されるため、作品が埋もれてしまいやすく、差別化が難しいというデメリットがあります。また、値下げ交渉される可能性もあり、適正な価格で販売しにくいのが懸念点です。
メルカリ
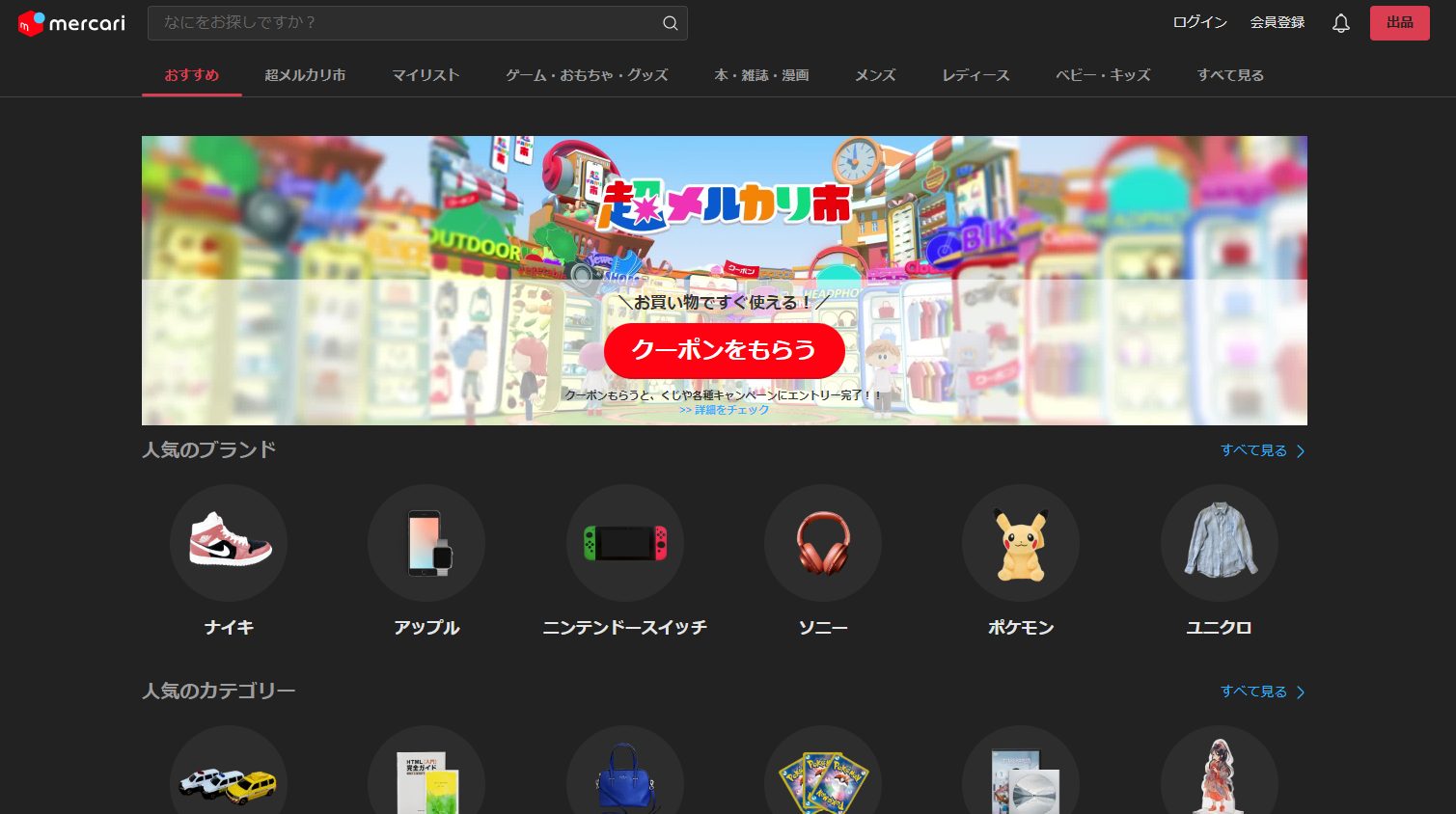
株式会社メルカリが運営するメルカリは、国内最大級のフリマアプリとして非常に幅広い年齢層の顧客に利用されています。中古品や新品など、さまざまな商品を販売できるプラットフォームで、累計出品数は2013年7月のサービス開始から40億品以上に達しています。(参照:株式会社メルカリ公式サイト/プレスリリース 2024年9月11日付)。ハンドメイド作品を含め、幅広いジャンルの商品を販売したい方におすすめです。
販売手数料は10%で、売上金を引き出すための振込手数料は一律200円です。
楽天ラクマ

楽天ラクマは、楽天グループが運営するフリマアプリです。楽天ポイントや楽天キャッシュなどと紐付けて活用できるため、楽天ユーザーには魅力です。
販売手数料は6%+消費税で、手数料率はメルカリよりも低く設定されています。売上金を受け取る際も、楽天銀行であれば1万円以上の振り込みで手数料が発生しないため、コストを抑えて販売したい方におすすめです。
ハンドメイドの販売でどのくらい稼げる?
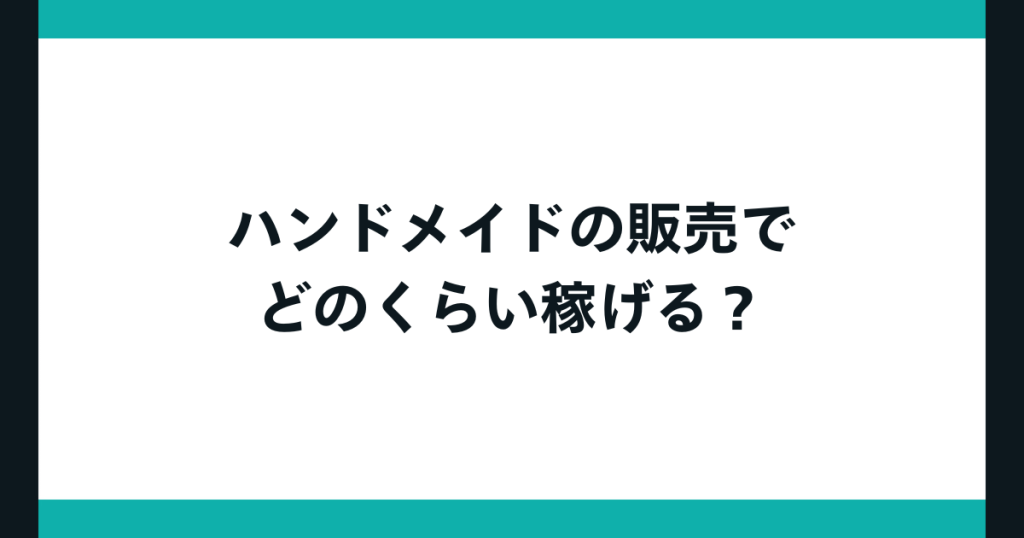
ハンドメイド販売によってどのくらいの収入が見込めるのかは、販売を検討する上で最も気になる点でしょう。
minneが2023年に実施した「ハンドメイド主婦・主夫作家の意識調査」によると、ハンドメイド販売によって毎月何らかの収入を得ている人は、回答者全体の約80%に上ります。これは、副業としてハンドメイド販売が広く定着していることを示しています。
しかし、主な収入源として期待するのは難しいのが現実です。調査結果によれば、1ヶ月に平均10万円以上の収入がある人は、回答者のうちわずか2.3%にとどまっています。この層の作家は、作品制作や発送作業などに週に20〜30時間ほど割いているケースが多いことも明らかになっています。
出典:「minnebyGMOペパボ」で副業として活動するハンドメイド作家の約80%が「収入を得ている」と回答~『ハンドメイド作家における副業調査』を実施~|GMOペパボ株式会社
ハンドメイド販売で稼ぐコツ

ハンドメイド販売で継続的に売上を伸ばし、安定した収入を得るためには、単に良い作品を作るだけでなく、戦略的な販売アプローチが欠かせません。ここでは、ハンドメイド販売で稼ぐための具体的なノウハウを紹介します。
ブランドコンセプトとターゲットを明確にする
ただ闇雲に「売れそうなもの」を作るのではなく、ブランドとしての方向性を明確にすることが大切です。コンセプトを考える際は、誰に向けて作品を作るのか、具体的にどのような価値を提供するのかを明確にしましょう。
特に重要なのが、作品を買ってほしいペルソナ(ターゲットとなる顧客像)を設定することです。どんな年齢・性別・趣味・ライフスタイルの人に買ってもらいたいか、という点を具体化してみましょう。
コンセプトやターゲットが明確であれば、作品のデザインや価格帯、販売ページの文章、写真の雰囲気、そして利用する販売サイトの選定まで、すべてが一貫したものになり、顧客にブランドの世界観が伝わりやすくなります。
リピーターを獲得しやすい販売方法を選ぶ
売上の8割は2割のリピーターに支えられていると言われるほど、リピーターの数や熱意は売上を左右する重要な要素です。
ハンドメイドマーケットやフリマアプリなどのプラットフォームを利用する場合、「あの作家の作品を買った」という認識よりも、「あのアプリ・サイトで買った」という認識になりやすい傾向があります。これは、プラットフォームのブランドが強く、作家個人のブランドが埋もれてしまうためです。
リピーターを増やし、ファン化を促すには、ショップデザインを自由にカスタマイズでき、顧客との接点も持ちやすいネットショップの開設がおすすめです。ショップの雰囲気を統一することで、作家個人のブランドの世界観が伝わりやすくなり、「この作家からまた買いたい」と思ってもらいやすくなります。
InstagramやTikTokなどのSNSを駆使して集客する
ネット販売では商品を実際に手に取れないため、動画や写真で商品の魅力を具体的に伝えることが非常に重要です。
特にInstagramのリール、TikTok、YouTubeなどの動画プラットフォームは、ハンドメイド作品と相性が良いメディアなので、積極的に活用しましょう。
実際に身に着けた様子や梱包方法などを投稿することで、商品の魅力が伝わります。また、作品の制作過程や裏話などのエピソードを発信すれば、作家の人柄や制作への想いを伝えられ、ファン獲得にもつながります。
InstagramやTikTok、YouTubeのSNSにはストア機能が備わっているため、販売ページに直接誘導することも可能です。ただし、ストア機能で販売ページにリンクできる販売サービスは一部に限定されているため、連携に対応しているか事前に確認が必要です。
材料以外のコストを極力抑える
ハンドメイドの販売価格を設定する際は、材料費だけでなく、サイトの手数料や送料、梱包材費なども考慮して検討する必要があります。
適正価格で販売しながら利益率を高めるためには、材料費以外のコストを極力削減することが重要です。販売手数料が比較的安いネットショップを選んだり、送料や梱包材の費用を工夫したりすることで、手元に残る利益を最大化できます。
特に初期費用や月額費用がかからない販売サイトを選べば、赤字のリスクを抑えながら販売活動をスタートできます。
BASEのハンドメイド販売事例
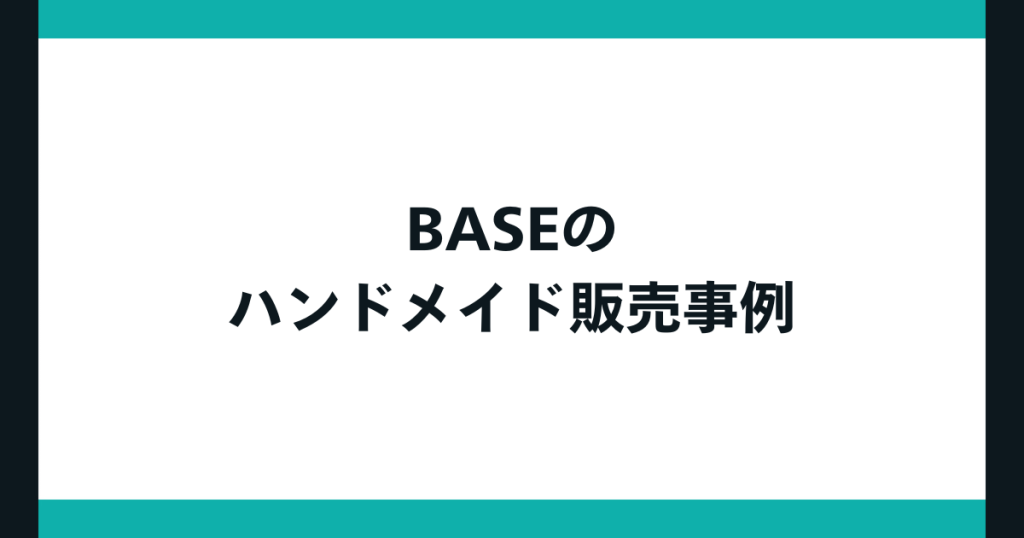
ネットショップ作成サービス「BASE」を利用してハンドメイドを販売している作家の例を紹介します。
まとめ販売スタイルで無理なく運営|Linola handmade jewelry
ピアスやネックレスなどのアクセサリーを販売する「Linola handmade jewelry」は、商品を一点ずつ丁寧に制作し、一定数の在庫を確保できたタイミングでまとめて販売するスタイルを取っています。このため、販売期間外は在庫がない状態が続くことになります。
オーナーは、在庫が確保できた時期にだけ販売するスタイルで運用するために、在庫がない期間にコストがかからない販売方法を探しました。その結果、初期費用や月額費用がかからないBASEを選び、コスト面でのリスクを抑えながら、自分のペースでブランド運営を続けています。
在庫が不安定になりがちなハンドメイド作家にとって、BASEは、柔軟でコスト効率の高い運営を実現するために適したネットショップです。


会社員の経験を活かして1人で起業|TRIP UTOPIA
手芸材料として人気のインド刺繍リボンを扱う「TRIP UTOPIA」のオーナーは、大学生の頃からWebサイトを使ってハンドメイド作品を販売していました。会社員時代に色鮮やかなインド刺繍リボンの商品写真がSNSで拡散されたことをきっかけに、売上が急上昇。いまでは会社を辞めて、ハンドメイド販売を本格的なビジネスとして取り組んでいます。
オーナーは当初フリマアプリを使っていましたが、「もっとお店っぽくしたい」という思いからBASEでネットショップを開設。その結果、Google検索で上位に表示されるようになりました。
ハンドメイド販売のよくある質問
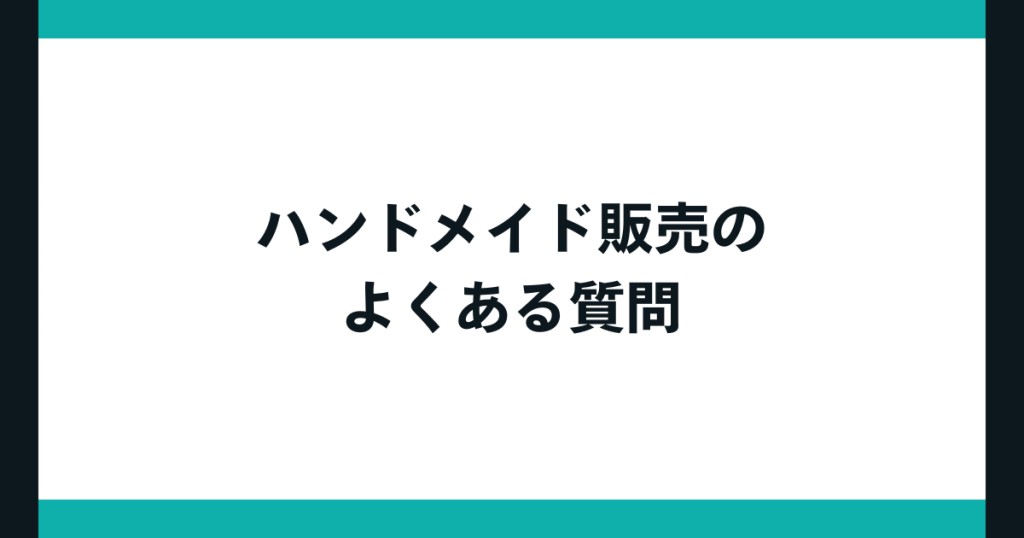
ハンドメイドの販売に関する疑問・質問をまとめました。
売ってはいけないハンドメイドは?
著作権や知的財産権に違反するものは販売できません。具体的には、有名キャラクターやブランドのロゴを無断で使用した作品、既存の作品をコピーした作品などです。
また、古物商許可を取得していないアンティーク品や、食品衛生責任者の資格・営業許可なく自宅で作った食品なども販売することはできません。これらは適切な許可や資格を取得すれば販売可能になります。
ハンドメイド作品が一番売れるサイトは?
ユーザー数と出品数の多さ、そしてハンドメイド作品を探している顧客層が集まっているという点から、国内ではminneとCreemaが有力です。どちらも国内最大級のマーケットであり、まずはこの2つのいずれか、または両方から販売を始めるのがおすすめです。
一方で、数多くの人気作家も利用しているサイトのため、作品が埋もれてしまう可能性が高いのが懸念点です。独自のブランドコンセプトや魅力的な商品写真によって差別化し、Instagramを活用して集客を行うなど、取り組み次第で売れるかどうかが変わってきます。
ハンドメイド作品を売るなら何がいいですか?
初期費用を抑えつつ、手軽に全国に作品を届けられるネット販売がおすすめです。特に、コスト面・手間を抑えることを最優先するなら、minneやCreemaなどのハンドメイドマーケット、またはBASEやSTORESなどの無料プランがあるネットショップを利用するのが良いでしょう。
まとめ
ハンドメイドの販売方法は、ネット販売、イベント販売、委託販売、実店舗販売の4種類です。なかでも、初期費用を抑えつつ、全国に作品を届けられるネット販売は、手軽に売上を伸ばしやすい販売方法と言えるでしょう。
ネット販売には、ハンドメイドマーケットやフリマアプリ、ネットショップなど様々な選択肢があります。サービスごとにユーザー層や機能が異なるため、作品やブランドコンセプトに合ったプラットフォームを選ぶことが大切です。
また、ハンドメイド販売で安定した収入を得るには、単に作品を売るだけでなく、ブランドコンセプトの明確化やリピーターの獲得、SNSを活用した集客など、戦略的なアプローチが欠かせません。
BASEをはじめ、初期費用や月額費用がかからないネットショップを選べば、コストを抑えながら、あなたのブランドの世界観を最大限に表現できます。ぜひ、この記事を参考に、あなたのハンドメイド活動を成功に導いてください。
テンプレートから選べる
BASEなら操作もかんたん

専門知識がなくても、驚くほどスムーズに、自分の世界観を表現することができます。デザインの難しさに悩むことなく、理想のネットショップを今すぐ形に。月額費用0円ではじめよう。