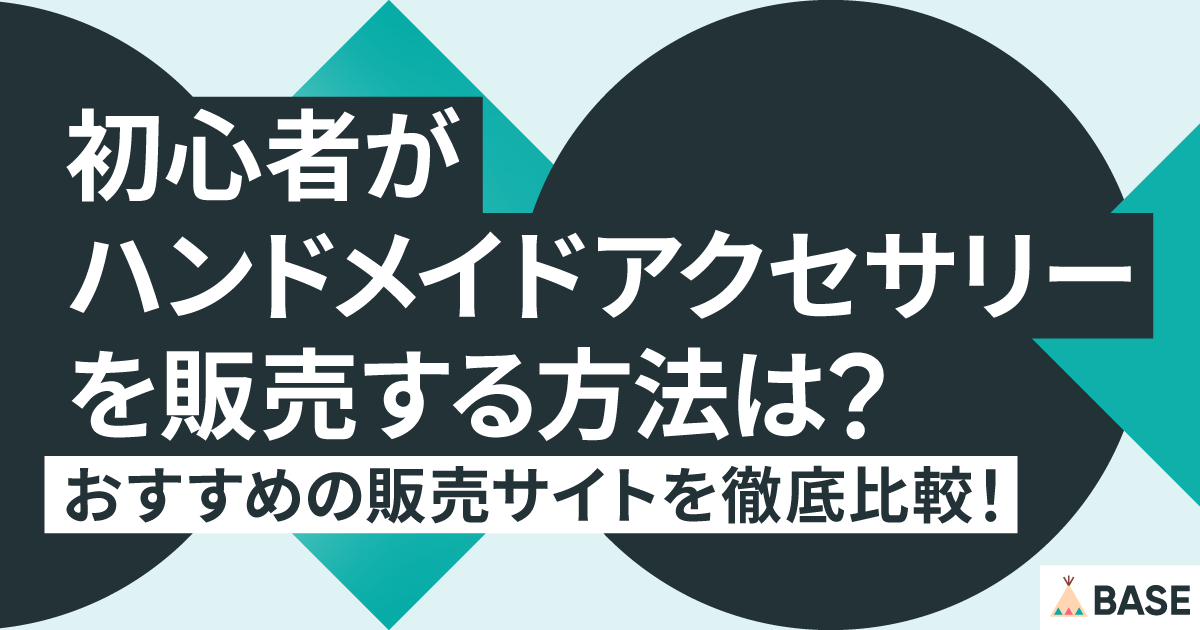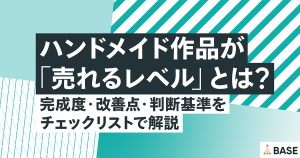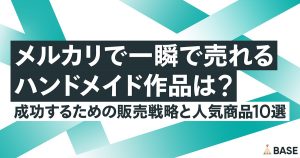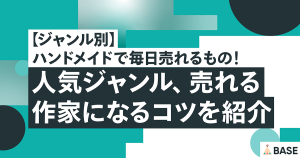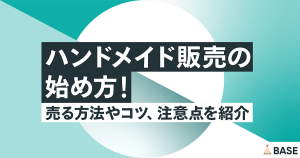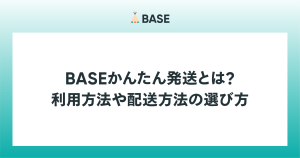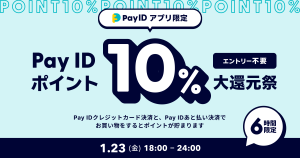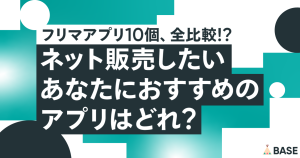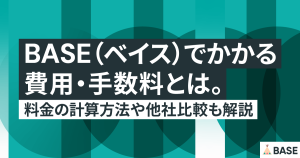アクセサリー作りが得意な人やハンドメイド作家として活動している方の中には、「商品を販売してみたい!」という方もいらっしゃるかと思います。
しかし、いざやろうと思うと「どのサービスを使うのが最適なのかな?」と迷ってしまうのではないでしょうか。
それもそのはず、ハンドメイドアクセサリーを販売する場所はたくさんあり、ざっと調べただけでも10以上あります。
そこで、この記事では、ハンドメイドアクセサリーを販売できるサービスの特徴をまとめてみました。販売にさいして知っておきたい基礎知識も解説しているので、参考にしてください。
【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ
- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです
- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます
- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています
- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています
ハンドメイドアクセサリーを販売する方法は、大きく3つ
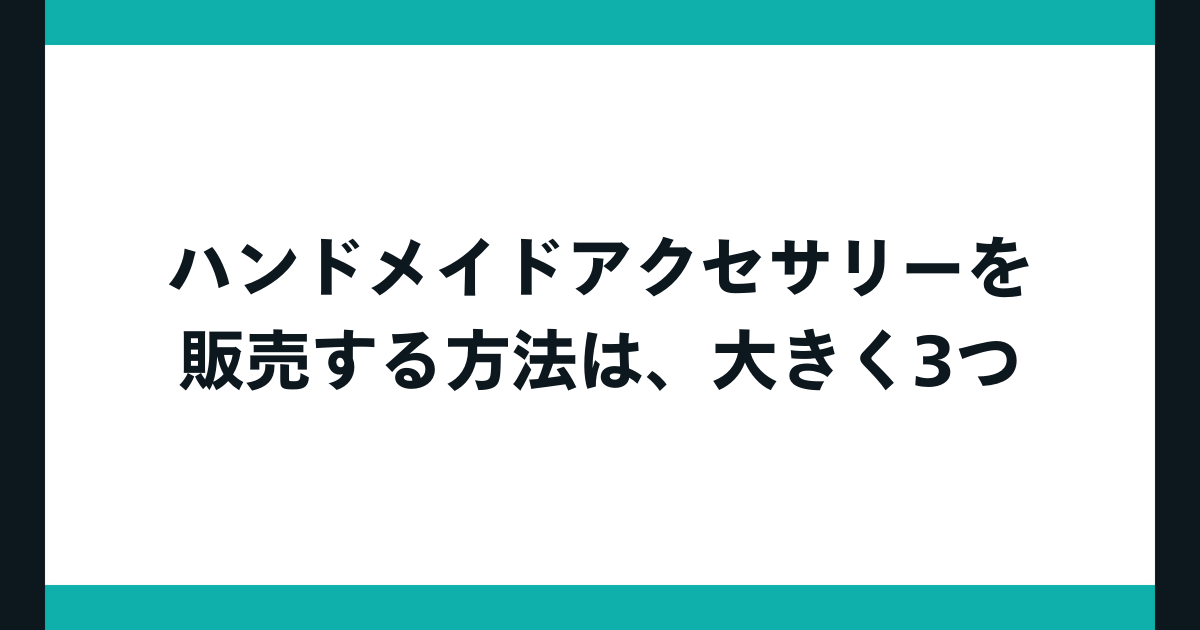
ハンドメイドアクセサリーを販売する方法は、大きく3つあります。
- 方法1. ハンドメイド販売サイト(マーケットプレイス)
- 方法2. フリマアプリ・オークションアプリを利用する
- 方法3. ネットショップを作成する
それぞれの方法ごとに、特徴や得意なこと、苦手なことがあるので、自分に合った販売方法を見つけることが、成功への第一歩となります。
方法1. ハンドメイド販売サイト(マーケットプレイス)
作成したハンドメイドアクセサリーを販売する方法の一つとして、ハンドメイド販売サイトを利用する方法があります。
代表的な販売サイトとしてminneやCreemaなどがあり、聞いたことがある方も多いでしょう。
これらのサイトは、ハンドメイドアクセサリーの販売に特化しているため、訪れる顧客もはじめからハンドメイド商品の購入を検討していることがほとんどです。
そのため、出品する商品がサイトに訪問する顧客のニーズに合いやすく、購入につながる可能性が高いのが特徴です。
デメリットとしては、サイトのデザインなどに凝りにくいため、個性を出してブランディングに力を入れたい人には向いていない場合があります。
海外への販売も視野に入れたい場合は、EtsyやPinkoiなどの販売サイトもおすすめです。
|
メリット |
デメリット |
|
・ハンドメイド商品を探している顧客が集まるため、購入につながりやすい ・初期費用や固定費用が必要ない ・サイト作りの手間が省ける ・サイトによっては海外への販売も可能 |
・サイトのデザインなどで差別化できない ・ブランディングがしにくい ・すぐに競合と比較される ・手数料が高め |
方法2. フリマアプリ・オークションアプリを利用する
メルカリなどのフリマアプリや、ヤフオク!などのオークションアプリでも、ハンドメイド商品の販売がさかんに行われています。
メルカリなどのフリマアプリは、利用者が非常に多く、商品登録などの操作もかんたんに行えるでしょう。
支払方法も、分割払いなどをふくめて豊富に用意されているため、商品の回転が非常に早い、という特徴があります。
ただし、あくまでフリマアプリという位置づけなので、顧客は値段重視で商品を選ぶことが多いです。そのため、価格交渉をされることも覚悟しておく必要があります。
こういった特徴があるため、フリマアプリでの販売は、「まずはためしに商品を販売して、顧客の反応を見てみたい!」という人におすすめの方法です。
オークションアプリは、フリマアプリよりもバラエティに富んだ品物が出品されています。
フリマアプリが若年層や女性に人気が高いのに対し、オークションアプリでは年代や性別に関係なく幅広い顧客に見てもらえる可能性が高くなります。
また、価格は売り手ではなく買い手が決め、最終的な落札価格によって取引されるのがオークションの特徴ですが、ハンドメイドとの相性はあまりよくないので、フリマアプリの方が使いやすいでしょう。
|
メリット |
デメリット |
|
・ハンドメイド商品を探している顧客以外にも 幅広くリーチできる ・利用者が圧倒的に多い ・出品者にも購入者にも使いやすいシステム |
・価格交渉される可能性もある ・値段重視での比較になることが多い ・手数料が高め |
方法3. ネットショップを作成する
ネットショップ作成サービスを利用して、自分のショップを作成する方法も人気です。
ネットショップ作成サービスを利用すれば、誰でもかんたんに自分だけのショップを開設できます。
自分だけのショップを持つことの利点は、競合と比較されにくいことです。その上、「◯◯というショップで購入した」と購入者に認識してもらえることで、リピーターにつながりやすいことが挙げられます。
代表的なサービスに、BASEやSTORESなどがあります。
|
メリット |
デメリット |
|
・自分だけのショップが作れる ・ブランディングしやすい ・SNSからの送客がしやすい ・手数料が低め |
・SNSなどを使って集客に工夫が必要 |
ハンドメイドアクセサリーの販売・出品ができるサイト・ツール比較
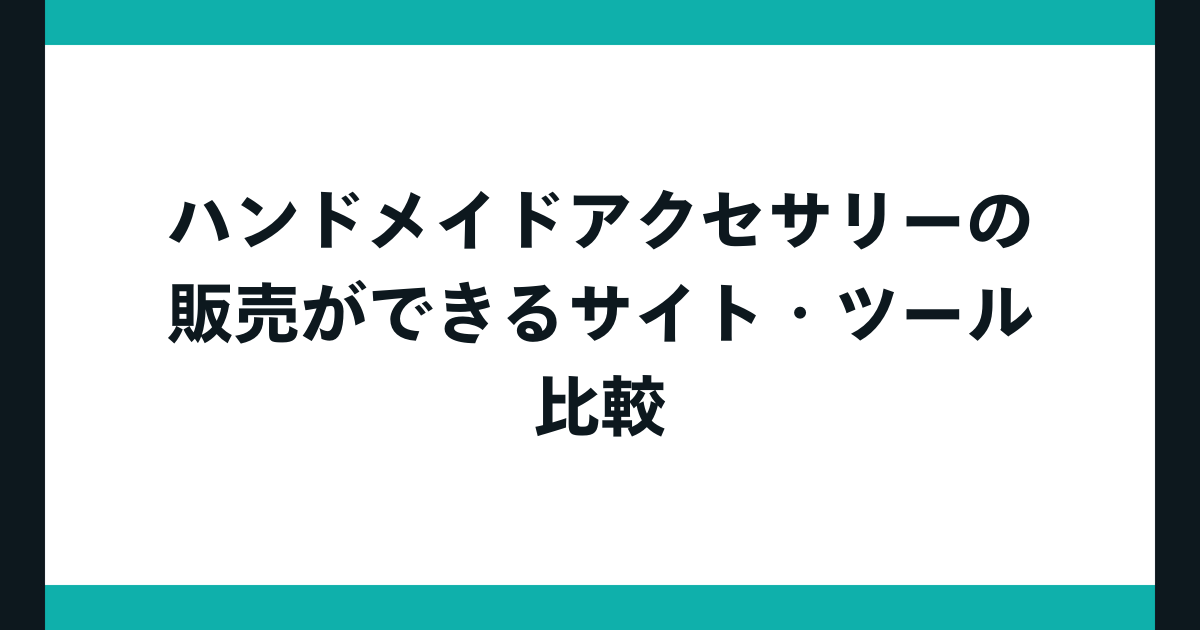
ここまでは、ハンドメイドアクセサリーの販売ができる方法について紹介してきました。
ここからは、実際にサービスを一覧でまとめて比較しながら紹介します。それぞれのサービスの特徴について把握し、自分にぴったりのサービスを探してみてください。
|
初期費用 |
固定費 |
手数料 |
アプリ販売 |
|
|
無料 |
無料 |
6.6%+40円 |
可 |
|
|
minne |
無料 |
無料 |
10.56% |
可 |
|
creema |
無料 |
無料 |
11% (作品、素材の販売) |
可 |
|
Etsy |
無料 |
無料 ※有料プラン有 |
出品料: $0.20 米ドル/商品 1 個(28.52円相当 2024年9月時点) 取引手数料: 合計価格の6.5% |
可 |
|
Pinkoi |
無料 |
無料 |
15% + 15台湾$ |
可 |
|
iichi(いいち) |
無料 |
無料 |
商品代金(送料除く)の20% |
不可 |
|
メルカリ |
無料 |
無料 |
10% (コンビニ・ATM・キャリア決済は決済手数料+100円) |
可 |
|
ラクマ |
無料 |
無料 |
6.6% |
可 |
|
ヤフオク! |
無料 |
無料 |
10% |
可 |
|
STORES |
無料 |
無料 |
5.5% |
不可 |
ご覧いただくとわかるとおり、フリマサイトやハンドメイドマーケットプレイスのサービスは、手数料が高い傾向にあります。
また、ほとんどのサービスでアプリがありますが、一部アプリのないサービスもありますのでご注意ください。
それぞれのサービスの詳細は、このあとの解説をご確認ください。
BASE

BASEは、ネットショップ開設実績7年連続No.1(※)のネットショップ作成サービスで、誰でも無料でネットショップの作成が可能です。
|
ポイント
|
※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)
ハンドメイド作家の集まるプラットフォームやフリマサイトなどではなく、自分だけのネットショップでブランドを展開できます。
集客支援機能が充実しており、Instagramからもかんたんに集客することが可能ですし、累計ID登録者数 1,400万のショッピングアプリ「Pay ID」があるのも魅力の一つです。
その他にも、BASEではポップアップショップの出店などもサポートしており、ハンドメイド販売には最適なネットショップ作成サービスです。
ハンドメイドアクセサリーの販売は、副業としてはじめたり、主婦の方がすき間時間ではじめたりするケースが多くなっています。BASEは商品が売れるまで費用が一切かからないほか、ショップオーナーが住所や電話番号を開示する必要がないなど、運営の安全性にも配慮しています。PCを持っていなくても、スマホでかんたんにオリジナルデザインのショップがオープンできるのも、BASEがハンドメイド作家さんに選ばれる理由の一つです。
- 月額費用:0円(グロースプラン:16,580円/月)
- 販売手数料:サービス利用料3%+決済手数料3.6%+40円(グロースプラン:2.9%)
- 売上振込手数料:【振込手数料】一律250円+【事務手数料】2万円以上の場合:0円(2万円未満の場合:500円)
minne(ミンネ)

小物やアクセサリーなどのハンドメイドが多く出品されている、国内最大級のハンドメイドマーケットプレイスです。
|
ポイント
|
20~30代の女性ユーザーが多く、ハンドメイドならではの魅力を求めて訪れることが多い傾向にあります。
また、顧客からのレビュー率が多く、感想やフィードバックを受け取れる可能性が高いことも魅力です。イベントや勉強会なども開催されるため、作家としてスキルアップを目指せます。
さらに、minnneではハンドメイドの販売や制作を促進するサービスが充実しているのも特徴です。ハンドメイド作家としてスキルアップするためのノウハウが公開されていたり、minnneのオウンドメディアやSNSで商品を紹介してもらえたりなどのサービスが受けられます。
- 月額費用:0円
- 販売手数料:10.56%(税込)
- 振込手数料:220円
Creema(クリーマ)

あらゆるジャンルのクリエイターと顧客が集うCreemaには、魅力的なハンドメイドアクセサリーが多く出品されています。
|
ポイント
|
中国版サイトも展開しているため、中国市場に参入することも可能です。
19万人のクリエイターによる、1,000万点のオリジナル商品が並びます。日本最大級のハンドメイドマーケットプレイスとして、ユーザーが増え続けています。ハンドメイドを好きな顧客が多く、商品を吟味して購入してくれる可能性があります。
Creemaは商品の単価が高い傾向があるので、家具など単価が高いハンドメイドも出品しやすいことも特徴です。また、クーポン機能やキャンペーン機能を使って、集客に役立てることもできます。
- 月額費用:0円
- 販売手数料:11%(税込)
- 売上振込手数料:合計金額が30,000円未満の場合176円/合計金額が30,000円以上の場合275円
Etsy(エッツィー)
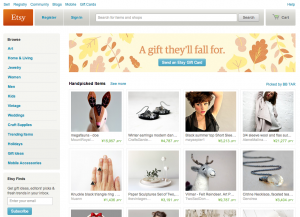
Etsyは、ハンドメイドアクセサリーが世界中のアーティストから出品されている、モール型のネットショップです。
|
ポイント
|
2005年の創設以降、世界中で多くのユーザーを獲得しています。海外のユーザーが多いため、日本向けのサービスと比べて、圧倒的に閲覧者が多いのが特徴です。日本語でショップの登録を行うこともできます。
ほかのサイトよりもおしゃれでコミュニティらしい雰囲気が強く、ハンドメイド好きのユーザーが好んで利用しています。
また、外部サイト広告手数料(15%)を支払えば、Etsyに商品の宣伝を委託することもできるので、効率的に広告運用を行いたい方におすすめです。
- 月額費用:0円
- 販売手数料:6.5%+PayPal入金手数料+27円の出品料
- 売上振込手数料:0円
Pinkoi(ピンコイ)

Pinkoiは、アジア最大級のデザイナーズマーケットで、アジアを中心に、世界中のデザイナーと顧客をつなぐ架け橋となっています。
|
ポイント
|
会員数は全世界で約400万人を超え、日本だけでなく、海外に向けてもアピールできるのが特徴です。「デザイン市場のエコシステムを広げて、グローバル規模で理想的なライフスタイルを提案したい」というコンセプトの上に成り立つサービスです。
メインの顧客層は20~40代で、比較的若めのターゲットに向けた商品に向いています。アクセサリーだけでなく、アパレル商品やインテリア、ペット用品など、幅広いジャンルのハンドメイドを販売しています。
- 月額費用:0円
- 販売手数料:(商品価格 + 送料)× 15% + ¥58※
- ¥58 → 15台湾ドルを日本円に概算
- 売上振込手数料:5台湾ドル(約180円)
iichi(いいち)

個人や小規模な作り手のものづくりを大切にするハンドメイドマーケットです。
|
ポイント
|
プロの作家が制作したハイクオリティの商品が出品されているので、比較的単価が高い傾向にあります。商品を出品する作家の中には職人も多いので、男女問わず幅広い年齢層の作家が利用しています。
また、メインターゲットの年齢層もほかのハンドメイドマーケットよりも高いため、1点ものの高価な商品などを販売したい方におすすめです。
- 月額費用:0円
- 販売手数料:商品代金(※送料除く)の20%(税込)
- 売上振込手数料:一律160円
メルカリ
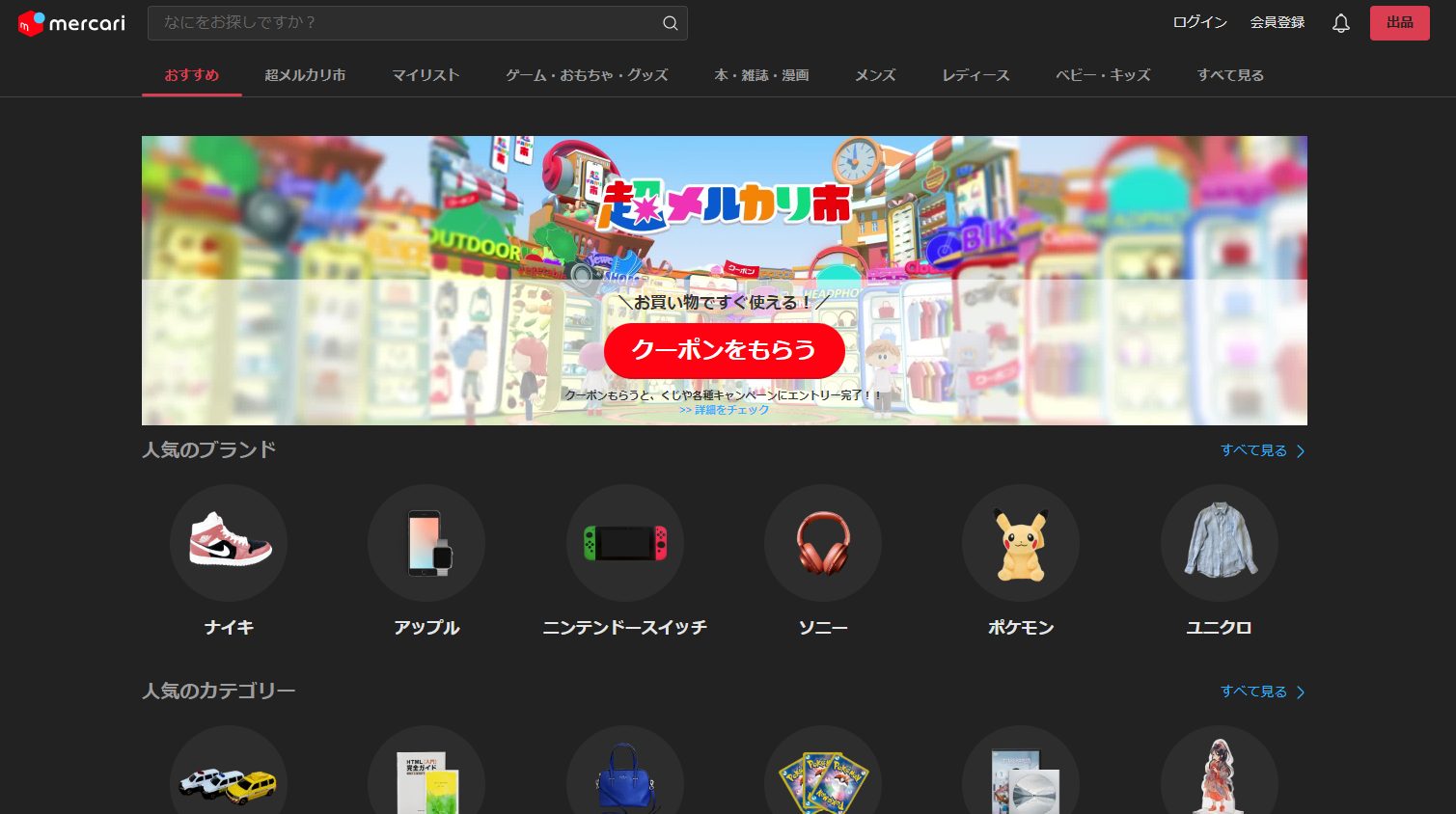
2013年にサービスをスタートしたメルカリは、口コミなどから広がり、現在では国内最大級のフリマアプリとなり、多くの人に利用されています。
|
ポイント
|
若年層に人気のフリマアプリですが、徐々に60代以上の利用者も増加傾向にあります。
魅力的な写真を掲載することで、ほかのセカンドハンド商品との差別化が可能です。
メッセージ欄でお客さんとのやり取りが公開されるので、閲覧者の購買意欲がかきたてられる可能性があります。
さらに、ヤマト運輸や日本郵便と連携した豊富な配送方法が用意されているため、誰でもどこからでも発送しやすいこともメリットです。
- 月額費用:0円
- 販売手数料:10%(コンビニ・ATM・キャリア決済は決済手数料+100円)
- 売上振込手数料:一律200円
ラクマ

ラクマは、楽天株式会社が運営しているフリマアプリです。楽天株式会社の会員数が多いことや、CMなどの宣伝活動などによって、利用者数が伸びています。
|
ポイント
|
すでに楽天会員になっている場合は、出品登録がよりスムーズにできます。
ハンドメイド専門ではないので、顧客がかならずしもハンドメイド商品を探しているとは限りません。興味を持ってもらった場合は、初心者のハンドメイドアクセサリーでも気軽に購入してもらえる可能性があります。
ラクマは楽天のサービスなので、楽天ポイントを貯めている方や、楽天Payといった楽天のサービスを日常的に利用している人にとって、メリットが多いでしょう。
- 月額費用:0円
- 販売手数料:6.6%(ペイディ・コンビニ・ATM・d払い・キャリア決済は決済手数料+100~200円)
- 売上振込手数料:210円
ヤフオク!

ヤフオク!は、幅広い顧客層に人気のオークションサイトで、出品のしやすさが魅力です。
|
ポイント
|
こちらもフリマアプリと同様にユーザー数が多いため、多くの人に見てもらえる可能性があります。
バラエティに富む商品が並んでいますが、ハンドメイド専門に特化したサイトではないので、逆に自分の商品に希少価値が生まれやすくなります。
とはいえ「ハンドメイドアクセサリーを探しに来ている」というユーザーは少ないので、注意が必要です。
Yahoo!プレミアム会員なら落札システム手数料を抑えて出品できるというメリットがあります。
- 月額費用:0円
- 販売手数料:落札システム手数料 10%(プレミアム会員は落札価格の8.8%)
- 売上振込手数料:100円
STORES

STORESも、誰でも自分のネットショップを作成できるサービスです。ただし、有料プランもあり、無料の「フリープラン」では機能が大幅に制限されるため注意してください。
|
ポイント
|
STORESの特徴は、ファッションコーディネイトアプリWEARと連携できることです。
その他、決済サービスも提供しているため、実店舗を持っている方などにとっては、有力な選択肢となるかもしれません。
ネットショップとしてだけではなく、実店舗の予約受付やテイクアウトといったプラットフォームとして活用することもできるので、実店舗と並行してネットショップを運営したい方におすすめです。
- 月額費用:フリープラン0円
- 販売手数料:フリープラン5.5%
- 売上振込手数料:0円(自動入金または売上合計10万円以上の場合)
※売上合計10万円未満の場合、振込手数料200円(うち消費税10% 18円)
将来を見据えてハンドメイドアクセサリーを販売するなら、「BASE」がおすすめ
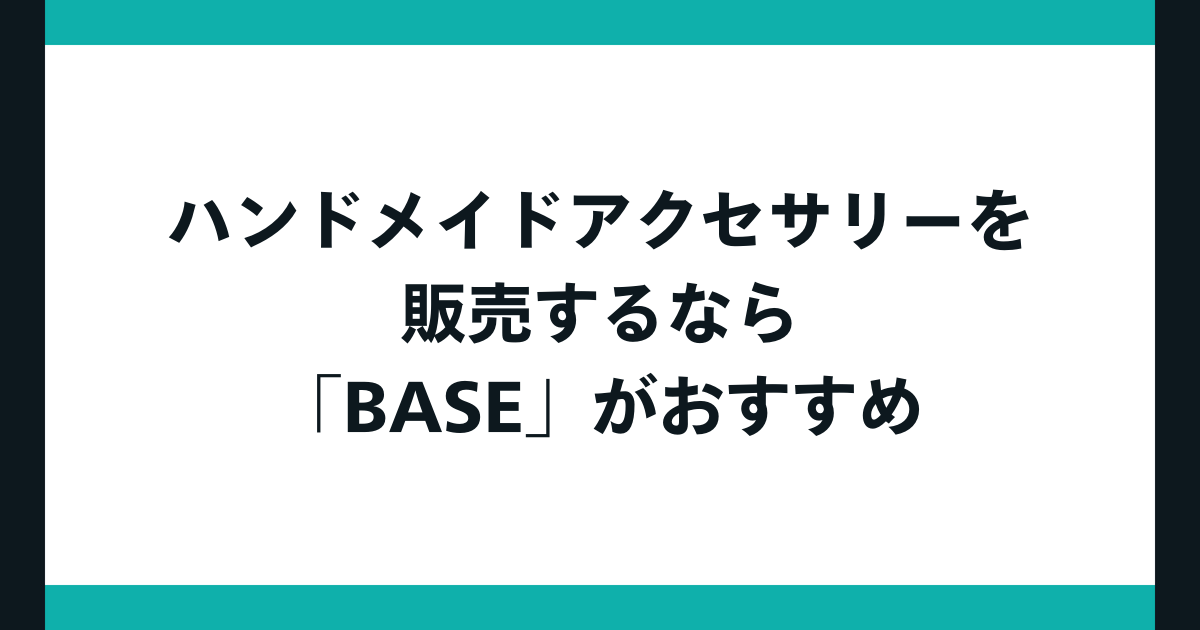
将来的にショップを構えてみたいと思っている人や、ブランドとして確立していきたいと考えている人におすすめなのは、BASEです。
BASEなら、ハンドメイドマーケットプレイスやフリマアプリなどと異なり、ブランドとして認知されるというメリットがあります。
たとえば、メルカリで商品が売れたとしても、顧客になかなかブランド名やショップ名を覚えてもらえないですよね?
それに対して、BASEのようなネットショップでは「◯◯というショップで買った」というように、ショップ名まで記憶に残りやすく、ファンやリピーターがつく可能性が高くなります。
最終的には、それがブランドとして周知されていき、顧客がどんどん増えていくでしょう。
さらに、BASEではラフォーレ原宿などをはじめ、全国の商業施設へのポップアップショップの出店をサポートしており、最低3日間から出店可能です。なお、ポップアップショップの出店料は無料です。
商業施設やスペースで商品を販売することで、商品を実際に見てもらう機会が増えたり、お客さんとつながりを深めたりできるでしょう。
1人で準備するのは大変ですが、BASEなら出店前後のやり取りなどもサポートしてもらえる点が魅力です。
また、BASEではInstagramの連携機能もあり、Instagramから直接お客さんをショップに誘導できます。
BASEのさまざまな販売促進機能を活用していけば、しっかりと売上を伸ばしていけるでしょう。
先輩ショップオーナー推薦!ハンドメイド集客に役立つ「BASE」の拡張機能
フリマアプリなどではなく、ネットショップを運営するには、自分でショップに必要な機能などをカスタマイズしていく必要があります。
BASEには50を超える拡張機能(Appsと呼びます)があるため、どういった機能を使えばいいのか、迷ってしまうかもしれません。
そこで、BASEで実際に商品を販売しているショップオーナーが推薦する拡張機能を、こちらの記事をもとに紹介しますので、参考にしてください。
「ラベル App」
新商品や注目商品、セール中の商品など、力を入れて売りたい商品がある場合に便利なのが「ラベル App」です。
商品の特性や伝えたいメッセージに応じたラベルをつけることで、商品一覧にメリハリがつき、お客さんにとって見やすくなります。
ラベルのパターンが多いだけでなく、オリジナルの画像をアップロードして、ラベルとして使うことも可能です。「ラベル App」を活用することで、おすすめ商品の訴求力を最大限に引き出せるでしょう。
螺鈿アートのハンドメイド作家である上本ミナさんは、「ラベル App」に加えて「カテゴリ管理 App」で、ラベルと同様のカテゴリを作成しています。
ラベルとカテゴリを統一することで、より際立たせたい商品に目がいきやすい工夫がなされています。
「送料詳細設定 App」
「送料詳細設定 App」は、配送手段を地域や商品によって設定できる拡張機能です。
配送料を、細かい条件に基づいて設定できます。たとえば、一定の購入額を超えた場合に、送料を無料に設定することもできます。
送料を無料にしたい、と考えているお客さんが購入に至った場合に、購入単価がアップする「アップセル」の効果を期待できるでしょう。
「メッセージ App」
メールを使わずに、チャットによって顧客とコミュニケーションを図れる機能です。
リアルタイムに近いコミュニケーションを行えるので、円滑なやりとりが実現し、お客さんの興味が薄れないうちに購入につなげられます。
管理画面で完結したカスタマーサポートが可能になるので、メディアやSNSなどからアクセスしてくれた顧客にも、迅速なレスポンスができます。
「Instagram販売App」
「Instagram販売App」はInstagramの投稿に商品をタグづけして、BASEの商品販売ページへ直接リンクできる機能です。
Instagramで商品を販売することで、Instagramユーザーに向けてショップをアピールし、新たな顧客の獲得に役立ちます。
「YouTubeショッピング連携」
「YouTubeショッピング連携」はBASEで開設したネットショップ上の商品と「YouTube ショッピング」を連携することで、YouTubeのチャンネルや動画上に商品のタグ付けなどができる機能です。
新たな顧客を獲得し、ショップの売上をさらに伸ばせる可能性があります。
その他にも、「BASE」にはさまざまな拡張機能がありますので、ぜひ一度ご覧ください。
「BASE」でハンドメイドアクセサリーを販売するショップの事例
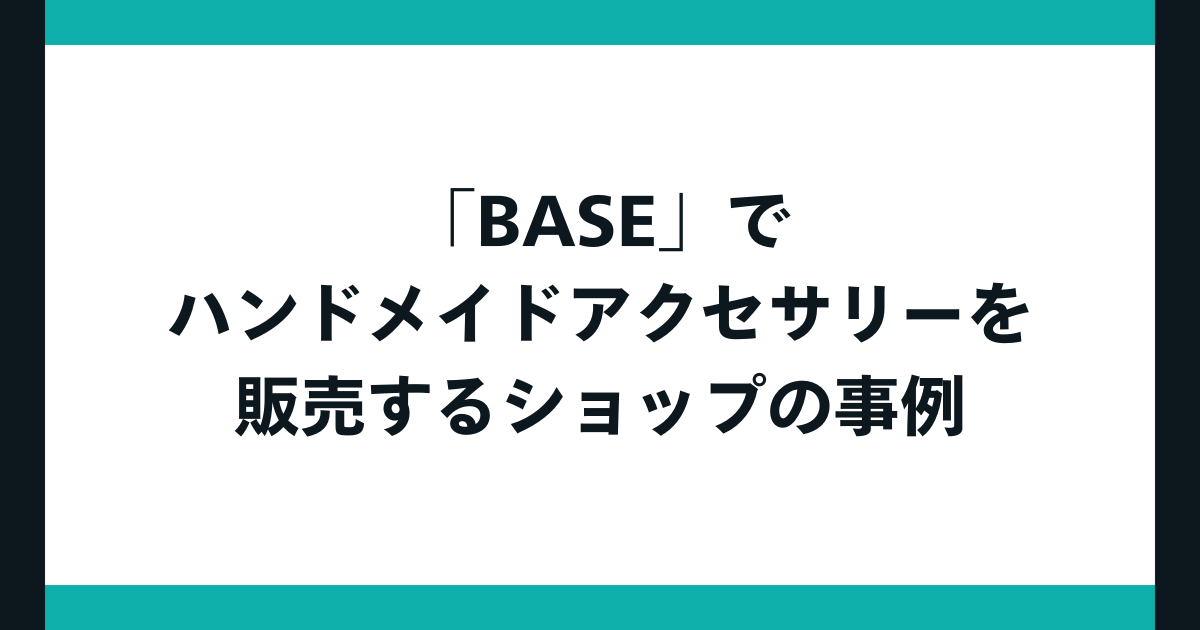
実際にBASEを利用して、自分だけのネットショップを運営している方はたくさんいらっしゃいます。その中から、いくつか事例を紹介します。
アクセサリーブランド|Linola handmade jewelry
<linola> は、ハワイ語の造語で「きらきら輝く太陽」という意味です。太陽が顧客で、制作者の穂園さんは太陽のもとで咲くひまわりというイメージでショップ名を決めたのだそうです。
もともと妹さんがハンドメイドアクセサリーを作っていたことに影響を受け、穂園さんもアクセサリー制作を開始しました。販売を決意したものの、販売日時が一定ではないので、月額でコストがかかると大きなリスクになってしまうのが懸念点でした。
そこで、初期費用が一切かからず販売手数料のみで販売できるBASEを選んだのだとか。BASEのポップアップ出店サポートを利用してポップアップ出店後、ネットショップでの売上は増加したそうです。
【ネットからリアルへ vol.5】ハンドメイドだからこそファンとの交流が大切。アクセサリーブランド<Linola handmade jewelry>が語る、リアル販売の魅力とは
レディースアクセサリーブランド|Quatorze
レディースアクセサリーブランド<Quatorze>では、ブライダル向けやオケージョナル向けのアクセサリーとデイリー向けのアクセサリーを販売しています。
最初はセレクトショップさんなどに卸していたそうですが、「フルラインナップを見たい」という声があり、認知度の高いネットショップ開設サービスであるBASEを選んだのだそうです。買える場所が明確になったおかげで、売上アップに成功しました。
BASEは自由度が高くて、小さい規模で回していけるネットショップなので、これからは買っていただけるお客さんの満足度を上げたいと考えているそうです。
オリジナルハンドメイド・セレクトアクセサリーブランド|FUIUCHI
女の子の“不意”のかわいいをお手伝いしたい、<FUIUCHI(不意打ち)>は、オリジナルハンドメイド・セレクトアクセサリーを販売するブランドです。
オーナーの柏木さんは、もともとInstagamに歌った動画を載せたり、WEARなどのSNSにコーディネートの写真を載せたりなど、自分を表現することが好きだったのだそう。その後思い切って会社を辞め、ブランド一本で生きていくことに。
Instagramがきっかけでフォロワーが大きく増えたこともありますが、BASEの豊富な機能やサポートが販売に役立ったといいます。なかでも、ポップアップ出店サポートはBASEならではの魅力的なサービスには特別な魅力を感じており、ポップアップショップの出店をきっかけに法人化する決意が固まったそうです。
ハンドメイドアクセサリーを販売する手順
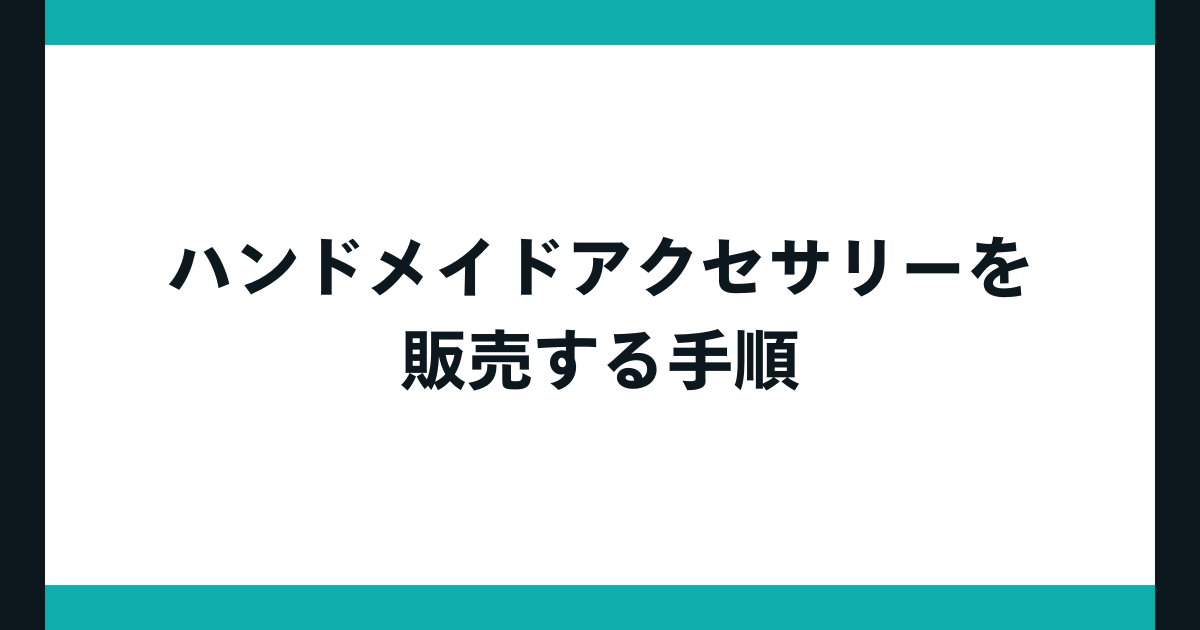
ハンドメイドアクセサリーの販売は、制作して売るだけではありません。たくさんの方に購入してもらい、リピーターを増やすためには、制作だけでなく販売の計画も綿密に立てていきましょう。ハンドメイドアクセサリーを販売する具体的な手順は、次の6ステップです。
商品の制作
まずはハンドメイドアクセサリーを制作します。
ハンドメイドアクセサリーはオンリーワンの商品を購入できるところが魅力の一つですが、ハンドメイドも既製品と同様に安全性を求められます。デザインや見た目の美しさだけにとらわれず、実際に使用してみて安全性や耐久性を確かめてから販売するとトラブルが起きにくいでしょう。
とくに華奢なパーツを使ったアクセサリーは金具の強度が弱かったり、レジンパーツは制作方法にミスがあると耐久性が低くなってしまったりすることがあります。繊細なアクセサリーを販売するときは、使用の注意事項など必要な注意点をしっかり記載して販売しましょう。
商品の販売方法を決定
販売する商品が決定したら、どこで販売するのかを決定します。
オフラインで販売する場合は、実店舗を立ち上げる方法のほかに、カフェや雑貨店に商品を置かせてもらう委託販売という方法もあります。
オンラインの場合は、写真や動画をメインで投稿できるInstagramで販売する人も多いです。また、minneやCreemaなどのハンドメイドサイト・アプリは、ハンドメイドの販売に特化しているため、ハンドメイドアクセサリーを求めている人を集客しやすいというメリットがあります。
独自のデザインでサイトを運営したい場合は、BASEなどのネットショップ作成サービスを活用するのがおすすめです。BASEは初期費用や月額費用無料で独自のネットショップが開設できるほか、手数料は商品が売れたときにしか発生しないので、自分のペースでハンドメイドアクセサリーを販売できます。
商品の撮影と登録
販売方法が決まったら、商品の画像や説明文を設定して商品の登録を行います。
よりたくさんの人の目に留まるためには、魅力的な商品写真と説明文を設定することが大切です。商品画像は必ず複数枚用意し、可能であれば動画もアップすると使用感をイメージしてもらいやすくなります。
また、商品のタイトルや説明文は商品と関連するキーワードなどを盛り込んで、検索で見つけてもらいやすいように工夫するのも一つの方法です。
さらに、サイズや素材は細かく採寸して記載する必要があるほか、注意事項なども漏れがないように記載しましょう。商品登録に欠かせない撮影・採寸・原稿といった「ささげ業務」に就いては、以下の記事も参考にしてみてください。
集客
ネットショップは実店舗とは実店舗とは違い、集客しないとショップや商品を見つけてもらえません。
そのため、ネットショップやECモールで商品を販売する場合は、SNSやWeb広告を活用して集客を行うのがマストといえます。
SNSや広告はそれぞれ用途やターゲット層が違うので、自身のショップやターゲットに合ったものを選びましょう。またWeb広告は検索キーワードによって検索結果に表示されるリスティング広告をはじめ、画像を掲載できるショッピング広告など、さまざまな種類があります。SNSにも有料広告があるので、予算に合わせて広告を導入するのも一つの方法です。
オフラインで販売する場合は、チラシ配布やポストインなどの広告をはじめ、オンラインで集客を行うとコストを抑えて効率的に集客ができるのでおすすめです。
商品の梱包と発送
オフライン販売の場合は発送作業をする必要がありませんが、オンライン販売の場合は、商品が売れたら梱包して発送します。
オフラインやオンラインに関わらず、ブランド独自のシールやボックスを用意すると、ブランドらしさをアピールできるほか、高級感が出るのでおすすめです。
BASEの「canal App」なら、オリジナルパッケージをかんたんに作成できます。商品選択からお見積り、デザイン入稿まで、オンラインで完結できるので、効率的な梱包資材の制作が可能です。
顧客管理
ショップの売上を安定させるためには、新規顧客だけでなく、リピーターを増やす必要があります。2回目以降にショップを利用する顧客にクーポンを配布したり、定期的にキャンペーンを行ったりして既存顧客に購買を促すのも一つの方法です。
BASEには「メールマガジン App」という拡張機能があり、購入経験のある顧客にメールマガジンを一斉送信できます。
また、BASEでショップを開設すると商品を出品できるショッピングアプリ「Pay ID」は、ショップをお気に入り登録してくれた顧客とコミュニケーションを取れたり、ショップの最新情報をプッシュ通知で送信できたりする機能があるので、顧客との信頼関係を構築し、リピーターを増やすのに役立ちます。
ハンドメイドアクセサリーの販売で押さえておきたいこと
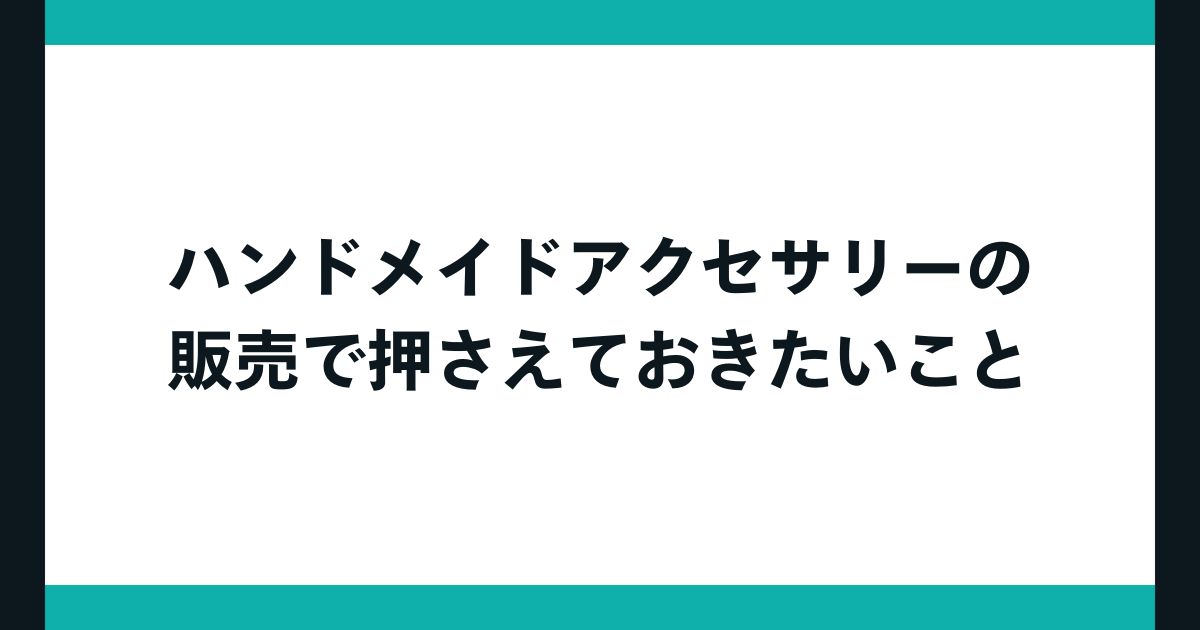
最後に、ハンドメイドアクセサリーをネット販売するさいに知っておきたい、基礎的な知識を解説していきます。
販売に資格は必要?
ハンドメイドアクセサリーを販売するためには、特別な資格や免許の取得がかならずしも必要となるわけではありません。
ただし、直接ハンドメイド作家の顔が見えないネット販売では、資格や経験などをプロフィールなどに明記すると、安心してもらえる可能性もあります。
たとえば、色彩検定や天然石アクセサリー、ハンドメイドアクセサリー、洋裁技術検定など、ハンドメイドに関連する資格や講座は多数用意されているので、気になる場合はチェックしてみるのもよいでしょう。
また、古物商許可証についても、ハンドメイドアクセサリーを販売する上では原則的に必要とされません。
ただし、例外として、古着やアンティーク雑貨など中古の材料を仕入れてリメイクして販売するさいには、「古物」として扱われ、古物商許可証が必要になることもあるので、心配な場合は、管轄の警察署の「生活安全課 」に相談してみましょう。
開業届は必要?
開業届は、事業を開始することを税務署に知らせる届け出です。原則として、ネットショップに限らず、事業を開業したら提出しなければなりません。
とはいえ、なにをもって「開業」とするのか、イマイチわかりにくいですよね。
国税庁によれば、所得税法第229条を根拠に「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」が手続きの対象です。
ハンドメイド販売は事業所得に該当しますが、事業所得というのは一般的に、一時的な収入ではなく、継続してなんらかの対価として収益を得る場合を指します。
そのため、ハンドメイド販売を継続的にはじめたさいに開業届を出す、というのが妥当かと考えられます。
開業届を出していないことで罰則を受けることはありませんが、メリットも数多くありますので、下記の記事も参考に検討してみてください。
まとめ
今回は、ハンドメイドアクセサリーをネットで販売する方法を紹介しました。ご覧いただいた通り、ハンドメイドアクセサリーを販売する場所は多岐に渡ります。とはいえ、なにも「一箇所だけで販売しなければならない」といった決まりはないので、さまざまなプラットフォームを触ってみることをおすすめします。
ネットショップ作成サービスの「BASE」は、初期費用、月額費用無料で独自のネットショップがかんたんに開設できるので、ハンドメイドアクセサリーの販売が初めての方にぴったりです。売上が伸びてきたら、手数料が業界最安水準の有料プランに切り替えることも可能です。各種SNSとの連携やWeb広告との連携、かんたんに発送できるサービスなど、ショップ運営をスムーズに進めるための機能が充実しています。ぜひBASEで魅力的なネットショップを開設してみてください。
売れるお店を作る機能とサポートが豊富
BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。
ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。
また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。
プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。
さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。
ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。
個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。