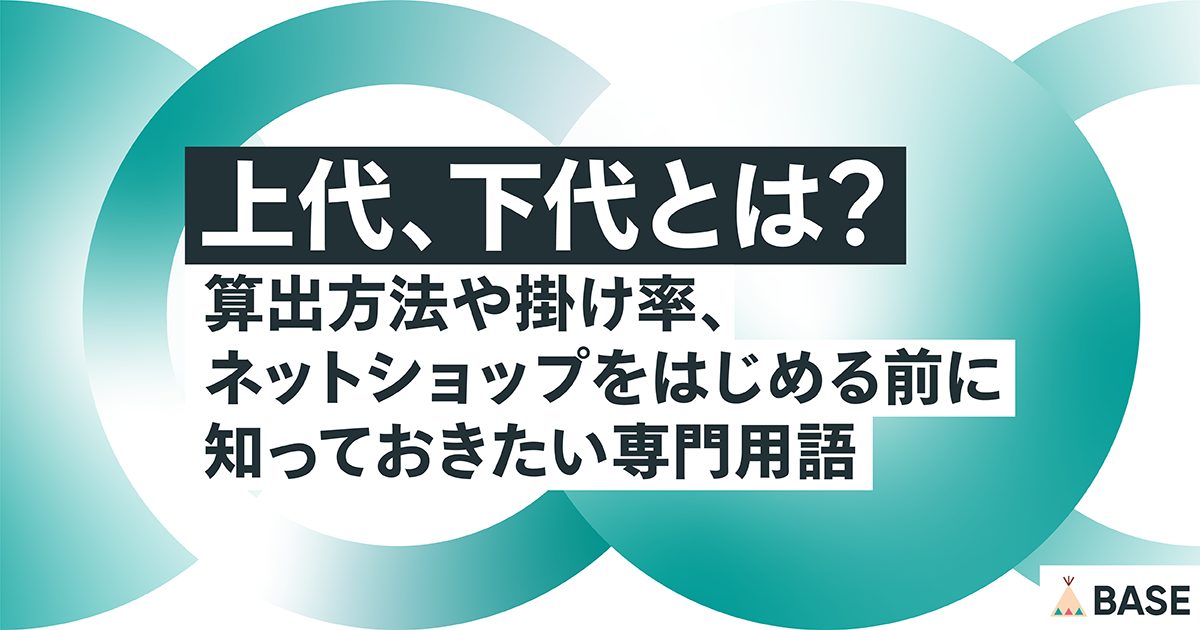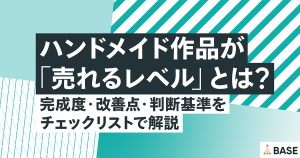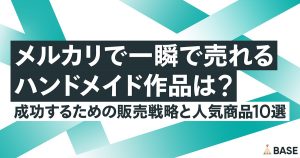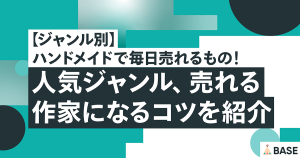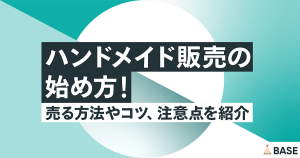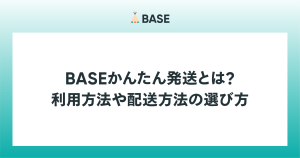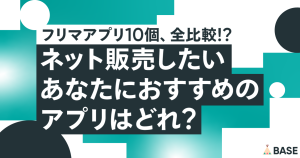ネット物販をはじめると、聞き慣れない用語を耳にする機会も多いでしょう。とくに「上代」や「下代」は仕入れを円滑に進めて、損するのを防ぐためにも覚えておきたい用語です。
そこで今回は、上代や下代をはじめ、商取引の場で使われる専門用語の意味を解説します。また、上代・下代の計算方法や仕入れの際に役立つ知識も紹介しているので、ネット物販を成功させるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
この記事で分かること
- 上代・下代の意味
- 取引でよく使われる専門用語の意味
- 上代・下代の計算方法
【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ
- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです
- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます
- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています
- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています
上代・下代とは 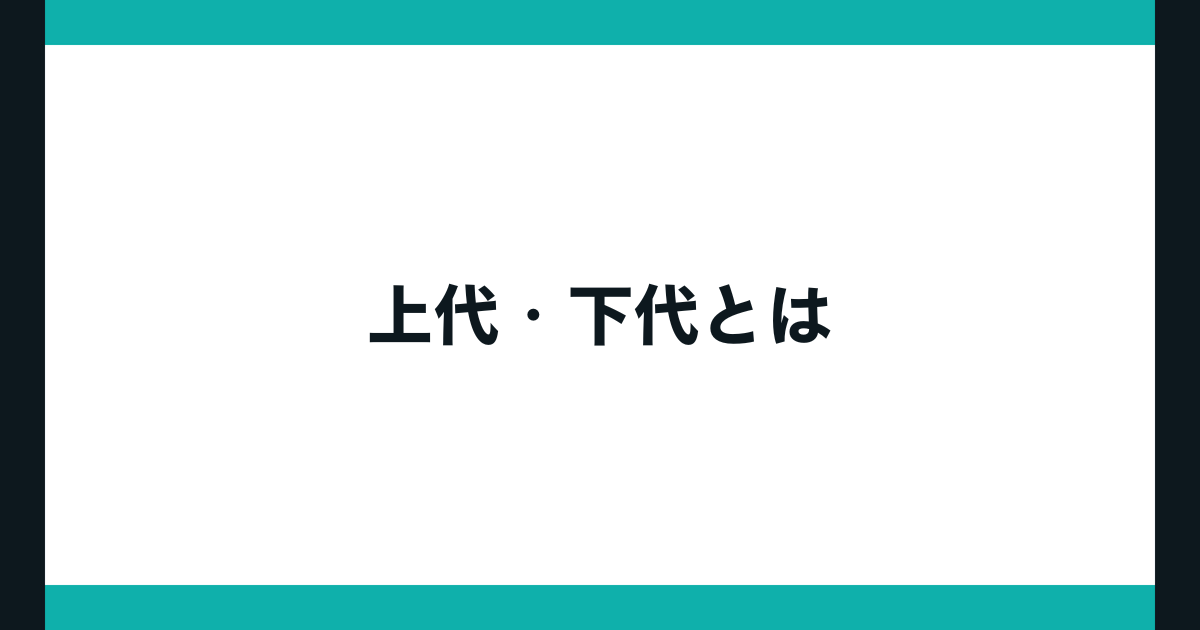
ネットショップを運営してネット物販をはじめようと思っているなら、仕入れでよく使われる「上代」や「下代」などの専門用語を覚えておきましょう。まずは「上代」と「下代」の意味や使い方、似ている用語との違いを解説します。
上代(じょうだい)とは
上代とは、かんたんに言うと商品の販売価格であり、「商品定価」と同様の意味を持ちます。「メーカー希望小売価格」や「参考上代」も上代と同義です。
「定価」を「上代」と呼ぶ人は、小売業を営んでいると思ってまず間違いないでしょう。
上代は、基本的には消費税を含まない価格を指しますが、人によっては消費税込で話している場合もあるため注意が必要です。
オープン価格とは
近年では電化製品などを中心に、メーカーが希望小売価格を決めない「オープン価格」の商品も存在します。
卸サイトなどで仕入れる場合にも、この「オープン価格」を目にする場合がありますので、覚えておきましょう。
定価との違い
「上代」は定価と同じ意味で使われることが多い言葉ですが、厳密に言うと「上代」と「定価」の定義は異なります。上代はメーカー希望小売価格なので、販売者が価格を変更して販売可能です。
しかし、定価は本来、国などが指定した変更できない「販売価格」を意味します。たとえば、たばこや新聞などは価格を変更できない「定価」の商品です。ややこしく感じるかもしれませんが、値下げが可能かどうかで違いを判断してみてください。
下代(げだい)とは
下代とは、卸値や仕入れ価格を意味する言葉です。
下代が低いほど、そして上代が高いほど、利益は大きくなります。メーカーや卸売業者が提示する下代に対して、いくら上乗せして上代を決めるかが、ネットショップ運営の重要な業務となります。
「卸単価」「仕切り」などと言うこともありますが、基本的に下代を用いれば間違いないでしょう。
掛け率(かけりつ)とは
「掛け率」は、商品の販売価格に対する仕入れ価格の割合です。「7掛け」と言えば、定価10,000円の商品なら7,000円が仕入れ価格であることを意味します。
業界では「仕入れ値はいくらですか?」と聞くよりも、「この商品の掛け率は?」と表現する方が一般的です。
業界によって掛け率はさまざまです。商品の定価(上代)、または売値の何%でその商品は買えるか?を知るためにも、仕入れ元に必ず尋ねます。
「掛け率」と「掛け(かけ)」の違いは?
掛け率とはまったく違った意味で、「掛けで買う」という言い方があります。この場合の「掛け」は、月末に締めてその月に仕入れた商品代金分の請求書を出してもらうことを意味します。
1ヶ月の間に何度も仕入れる場合、その都度支払うのは面倒です。そこで月締めでまとめて請求してもらうことを、掛けで買う、といいます。掛けで購入した商品の代金は「買掛金」といいます。掛けで商品を売った側は「売掛金」として計上します。
掛け率は販売時の利益を考えるために用いられますが、掛けは仕入れの支払いに関連する意味だと覚えておきましょう。
掛け売りや後払いはキャッシュフローの流れが悪くなる可能性がある
掛け売りや後払いをする人が多いと、売上金が手元に入るタイミングが遅れ、キャッシュフローの流れが悪くなります。
しかし、BASE独自の決済方法である「あと払い Pay ID」なら、翌月に売上が全額入金されます。「あと払い Pay ID」には「翌月あと払い」と「3回あと払い」の2種類がありますが、顧客がどちらの決済方法を選択しても、ショップに入金されるタイミングは変わりません。
万が一未払いが発生しても全額保証されるので、キャッシュフローが滞る心配がありません。
その他の仕入れ・販売価格に関する専門用語
上代・下代に関する関連用語を紹介します。上代や下代と合わせて使用されることも多いので、取引をする際に齟齬が生まれないよう、ぜひ覚えておきましょう。
- 発注単位(はっちゅうたんい)
商品を仕入れる場合、卸値で買いますが、多くの場合、発注する際の最低単位が決められています。
「発注単位は10ケースからでお願いします」「発注は30万円以上でお願いします」など。
注文するときの単位のことを、発注単位と言います。
- 入数
発注書に、入数と書かれている場合もあります。入数とは、1箱に入っている商品数を指します。
たとえば「入数50個で発注単位1」とある商品の場合、3つ発注すれば150個の商品が届くことになりますので、この入数をベースにして発注数を考えるようにしましょう。
- 元払い(もとばらい)
元払いとは、発注先が送料を負担してくれて商品を送付してくれることを言います。
商品の仕入れで、郵送・宅配で仕入れ商品を送付される際に、送料をどちらが負担するかは重要な問題です。
何も確認せずに進めると、着払いにて送られてくることも少なくありません。元払いにて配送してくれるのか?いくら以上発注すれば元払いになるのか?必ず確認しましょう。
- 発注書(はっちゅうしょ)
注文書のことを指します。「注文の受け付けはFAXのみ」という企業もまだあります。
仕入れ先指定の発注用紙を使わないといけない場合もあれば、自由な形式で注文を出せる場合もあります。発注は電子データでよいのか、FAXなど紙の原本が必要かどうかなど、発注方法を事前に細かく確認しておいた方がベターです。
- 口座(こうざ)
問屋などと取引できることになった場合、「口座を開設する」話になるケースがあります。これは「あなたと継続的に取引してもいいよ」ということを意味します。
ここでいう口座とは、銀行口座のことではなく、「取引先としてデータを登録する」ことをいいます。取引先としてアカウントを開設するイメージです。
口座の開設にあたり、必要な情報提示や書類の記入を求められる場合があります。
上代・下代の算出方法
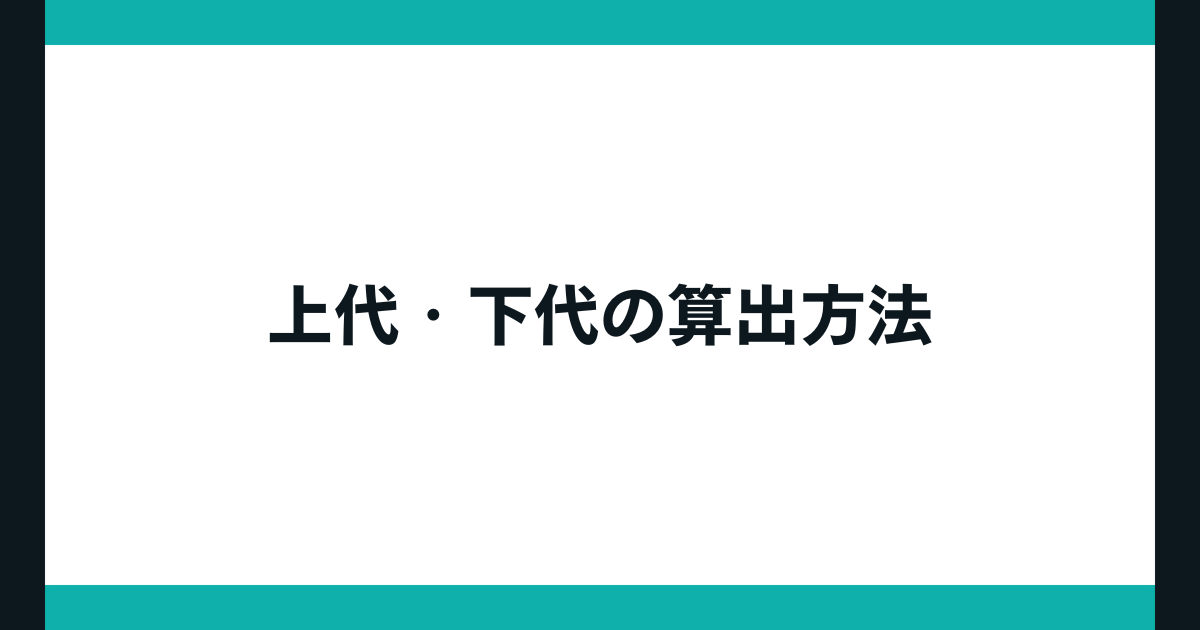
上代と下代をそれぞれ算出する式は以下のとおりです。
- 上代=下代÷掛け率
- 下代=上代×掛け率
たとえば上代10,000円の商品を仕入れる際に、掛け率が60%だった場合の下代は6,000円となります。
上代・下代などの言葉が使われる理由
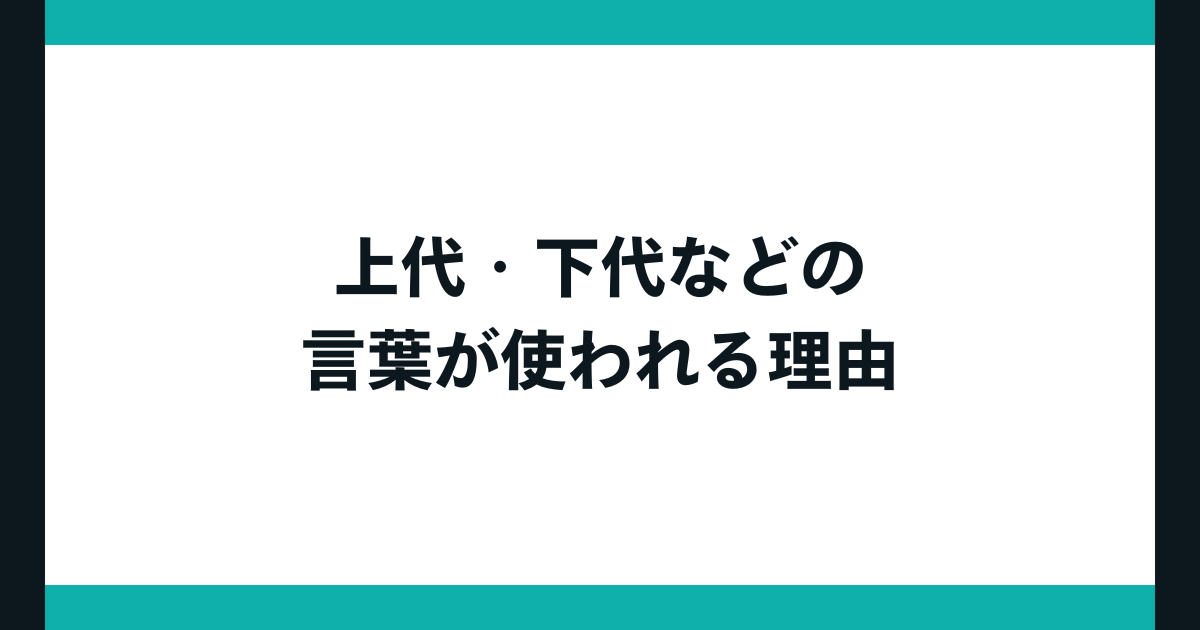
上代や下代は古くから使われている商取引の専門用語です。いつから使われていたか分からない専門用語が現代でも使われている理由は、取引先とスムーズにやり取りするためと言われています。
また、あえて専門用語を使って取引することで、外部に自社の利益などがオープンになりにくいのがメリットです。
上代・下代に関するよくある質問
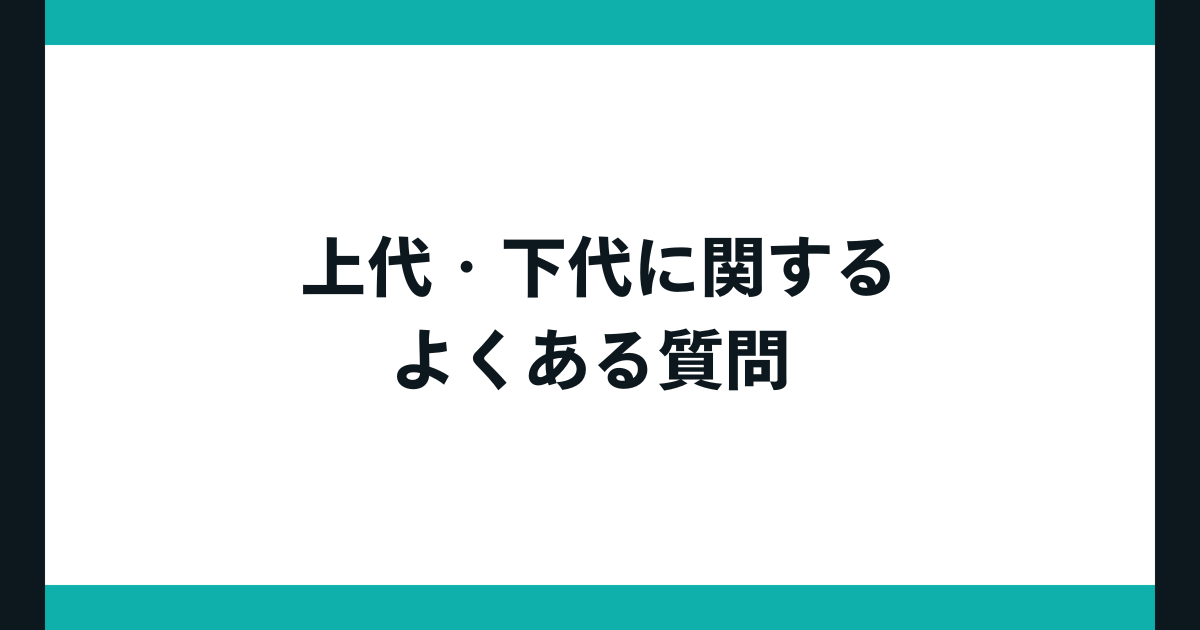
上代・下代に関するよくある質問を集めました。取引の際に使われる税の認識や掛け率の相場などが知りたい場合は参考にしてみてください。
上代は税込?税抜き?
上代は一般的に消費税を含みません。ただし、人によっては消費税を含めた金額を上代としていることもあります。事前に税込か税抜かを確認しておくことで、トラブルに発展するのを防げます。
掛け率に相場はあるの?
商品を仕入れる際の掛け率は業種によって異なりますが、一般的には40〜70%ほどといわれています。たとえば、アパレル業界なら50~60%ほど、食品業界や家電は70%ほどに設定されているケースが一般的です。
掛け率を設定するときはどうすればいい?
自分が商品を納品する立場だった場合は、掛け率を聞かれることもあるでしょう。掛け率には市場のニーズ、競合他社の価格設定、市場における商品の価値など、多くの要素が影響します。
随時相場を確認して参考にすると、掛け率が設定しやすくなります。
BASEでは仕入れを簡略化できるさまざまなサービスと提携しています
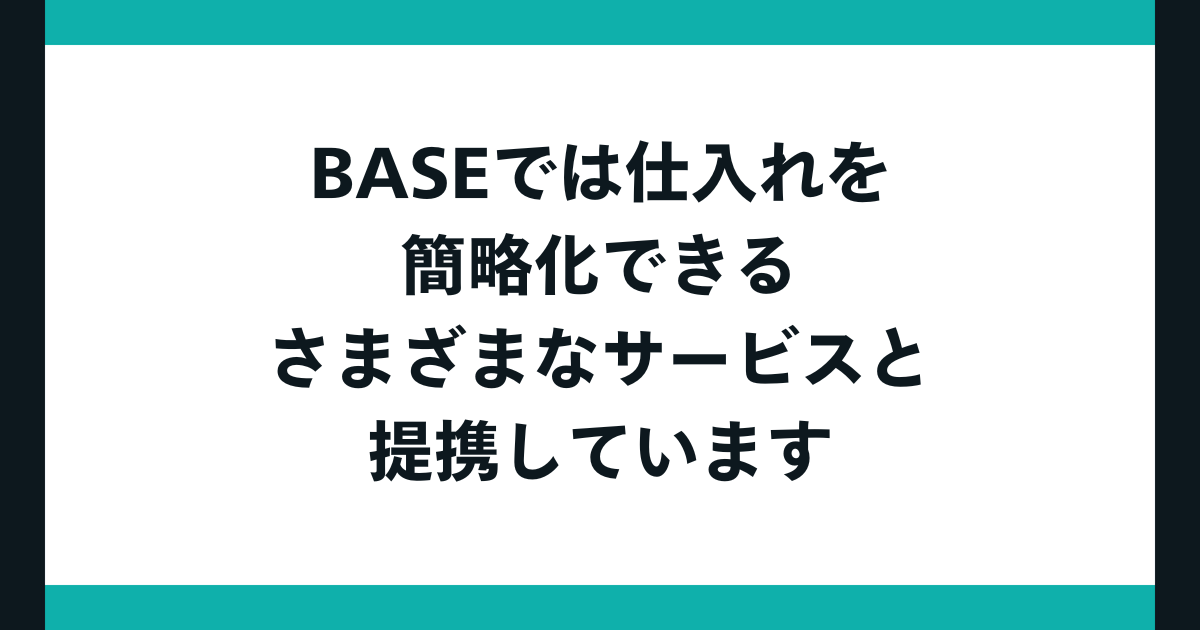
ネットショップ開設実績7年連続No.1(※)の「BASE」では、さまざまなサービスと提携して仕入れから販売までのプロセスのハードルを極力低くしています。
※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)
たとえば以下の記事では、オリジナル商品を受注販売できるサービスを紹介しています。
また「タオバオ新幹線」や「スーパーデリバリー」などとも提携しているので、仕入れやドロップシッピングもスムーズに実施できます。
「BASE」を利用しているアパレルブランドオーナーも参考に
BASEでは多くの方がアパレルブランドを運営しています。
インタビュー記事もたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてください。
商品を仕入れる5つの方法
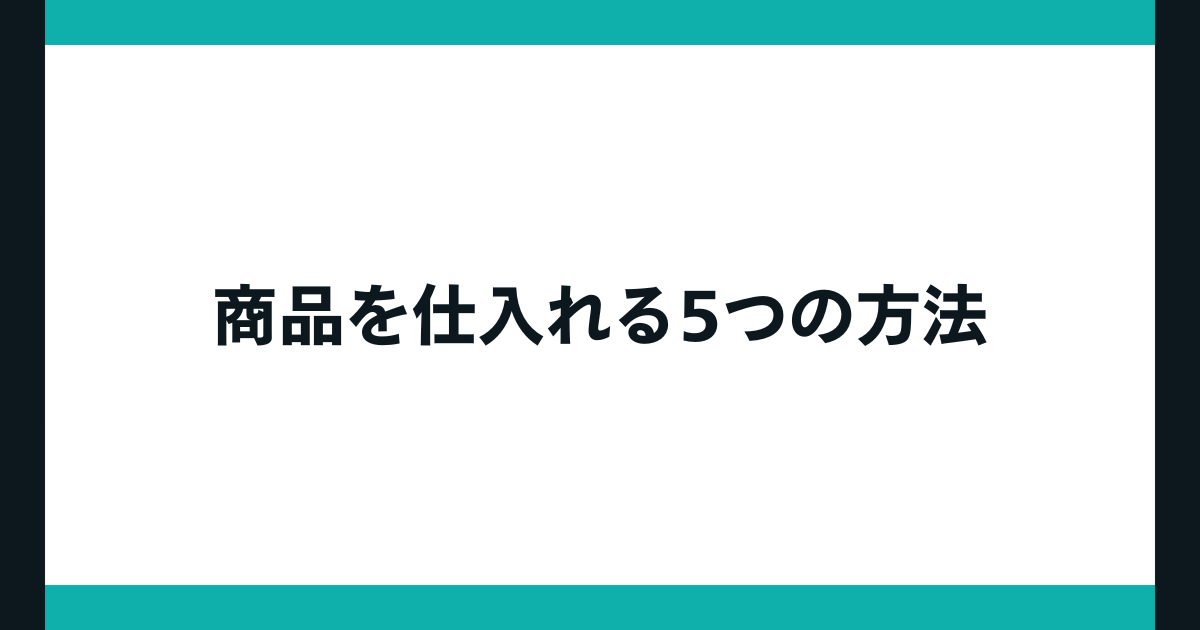
上代や下代などの専門用語を使うのは、おもに仕入れの場面です。
仕入れの場はさまざま。各地で仕入れ商品を見つけるための見本市なども開催されています。ほかにも、商品を仕入れる手段はいくつか存在します。
ここでは、代表的な5つの方法をお伝えします。その他詳しい内容は下記の記事もご覧ください。
方法1:メーカーから直接仕入れる
商品の製造元から直接仕入れる方法です。
日本の商習慣として、卸売業者を通して商品を仕入れる方法が一般的です。
それほど大きくないメーカーで、かつそこそこの発注数があるのであれば、メーカーからの直接仕入れても良いかもしれません。
方法2:実店舗から直接仕入れる
実店舗から直接仕入れる方法です。街を歩いていて、面白い雑貨やビビッと来た商品があればその場で購入して売りに出すこともできます。ぜひ直接仕入れ交渉をしてみましょう。
海外における雑貨屋でも同様です。ネットショップで販売する商品を海外に買い付けにいく人も増えています。
方法3:商社から仕入れる
専門商社から仕入れます。三菱商事や三菱物産、伊藤忠障子などの大手の総合商社から仕入れることはまずありません。
専門商社は海外製品の輸入窓口であり、国内販売の川上と言えます。商社自身がモノを企画・製造することもありますが、小さな専門商社は既成の輸入品を扱うところが多いようです。
方法4:Web上の仕入れサービスを活用する
メーカーとバイヤーを繋いでくれる便利なサービスも、多数存在します。
日本を代表するそのような卸サービスとしては、「BASE」でも連携しているタオバオ新幹線などです。ほかにもグローバルなサービスとしては、アリババが挙げられます。
最初に商品仕入れを考えている方にとっては、もっとも現実的な仕入れ方法ではないでしょうか。
方法5:モノづくりをおこなっている人を見つける
雑貨やアクセサリーに限らず、今や個人でモノづくりをおこなっている人は、多く存在します。
minneやiichiといったサイトで、あなたのショップのコンセプトにあった作り手さんを見つけて仕入れ交渉をするのも一つの手段です。
まとめ
「上代」「下代」は古くからある用語ですが、現在でも仕入れ取引で多く使われています。ネット物販をしている方やはじめようと思っている方は覚えておきましょう。
仕入れにはまとまった資金が必要となるため、ネットショップを効率的に運営するなら、キャッシュフローを円滑にすることも大切です。キャッシュフローをスムーズにすれば「仕入れのための資金がない」「ショップ運営にかかる費用が支払えない」といったトラブルを回避できます。
売上金の振込が翌月以降になるネットショップが主流ですが、ネットショップ作成サービス「BASE」なら、振込申請から10営業日で売上金が振り込まれます。また、「お急ぎ振込」機能を利用すれば、売上金の振込を最短翌営業日まで短縮することも可能です。
BASEは初期費用・月額費用無料でネットショップをかんたんに開設できるので、ぜひBASEで効率的にネット物販をはじめてみてください!
※「お急ぎ振込」は一定の基準を満たしているショップへ順次機能を解放しており、すべてのショップに利用いただけるとは限りません。
売れるお店を作る機能とサポートが豊富
BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。
ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。
また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。
プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。
さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。
ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。
個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。