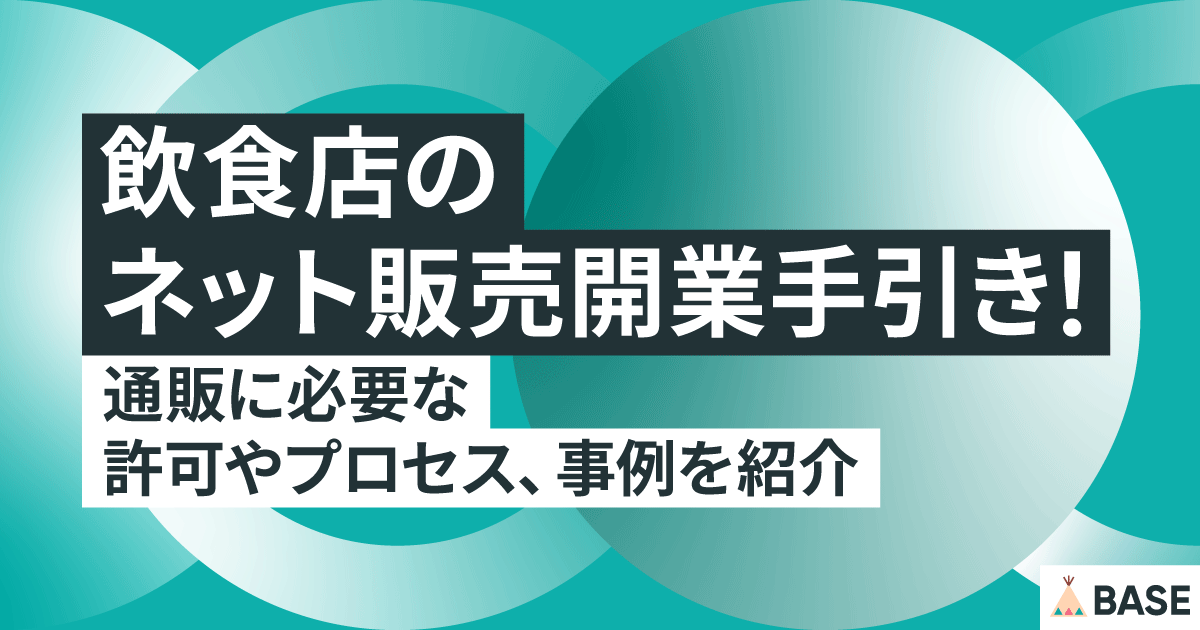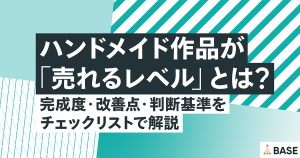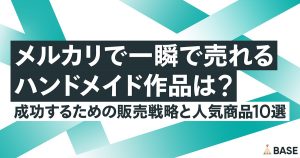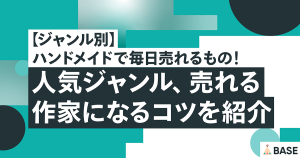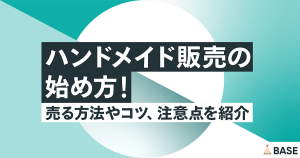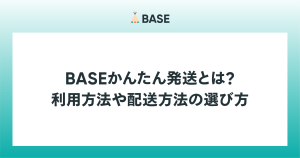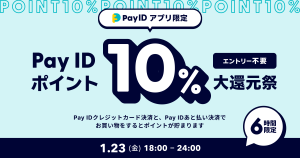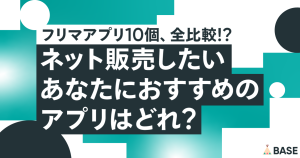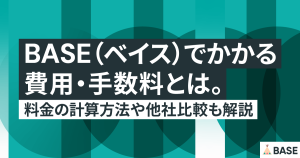飲食店を経営している方の中には、実店舗だけでなく、ネットショップの開業を検討している方もいるでしょう。
とはいえ、実店舗における経営経験はあっても、ネットショップは初めてでどうすればいいのかわからない……という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、これからネットショップを開業したいという方に向けて開業方法を解説します。ネットでの食品販売に必要な許可・資格や、ネットショップ選びのコツ、成功事例なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ
- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです
- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます
- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています
- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています
飲食店がネットショップを開業するメリット
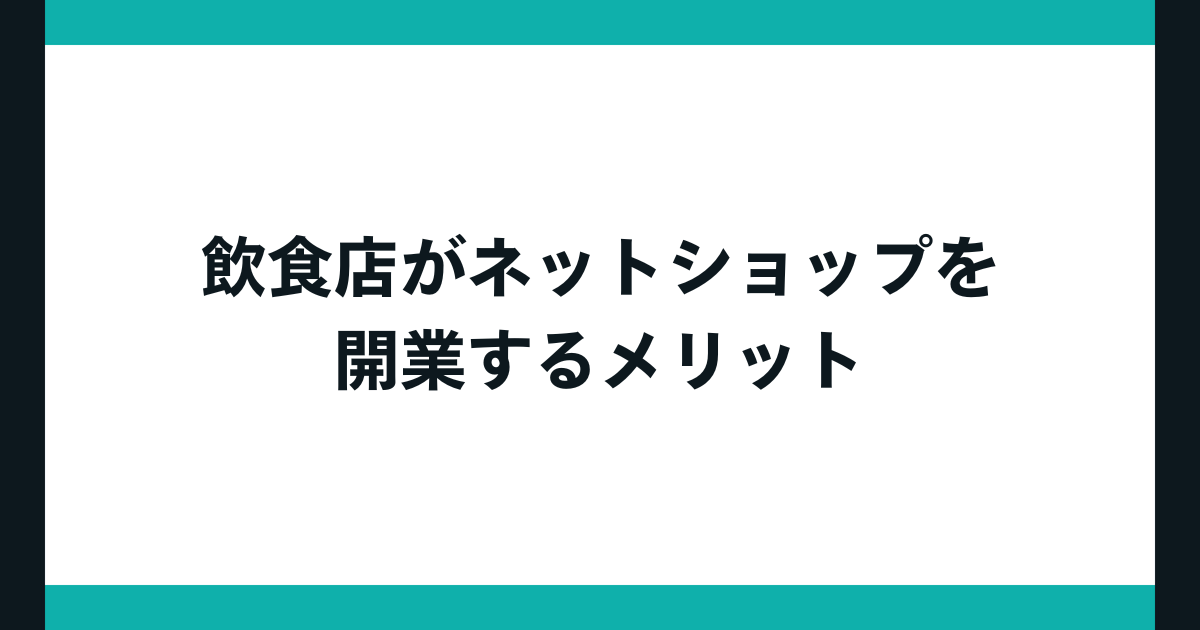
そもそも飲食店がネットショップを開設することに、どのようなメリットがあるのでしょうか。
安定した売上を期待できる
飲食店経営だけでなく、ネットショップを開業すると、ビジネスの軸を増やすことになります。軸が増えることで、コロナ禍のような社会情勢の変化にも強くなるでしょう。
くわえて、ネットショップは実店舗と違って、天候に左右されないことも魅力です。商品の季節感は大切ではあるものの、雨や雪などの悪天候によってネットショップでの商品の売れ行きが下がることはほとんどないでしょう。
また、ネットショップではサブスクリプション型の定期販売のように、固定の収益を確保する販売方法を取り入れることもできます。これらの理由から、安定した売上を期待できることがネットショップの魅力です。
ファンづくりに役立つ
ネットショップであれば、住む場所に関係なく購入できます。そのため、遠方の人はもちろん、実店舗に足を運んだことがない人が商品を食べて気に入れば、来店するきっかけにもなるでしょう。また、実店舗と違って商品を購入した顧客の情報を管理できるため、リピーター向けのアプローチをしやすいのも魅力です。
仕入れの予測を立てやすい
実店舗でも事前予約制であれば、仕入れる食材の予測を立てやすいでしょう。同じようにネットショップであれば注文から発送までに数日かけることもできるため、注文を受けてから商品を用意することも可能です。食材のムダを抑えられるので、コスト削減にも食品ロス防止にも繋がります。
【セミナーレポート】飲食店の新たな挑戦vol.2 売れる飲食店・ネットショップの作り方〜コロナの逆境に負けない新しい手法〜
飲食店のネットショップ開業に必要な許可・資格
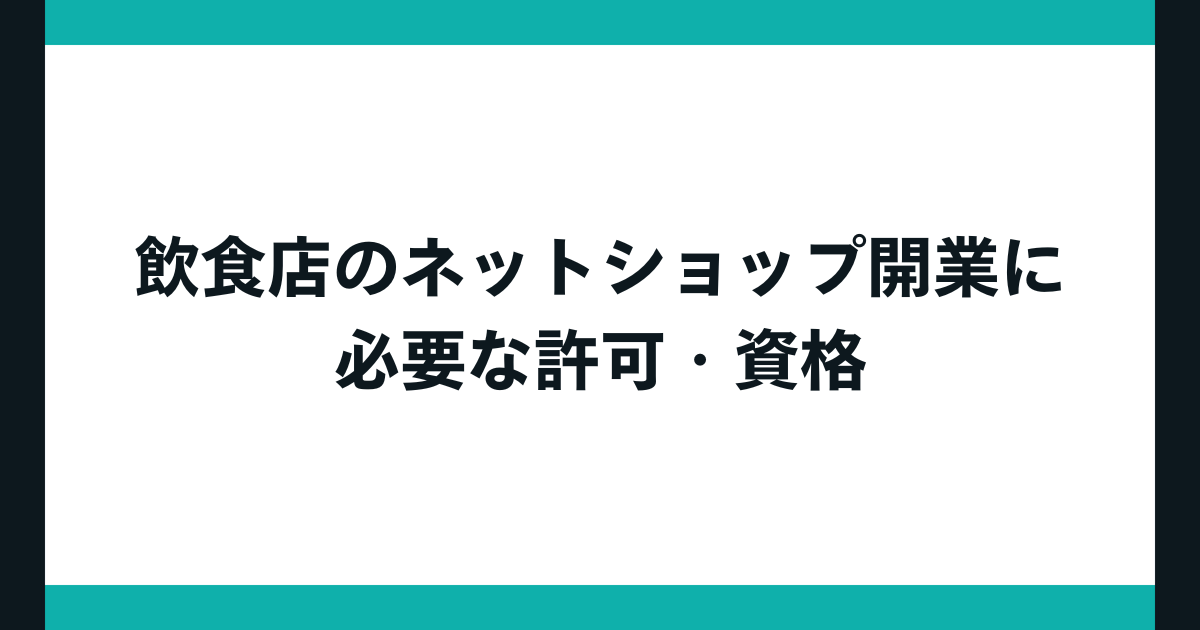
飲食店がネットショップを開業するにあたり、営業許可を別途取得しなければいけないケースもあります。また、イートインやテイクアウト販売と違って、食品表示が必要になるため要注意です。
ここでは、ネットショップ開業に際して押さえておきたい営業許可と食品表示について紹介します。
営業許可
イートインやテイクアウトを行う飲食店であれば、基本的に「飲食店営業」の許可を取得済みです。しかし、ネットショップでの食品販売をはじめる場合は、追加で許可が必要な場合があります。
営業許可は全部で32種類あり、このうちネットショップでの販売に必要な営業許可は次の3つにカテゴライズされます。
- 商品の種類に応じた製造許可
- 商品の包装方法に応じた許可
- 冷凍して発送する場合
それぞれ紹介します。
商品の種類に応じた製造許可
商品のカテゴリごとに許可が分かれていて、それぞれで定められている施設基準を満たす必要があります。主な業種と、食品の例をまとめましたので、販売予定の食品がどれに当てはまるか確認してみてください。
- 菓子製造業:パン、菓子類など ※あん類の製造を含む
- アイスクリーム類製造業:アイスクリーム、シャーベットなど
- 乳製品製造業:乳製品、乳酸菌飲料など
- 清涼飲料水製造業:生乳を使用しない清涼飲料水
- 食肉製品製造業:ハム、ソーセージ、ベーコンなど
- 水産製品製造業:魚介類・魚卵などを使用した食品(あじの開き、明太子、かまぼこ、ちくわなども含む)・そうざいなど
- 食用油脂製造業:サラダ油、オリーブオイル、マーガリン、ショートニングなど
- みそ又はしょうゆ製造業:みそ、しょうゆ、みそ・しょうゆを原料にする食品(粉末みそ・調理みそ、つゆ、たれ、だし入りしょうゆなど)
- 酒類製造業:日本酒・ビールなど
- 豆腐製造業:豆腐、焼豆腐、油揚げ、生揚げ、がんもどき、ゆば、豆乳、おからドーナッツなど
- 納豆製造業:糸引納豆(豆納豆等)、塩辛納豆(浜名納豆、大徳寺納豆、天竜寺納豆など)
- 麺類製造業:生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニなど
- そうざい製造業:煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物など副食品にあたる食品
- 複合型そうざい製造業:食肉処理業・菓子製造業・水産製品製造業・麺類製造業をそうざい製造とあわせて行う食品
- 漬物製造業:高菜漬けなど
また、飲食店営業と同じく、食品衛生責任者の配置も要件となっています。食品衛生責任者は実店舗または製造施設ごとに必要です。ネットショップ開業にあわせてキッチンを新設する場合は、食品衛生責任者の配置も進めましょう。
商品の包装方法に応じた許可
衛生的に食品を発送するためには、包装方法にも配慮が必要です。食品の包装に関する営業許可は、密閉容器とそれ以外とで分けられます。
- 密封包装食品製造業:レトルト包装・かん詰・びん詰めにして発送する場合
- 食品の小分け業:密閉容器以外で包装する場合はこちら
食品の種類にあわせて、適切な営業許可を取得しましょう。
冷凍して発送する場合
食品を冷凍で発送する場合には、「冷凍食品の製造」とみなされ、さらに別途営業許可が必要な可能性があります。
冷凍食品に関する営業許可は、以下のうちのいずれかです。
- 冷凍食品製造業:そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業
- 複合型冷凍食品製造業:冷凍食品製造業と併せて食肉処理業に係る食肉の処理をする営業又は菓子製造業、水産製品製造業若しくは麺類製造業に係る食品を製造する営業
食品表示
食品をネットショップで販売する場合、食品表示が必須となります。
加工食品や生鮮食品、添加物を販売する場合、食品表示基準が適用されるため、パッケージやラベルに食品表示をしなければなりません。
食品に応じて、記載しなければならない内容や表示レイアウトが詳細に定められています。食品表示の項目には、以下のようなものがあります。
- 名称(食品を表す一般的な名称)
- 原材料名(食品に含まれる原材料、添加物、アレルギー情報(特定原材料7品目と、特定原材料に準ずるもの21品目)など。原材料と添加物に分けて、重量順に並べる)
- 内容量(グラム、ミリリットル、個数などの単位で表示)
- 消費期限・賞味期限(一般的に品質が劣化するスピードが早い食品は消費期限、品質が劣化しにくい食品は賞味期限で表示する)
- 保存方法
- 製造者
- 製造所
- 栄養成分表示
このうち加工食品においては、「原材料名のアレルギー表示」「消費期限」「保存方法」の3項目は、かならず表示させなければならないので、覚えておきましょう。
飲食店のネットショップ開業までの流れ
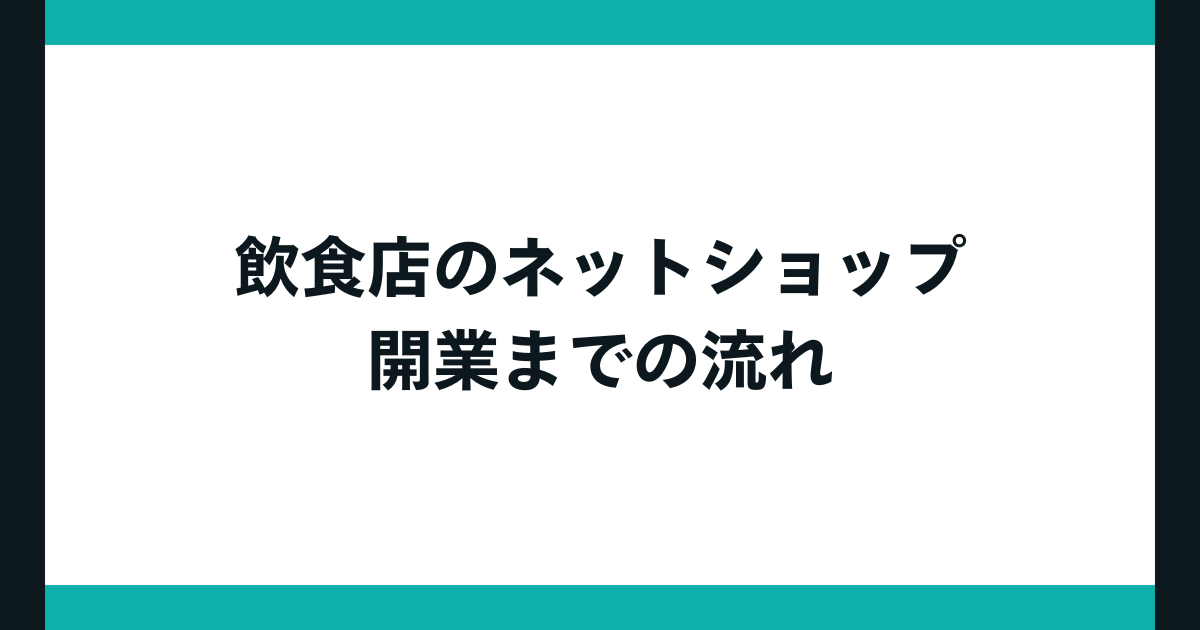
実店舗でサービスを提供していた飲食店がネットショップを開業する場合、どのように進めていけばいいのでしょうか。
ここでは、4つの段階に分けて、ネットショップ開業の流れを解説していきます。
手順1. 販売する商品を企画する
ネットショップを開業するには、まず販売する商品を企画する必要があります。
飲食店のメニューを自宅で味わえる商品を用意するのであれば、どのような状態で販売するのかを考えなくてはなりません。
実店舗で販売している商品を冷蔵・冷凍しただけのものでは、店内で食べるよりも味が落ちてしまう可能性があります。
また、一般の家庭では飲食店にあるようなオーブンや火力の強いコンロはないため、食材セットを販売しても調理工程を再現しきれないことも考えられます。
そのため、食べるシーンを想定した商品開発が必要です。
また、飲食店によっては、オリジナルグッズを販売しているところもあります。
たとえば、ラーメン屋であれば丼ぶりやレンゲ、Tシャツなどです。ほかにも、オリジナルのキャップやソックスを作っている飲食店もあります。
最近であれば、レジ袋有料化にともなって、エコバッグやトートバッグを販売するネットショップも多く見られます。
手順2. 保健所に許可をもらう
ネットショップでどんな商品を販売していくかを決めたら、次は 、開業に必要な許可を保健所にもらう必要があります。
食品をネットショップで販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可を得なくてはなりません。
一から製造や加工を行ったものを販売する場合、「製造・加工業」の免許が必要です。さらに、食品の種類によって、それぞれ異なる許可を取得しなければなりません。注意しましょう。
たとえば、ジャムを販売するなら「かん詰又はびん詰食品製造業」が必要になる可能性がありますし、冷凍した食品を販売するなら「冷凍食品製造業」の免許が必要です。
販売を予定している食品にどんな許可が必要か、事前に調べておくようにしましょう。営業許可については、以下の記事でくわしく解説しています。
手順3. ネットショップの開設
販売する商品の決定、営業免許の取得とあわせて、準備しておかなければならないのがネットショップです。
ネットショップを開設する方法は、大きく分けると3つあります。
- 制作会社にネットショップ作成を依頼する
- 既存のモール型ネットショップに出店する
- ネットショップ作成サービスを使って自力で立ち上げる
コストをかけたくない、早く開設したいという場合は、3.のネットショップを自作する方法がおすすめです。まずは、それぞれの方法でどのような違いがあるのかを説明します。
制作会社にネットショップ作成を依頼する場合
制作会社にショップ作成を依頼する場合、フルスクラッチといって1からすべて作り上げるパターンや、パッケージソフトを使って構築してもらう方法などさまざまな手段があります。
ただし、総じて構築費用や維持費用が比較的高く、作成期間も長くなる傾向にあり、企画から実際の運用開始までに最低でも3ヶ月以上かかると思っておく必要があります。
コスト面に関しては、構築方法にもよりますが、制作会社に依頼をするため最低でも数十万円以上はかかることを想定しておきましょう。
既存のECモールに出店する場合
楽天市場やYahoo!ショッピングといったモール型ネットショップに出店するという方法もあります。
知名度の高いモールであれば集客しやすいというメリットがありますが、初期費用や維持費用は比較的高額になる可能性が考えられます。
大手モール型サイトを例にあげると、以下のような費用がかかります。
|
初期費用 |
一律60,000円 |
|
月額出店料 |
25,000〜130,000円/月+システム利用料等 |
|
システム利用料 |
2.0〜7.0% |
|
契約期間 |
1年間 |
|
モール独自ポイント利用料 |
購入した代金の通常1.0% |
|
モールにおける取引の安全性・利便性 |
月間売上高の0.1% |
|
アフィリエイト手数料 |
アフィリエイト経由の売上の2.6〜5.2% |
|
メッセージ機能 |
月額3,000〜5,000円 |
|
決済手数料 |
月間決済高の2.5〜3.5% |
また、モール内に広告を掲載する場合、掲載枠や掲載期間によって費用が異なり、40,000〜1,200,000円程度かかるといわれています。
コストを抑えて早く開設するなら、ネットショップ作成サービス
できるだけコストを抑えて、早くネットショップを持ちたいのであれば、ネットショップ作成サービスを利用して自作するのがおすすめです。
ネットショップ作成サービスの「BASE」は、ネットショップ開設実績7年連続No.1のサービスです(※)。
※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)
実際にショップの構想〜開設まで1ヶ月もかからず進めるオーナーさんが多く、その迅速性は非常に好評です。くわえて初期費用・月額費用が0円のプランもあり、商品が売れるまで0円でショップを運営することが可能です。
BASEには、「テイクアウト App」をはじめ、飲食店に便利な拡張機能もたくさんあるので、運営形態にあわせて快適にショップ運営を続けることができます。
手順4. 商品の梱包・発送
ネットショップで商品を売る場合、「商品の梱包・発送」が必要です。食品を取り扱うので、基本的には冷蔵・冷凍配送になるでしょう。
冷凍配送の場合は冷凍食品扱いになるため、「冷凍食品製造業」または「複合型冷凍食品製造業」の営業許可が必要です。冷蔵配送の場合は届出対象となるため、保健所に確認して書類を提出してください。常温で保存可能な食品であれば、原則許可・届出は不要です。
冷蔵・冷凍食品の梱包方法については、商品が入る大きさのダンボールを用意しましょう。ダンボールは、100円ショップやホームセンターなどで購入できます。
また通販でかんたんに購入できますし、BASEと連携している「canal」などのサービスを利用すれば、オリジナルのダンボールも作成可能です。
ダンボールの底には、結露が出ても大丈夫なように、新聞紙などを敷き詰めましょう。その上に商品を置いたら、保冷剤などを一緒に入れます。隙間がある場合は、丸めた新聞紙や緩衝材を詰めるといいでしょう。そのほか、発泡スチロールを代用する方法もあります。
荷物持ち込み時に冷たい状態にしておく「予冷」が不十分だと、配送会社に受け取ってもらえないリスクがあるため、冷蔵庫や冷凍庫を利用してしっかり温度を下げておきましょう。また、アイスは冷凍便の対応温度よりもさらに低い温度が適温なので、ドライアイスを詰めるなどの工夫が必要です。
主要配送会社の冷蔵・冷凍便を比較
送料については、利用する配送業者や商品のサイズ、郵送先の地域によって料金が異なります。そこで、配送会社主要3社の冷蔵・冷凍サービスを比較してみました。
|
|
日本郵便 |
ヤマト運輸 |
佐川急便 |
|
冷蔵 |
○ |
○ |
○ |
|
冷凍 |
× |
○ |
○ |
|
60サイズ |
820円〜+225円 |
1,210円〜 |
910円〜+275円 |
|
80サイズ |
1,130円〜+360円 |
1,551円〜 |
1,220円〜+330円 |
|
100サイズ |
1,450円〜+675円 |
1,969円〜 |
1,520円〜+440円 |
|
120サイズ |
1,770円〜+675円 |
2,563円〜 |
– |
|
140サイズ |
2,120円〜+1,330円 |
– |
2,180円〜+880円 |
※東京→東京で計算した場合の料金(2024年9月時点)
配送業者によって温度が異なりますので、商品に適した温度で配送できるかどうかもチェックしておきましょう。
BASEではヤマト運輸と連携して、送料を全国一律にできるサービス「かんたん発送(ヤマト運輸連携) App」を提供しています。クール便も対象になっている上、伝票作成の負担を減らせるなど、飲食店営業の合間にネットショップを運営する場合にもぴったりな機能が備わっていて便利です。
飲食店のネットショップ開業で気をつけたい、4つのこと
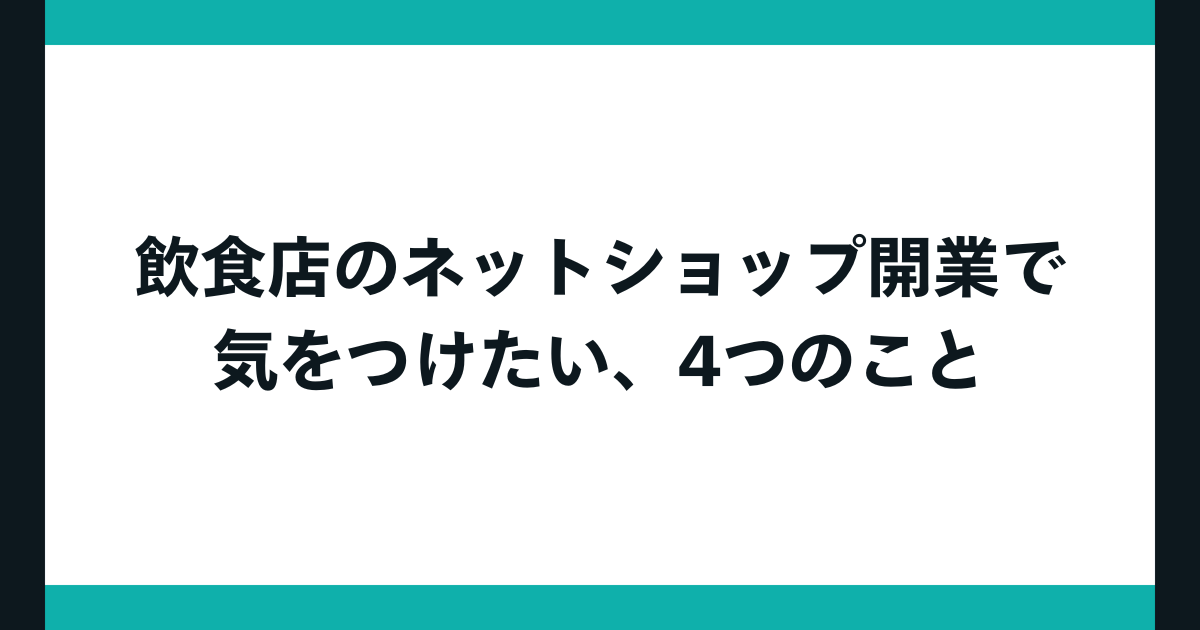
飲食店がネットショップを開業するにあたって、以下、気をつけたい点が4つあります。
- 特定商取引法について理解する
- 商品写真にこだわる
- 商品の説明書きを作成する
- 積極的に集客する
それぞれくわしく解説していきます。
特定商取引法について理解する
ネットショップを運営する準備として、特定商取引法についてしっかり理解を深めておくことをおすすめします。
特定商取引法とは、通信販売などのトラブルから消費者を守るために、事業者に対して定められた法律です。
ネットショップのオーナーにも適用されていて、以下の項目を記載するよう義務づけられています。
・事業者の区分と氏名(法人名または個人名)
・事業者の所在地
・事業者の連絡先
・営業時間・ショップ情報など
・販売価格
・代金の支払方法・時期
・商品のお届け時期
・返品についての規定
ネットショップの特性上、商品が手元に届くまで状態を確認できません。そのため、ネットショップ特有のトラブルが起こるケースがあります。
BASEなら、個人の利用に限り「事業者の所在地・連絡先」を非開示にすることができるため、安心してネットショップを開設することが可能です。
くわしくは、下記のページをご確認ください。
商品写真にこだわる
商品販売ページには、商品が美味しそうに見える写真にくわえて、家で食べるシーンを想像しやすい写真のどちらも入れると効果的です。
美味しそうに見える写真とは、湯気や果汁・肉汁などを強調したシズル感のある写真が代表的です。一方で、家で食べるシーンを想像しやすい写真は、食べあわせのいい他の料理が映り込んでいたり、食べる様子を写したりした写真が当てはまります。
どちらも自然光の入り込むスペースで日中に撮影することで、より美味しそうに見える写真が撮れるでしょう。食品写真を上手く撮る手法は以下の記事でくわしく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
商品の説明書きを作成するとなおよし
食品をネットショップで販売する場合、実際の調理などは、商品を受け取った消費者が行うことになります。
商品だけ送っても、実際にどうやって調理すればいいのかわからない、と困ってしまうケースがあるかもしれません。
そのため、商品とあわせて、温め方や調理方法などの商品の説明書きを作成し、同梱しておくといいでしょう。
商品の美味しい食べ方や、アレンジメニューなどもあると、喜ばれます。
オンラインショッピングは、届くまで内容を確認できない不安こそあれ、商品が届くまでのドキドキ感や、開封するときのワクワク感は楽しくて魅力的なものです。
購入者が商品を受け取ったときに喜んでもらえるような工夫を施してみましょう。
積極的に集客する
飲食店のネットショップであれば、集客ツールはInstagramとYouTubeがおすすめです。
Instagramは写真が中心のSNSなので、食べ物との相性がよく、高い集客効果を期待できます。フィードやストーリーを投稿するだけでなく、広告の出稿も可能です。アルゴリズムを活用して、似たカテゴリの情報を収集する顧客にアプローチできるため、新規顧客との接点を持つきっかけにもなります。
動画サイトのYouTubeでは、写真だけでは伝わらないシズル感や食の体験を伝えられます。全世界のアクテブユーザーが25億人と、莫大な利用者数を持つプラットフォームなので、国内はもちろんインバウンド需要にもアプローチしやすいのも魅力です。さらにYouTubeショッピングを活用すると、動画内やチャンネルに商品の情報を掲載できます。動画から商品ページへとシームレスに誘導できるため、ショップへの集客に役立つでしょう。
また、他のショップと差別化するためには、料理の写真や動画だけでなく、商品やショップに関するストーリーを作ることも重要です。成功しているショップの事例から学びながら、自分のショップのストーリーを考えていきましょう。
飲食店のネットショップ成功事例
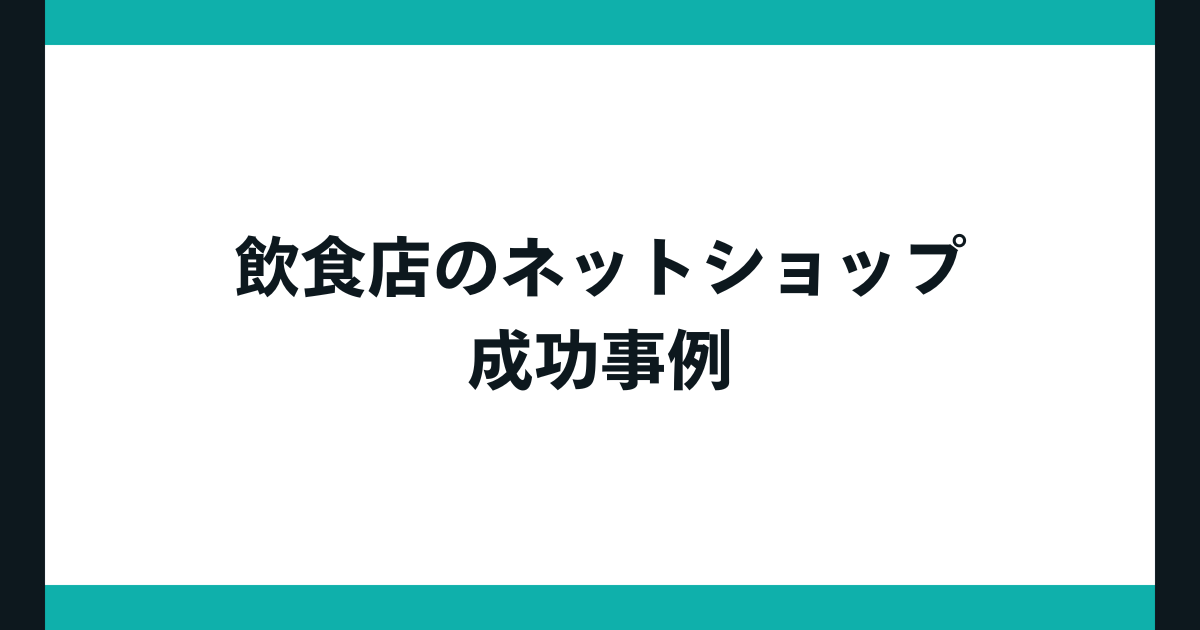
飲食店の経営と並行して、BASEでネットショップを開設した事例を4つ紹介します。
予約が取れない焼肉店の味を自宅で楽しめる|焼肉ヒロミヤ
予約が2年待ちの人気焼肉店「焼肉ヒロミヤ」では、実店舗の座席数が限られていて迎えられる顧客数が限られていたため「食べたいけどなかなか食べられない」という声が多く届いていました。
そうしたニーズを受けてBASEで立ち上げたネットショップでは、仕込み専用の厨房で加工した焼肉用の肉を取り扱っています。ネットショップの立ち上げに必要な営業許可の取得や保健所の申請は、1週間ほどで完了したそうです。
包装は肉の品質を保つために、肉同士がくっつかないよう配置し、冷凍で発送しても劣化の少ない部位を選ぶなどの工夫を行っています。また、家庭では炭焼きではなくフライパンやホットプレートなどでの調理になるため、家庭向けの味付けや調理方法にも配慮して商品を開発してきました。
そうした取り組みの結果、ピーク時は150〜200セットがたった3分で完売になったほどの人気を誇っています。商品がたくさん売れたあとも、BASEでは振込申請をすれば10営業日で売上金が振り込まれるため、短い入金サイクルで運営できるのも魅力だそうです。
テイクアウトの予約・決済をネットショップで実施|海鮮ふじ
新鮮な海鮮が名物の大阪の居酒屋「海鮮ふじ」では、コロナ禍をきっかけに、ネットショップで予約して実店舗で商品を受け取る予約販売をはじめました。実店舗では3万円以上するような食材を使った宴会セット(おうちでHappy体験セット)を約1万円で販売していました。
ネットショップという形態を選んだのは、予約販売が口コミで広まったことで、従業員が電話対応に追われてしまっていたためだそうです。BASEの「テイクアウトApp」を活用すれば、事前に決済できるため、予約後にキャンセルされるリスクを避けられるのも魅力だと語っています。
実店舗では難しい大人数の受注も可能に|カレー屋ヒゲめがね
長野県にある「カレー屋ヒゲめがね」は、元食品メーカー勤務のオーナーが、クラウドファウンディングで資金を集めて立ち上げたショップです。実店舗は、オーナーが家族との時間を確保するために、週4日ランチのみ営業しています。営業時間が限られているため、受け入れ可能な顧客数が限られていることに悩んでいました。
そうした中で顧客からテイクアウトの希望が寄せられるようになり、BASEでネットショップを立ち上げて「テイクアウトApp」を活用した予約受付をスタートしました。会社員のランチや家族でのごはんなど、実店舗では応じられなかったような顧客ニーズも満たせているそうです。
【飲食店の新たな挑戦 vol.3】「飲食店の新しい価値提供を」家族ファーストの店主がIターン先で営む<カレー屋ヒゲめがね>の奮闘
二つ星フレンチの将来を見据えた生き残り戦略|Edition Koji Shimomura
東京・六本木にあるミシュラン二つ星のフレンチ「Edition Koji Shimomura」も、コロナ禍をきっかけにネットショップを開業しました。ネットショップ立ち上げ当初のコンセプトは、「家でも店でも食べられない、“まかない食”」です。
ネットショップを立ち上げるために冷凍庫を3台増やし、営業前後の時間にネットショップ用の商品の仕込みを行うなど、費用・手間ともに増えました。下村シェフは、こうした負担は今後も店が生き残っていくために必要な戦略だと認識しているそうです。
コース内で提供しているスイーツ「ピーカンナッツショコラ」の販売が中心となっています。
まとめ
今回は、飲食店を経営している方に向けて、ネットショップの開業方法を解説しました。
ネットショップには、実店舗とは異なる運営が求められるだけでなく、さまざまな許可や届出などが必要です。また、ネットショップにもいろんな選択肢がありますので、コスト面やサービス面を比較しながら、自分に合った方法でネットショップを開設しましょう。
ネットショップ作成サービスの「BASE」のオーナーさんにも、実店舗とあわせてネットショップを運営する方が数多くいます。サブスクのように定期的に商品を届けられる「定期便App」や、テイクアウトの事前予約を受付できる「テイクアウトApp」など、飲食店にぴったりの機能が豊富に備わっているので、実店舗との相乗効果も狙えるでしょう。ネットショップの立ち上げを検討中であれば、ぜひBASEをチェックしてみてください。
売れるお店を作る機能とサポートが豊富
BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。
ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。
また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。
プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。
さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。
ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。
個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。