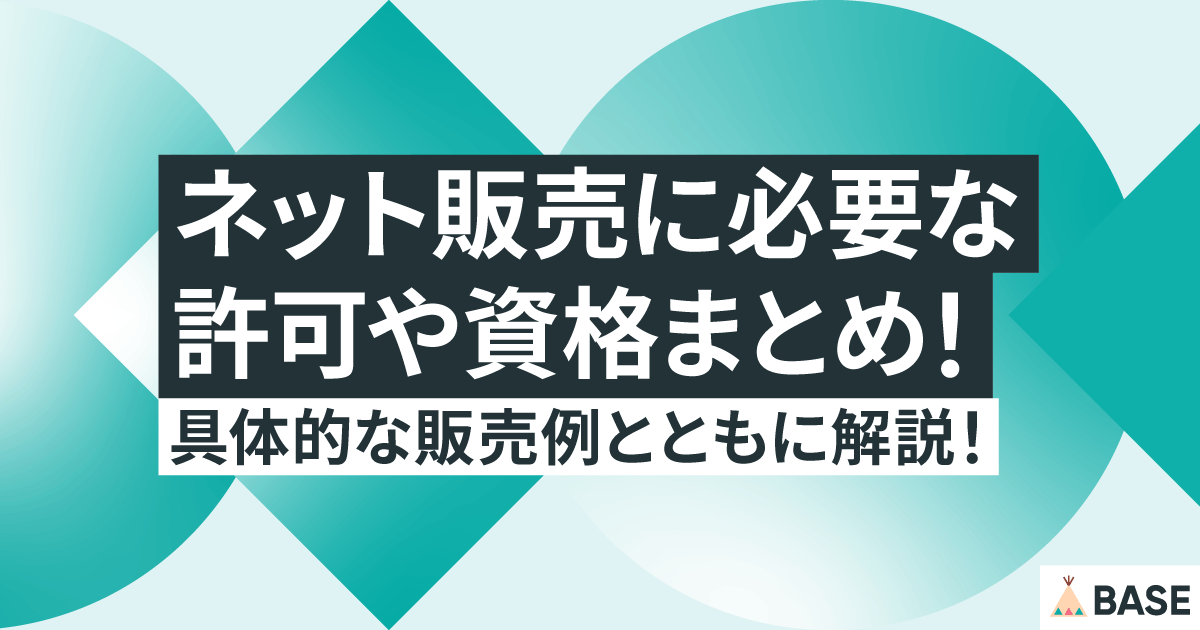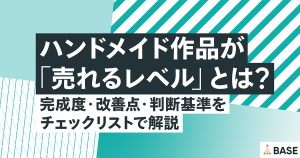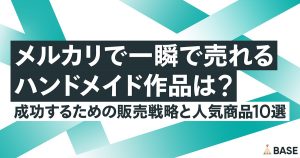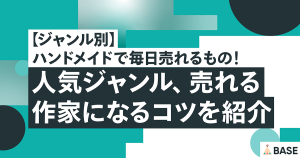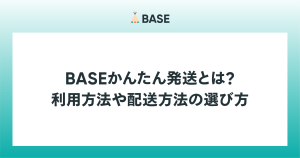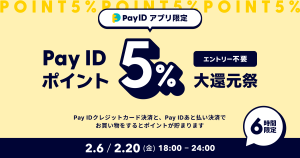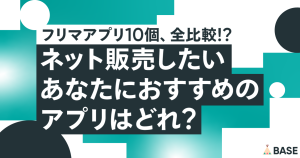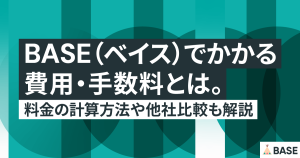ネットショップで商品を販売する場合、商品によっては販売の許可や資格などが必要となってきます。「自分が売ろうと思っているものは許可がいるのだろうか?」と不安な方も多いでしょう。
許可や資格を取得せずにネット販売をはじめると、警察や官公庁からペナルティを課される可能性があるため要注意です。
また、原材料や仕入れ商品を海外から輸入する場合、国内とは異なる税金ややり取りが発生することもあります。
そこでこの記事では販売する商品ごとに、必要な許可や資格、その取得方法までくわしく解説します。商品の品目を問わずネット販売に必須の「特定商取引法」や開業届についても紹介しますので、参考にしてください。
【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ
- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです
- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます
- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています
- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています
ネットショップ開業に必要な許可や資格一覧
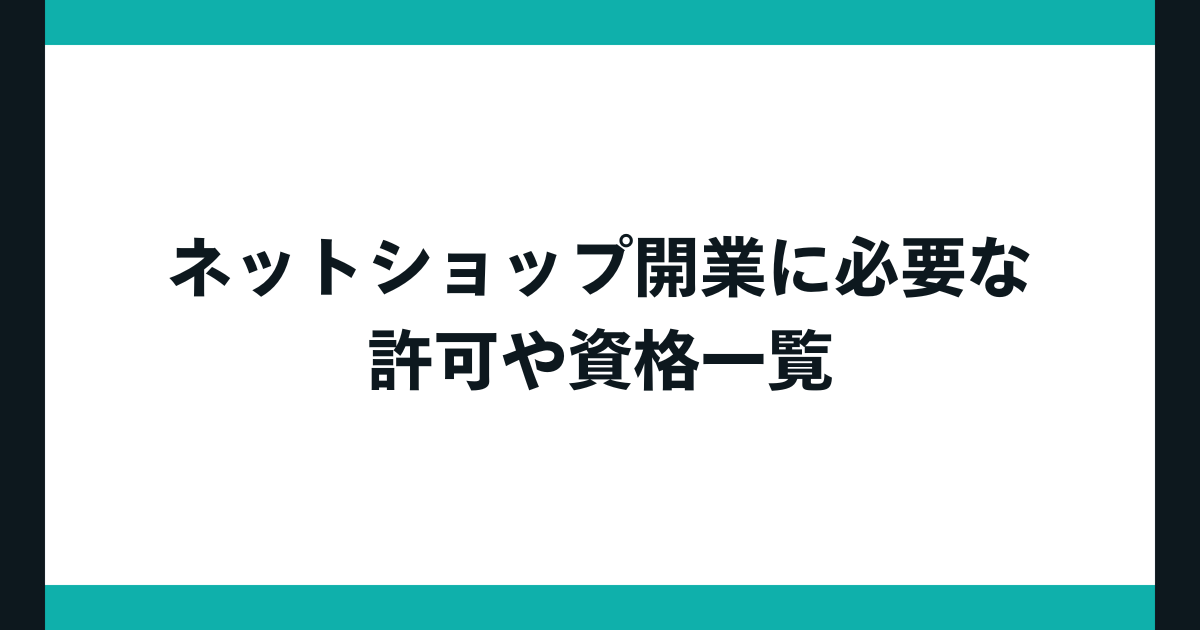
はじめに、ネットショップで販売される代表的な商材と、それぞれに必要な許可や資格をまとめてみました。くわしくは後半で解説していますので、参考にしてみてください。
|
商材 |
必要な許可や資格 |
|---|---|
|
衣類 |
許可:不要 |
|
古物 |
許可:古物商許可 |
|
香水・化粧品 |
許可:化粧品製造販売業許可 |
|
お酒 |
許可:通信販売酒類小売業免許 |
|
農産物 |
許可:不要 |
|
魚 |
許可:食品衛生法に基づく営業許可 |
|
加工食品 |
許可:食品衛生法に基づく営業許可 |
|
サプリメント・健康食品 |
許可:食品衛生法に基づく営業許可 |
洋服のネット販売に必要な許可
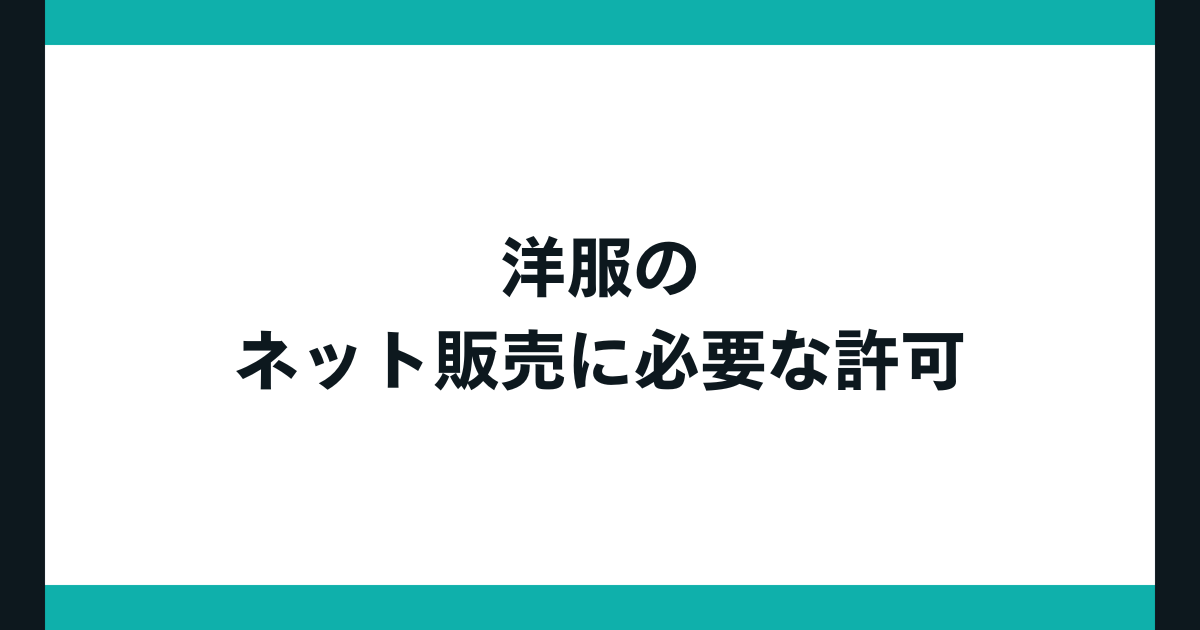
新品の洋服を仕入れてそのまま販売するだけなら、特に許可や資格は不要です。
ハンドメイドの洋服をネット販売する場合でも、許可や資格は必要ありませんが、家庭用品品質表示法に従った「品質表示」を付ける必要があります。くわしくはこちら。
品質表示には「綿100%」など繊維の成分と、「洗濯表示」「会社名(個人名)」「連絡先」の記載が必要です。
また古着をネット販売する場合については次の「古着」の項目をご確認ください。
古着・アンティーク雑貨のネット販売に必要な許可や資格
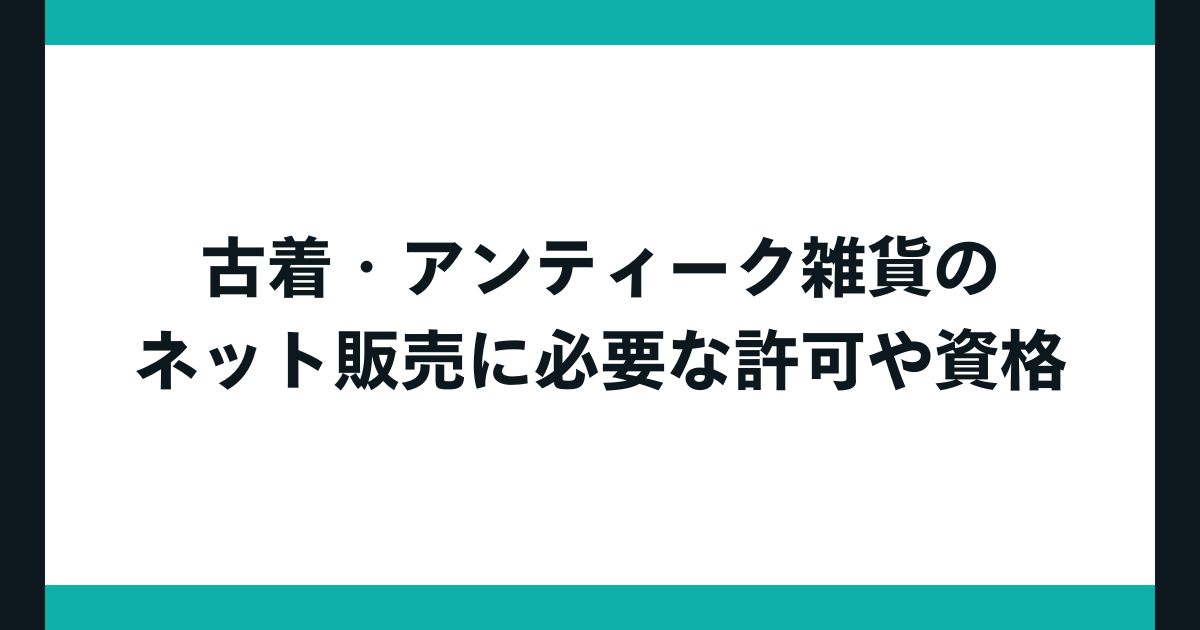
古着やアンティーク雑貨をはじめとする中古品の販売には、「古物商許可」を取得する必要があります。
個人で使うために購入した不用品を、メルカリなどのフリマアプリで販売する場合は、古物商許可がなくても問題ありません。
しかし、個人事業主や法人が中古品を仕入れて販売する場合は「古物商許可申請」が必要です。
たとえば古着やアンティーク雑貨、古本をはじめ、ハンドメイドに中古の材料を使ったり、中古の部品を使ってカスタマイズした機械を扱ったりする場合などに、古物商許可が求められます。
古物商許可には13品目あり、その中から必要な品目を選んで許可を取得することになります。
衣類
時計・宝飾品類
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類
皮革・ゴム製品類
書籍
美術品類
金券類
自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
古物商許可は、盗品の売買防止を目的としたものです、許可なく古物商を行うとペナルティが課されるリスクがあります。
古物商許可を取得する窓口は、管轄の警察署です。書類(許可申請書、登記事項証明書、住民票の写し、身分証明書など)を提出して手数料(19,000円)を支払うことで取得できます。
「商品が古物にあたるかどうかわからない」と心配な方は、一度相談してみてください。
香水や化粧品のネット販売に必要な許可や資格
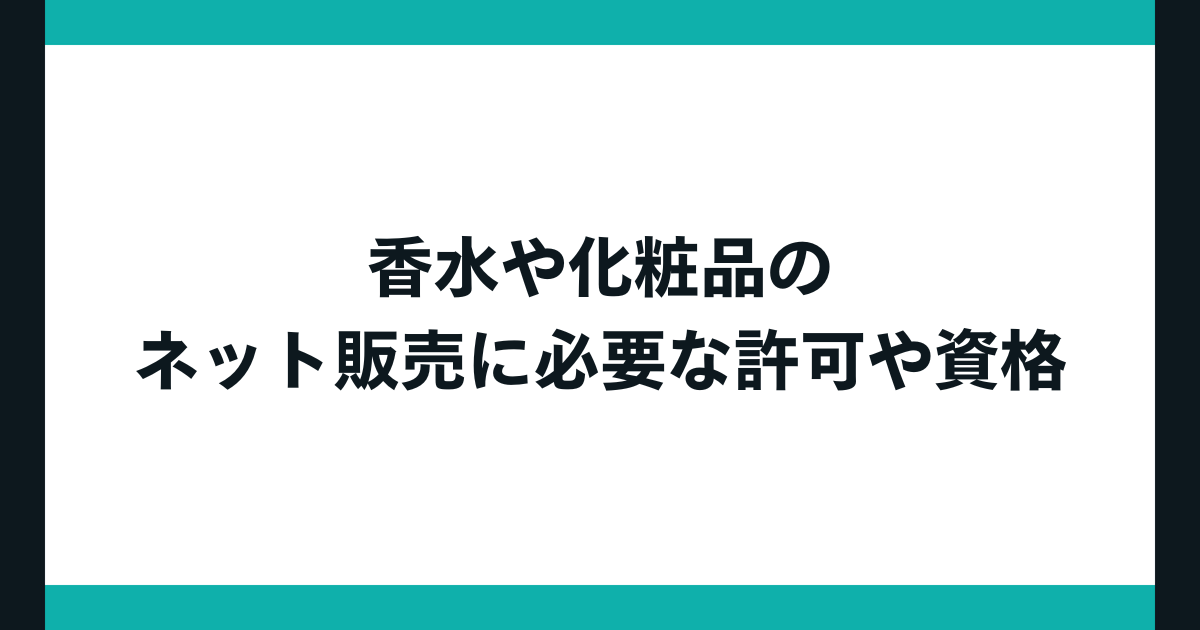
化粧品をオリジナルで製造して販売するには許可が必要ですが、単に化粧品を仕入れて加工せずにそのまま販売するだけなら、許可や資格は不要とされています。
なお国内で製造された化粧品ではなく、海外の化粧品を個人で直接輸入して販売する場合にも、許可を取得しなければなりません。
ちなみに香水や手作り石けんなどの簡易的なものであっても、「肌」「顔」など薬事法に規定された単語を使った商品説明があると、化粧品とみなされるため「化粧品製造販売許可」の取得が求められるようです。
化粧品製造販売許可を取得するには、都道府県の「薬務課」に必要書類を提出し、申請手数料を支払う必要があります。(とはいえ個人で取得するにはハードルが高いです)
その後、事務所の訪問調査などを実施し、審査を受けてから許可を取得するという流れです。くわしくは下記の記事をご確認ください。
お酒のネット販売に必要な許可や資格
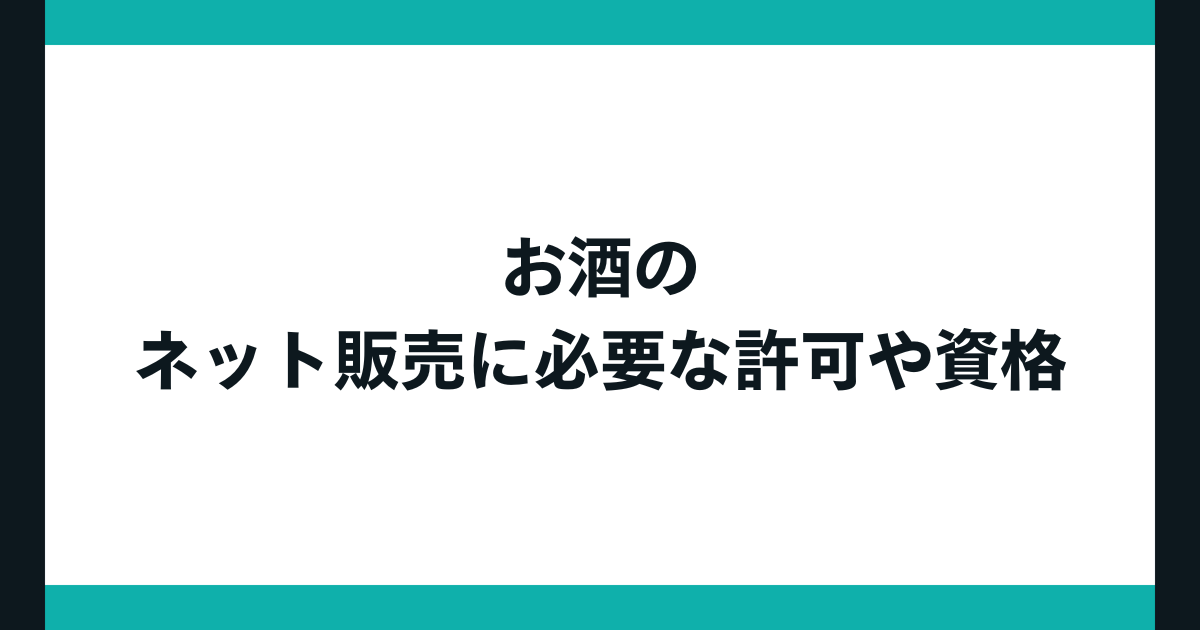
お酒は、自分で製造する場合はもちろんのこと、未開封のお酒を仕入れて販売するだけでも許可(免許)が必要です。
ネット通販の場合も例外ではありません。「通信販売酒類小売業免許」というものが必要となります。
「通信販売酒類小売業免許」を取得する手続きは、税務署の管轄です。くわしくは下記の記事をご確認ください。
なお「通信販売種類小売業免許」の取得には、蔵元に書類を用意してもらう必要があるなど、準備期間も必要です。
実現可能なのかどうか含めてしっかりと事前に確認しておきましょう。
農産物(加工食品)のネット販売に必要な許可や資格
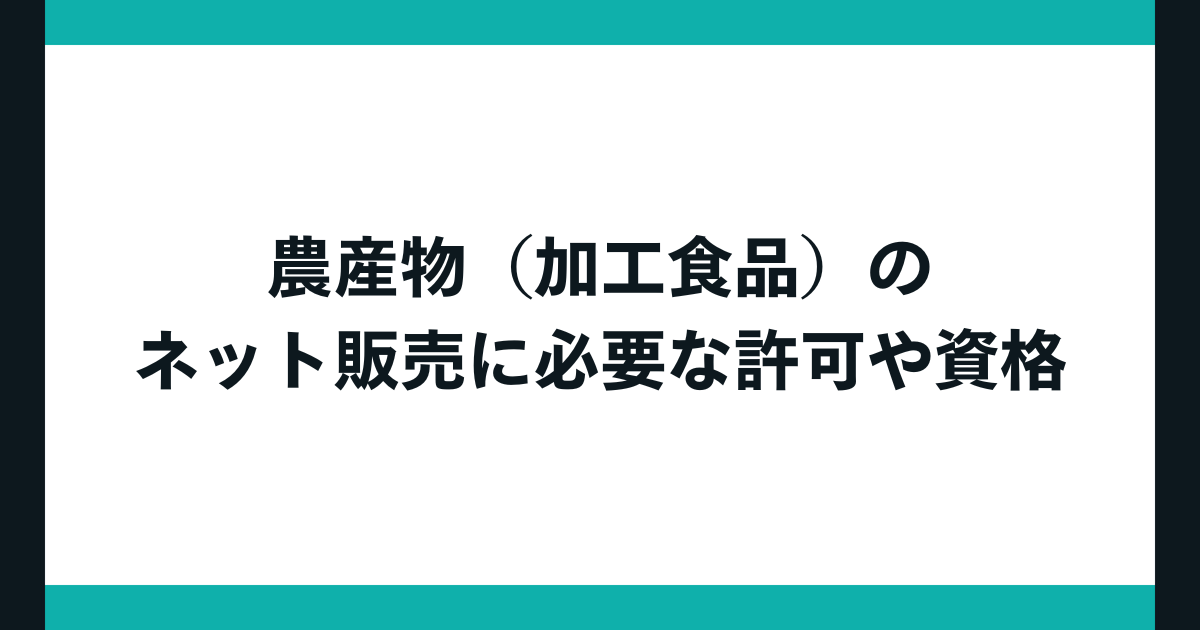
農産物を加工せず、そのまま販売する場合には、許可や資格は必要ありません。
ただし農産物を漬物やジャムなどに加工して販売する場合には、許可が必要になる場合があります。くわしくはこのあと記載している「加工食品」の項目を参照してください。
※たとえば野菜ジュースや漬物などに加工して販売するさいは、食品衛生法に基づく許可が必要。
とはいえ加工品であっても、自分で加工するのではなく、すでに加工されていてパッケージ済みの商品を販売する場合には、許可を取る必要はないとされています。
魚のネット販売に必要な許可や資格
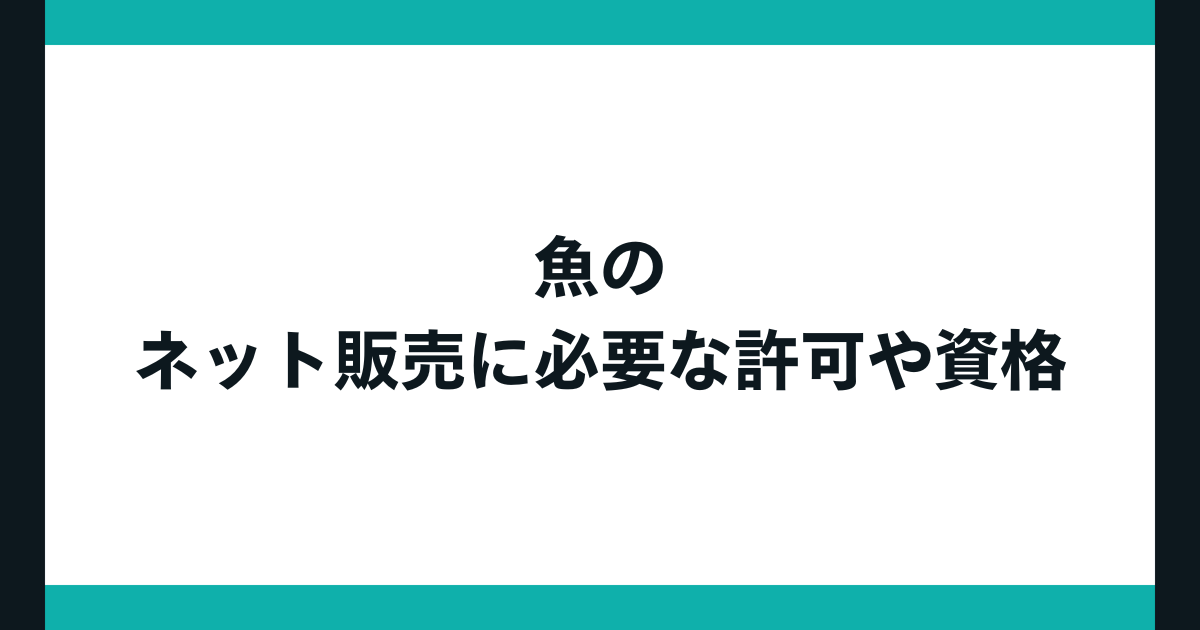
魚の販売に関しては基本的に食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
ただし、一口に魚介類の販売といっても、鮮魚なのか加工したものなのか、など、その販売形態によって「魚介類販売業」「魚介類加工業」「食品の冷凍または冷蔵業」「そうざい製造業」など必要な許可が異なってきます。
そのため、まずは管轄の保健所にご相談いただくことをおすすめします。
加工食品のネット販売に必要な許可や資格
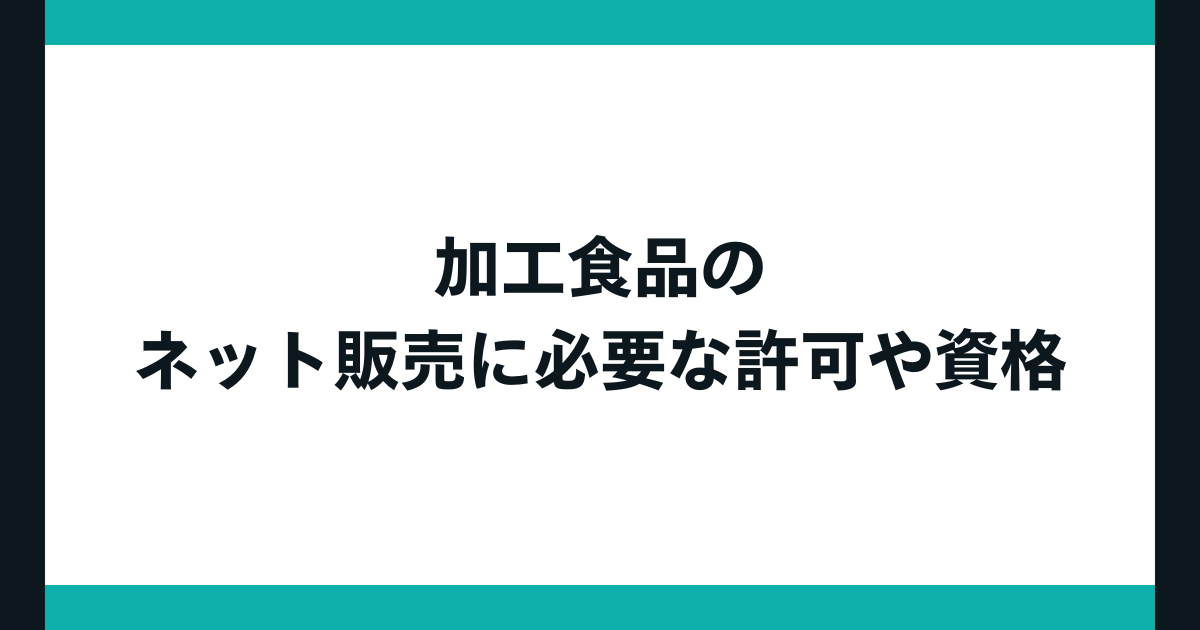
加工食品のネット販売に関しては基本的に、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。営業許可が必要となる業種は下記の35種あり、商材に応じて許可が異なります。
|
大分類 |
小分類 |
|---|---|
|
製造・加工業 |
菓子製造業 |
|
販売業 |
乳類販売業 |
|
調理業 |
飲食店営業 |
|
運搬・保管業 |
集乳業 |
また食品衛生法に基づく営業許可の取得には食品衛生責任者を1名設置することが義務づけられているので、その点も注意が必要です。
くわしい内容は下記の記事で解説していますのでご確認ください。
ここではさらに深掘りして「手作りスイーツ」「ジャム」「ドレッシング」「お茶」の場合について解説します。
手作りスイーツのネット販売に必要な許可や資格
スイーツの種類によって必要な資格が異なることがありますが、基本的に食品衛生法に基づく営業許可の中でも「菓子製造業営業許可」が必要とされます。許可の取得のためには「食品衛生責任者」も必要となります。
くわしくは管轄の保健所にお問い合わせください。
手作りジャムのネット販売に必要な許可や資格について
手作りジャムについては都道府県ごとに対応が異なりますが、東京都の場合には「製菓材料等製造業」の許可を取得することが求められています。
ジャムは都道府県によって扱いが大きく異なることがあり、届け出が不要な場合もあります。
ジャムについては下記の記事でくわしく解説していますのでご確認ください。
ドレッシングのネット販売に必要な許可や資格について
手作りのドレッシングを販売する場合、住所を管轄する保健所によって扱いが異なることがありますが、多くの場合「かん詰又はびん詰食品製造業」の許可が必要です。
すでに飲食店を経営していて、ショップで出していたドレッシングのネット販売を始めるという場合でも、改めて許可が必要になることが多いので注意しましょう。
かん詰又はびん詰食品製造業の許可を取得するには、管轄する「保健所」に届け出をします。
お茶のネット販売に必要な許可や資格について
オリジナルのお茶ではなく、すでに包装済みのお茶を販売するだけなら、許可を取る必要はないとされています。
コーヒーやスナック菓子など、すでに梱包されている商品を、開封したり表示を変えたりせずに、そのまま販売するだけなら、基本的に許可は不要とされる場合が多いので覚えておきましょう。
ただし、詰め替えやパック包装で販売する場合は、加工食品の扱いになり許可が必要になるケースもありますので、管轄の保健所に確認するようにしましょう。
サプリメント・健康食品のネット販売に必要な許可や資格
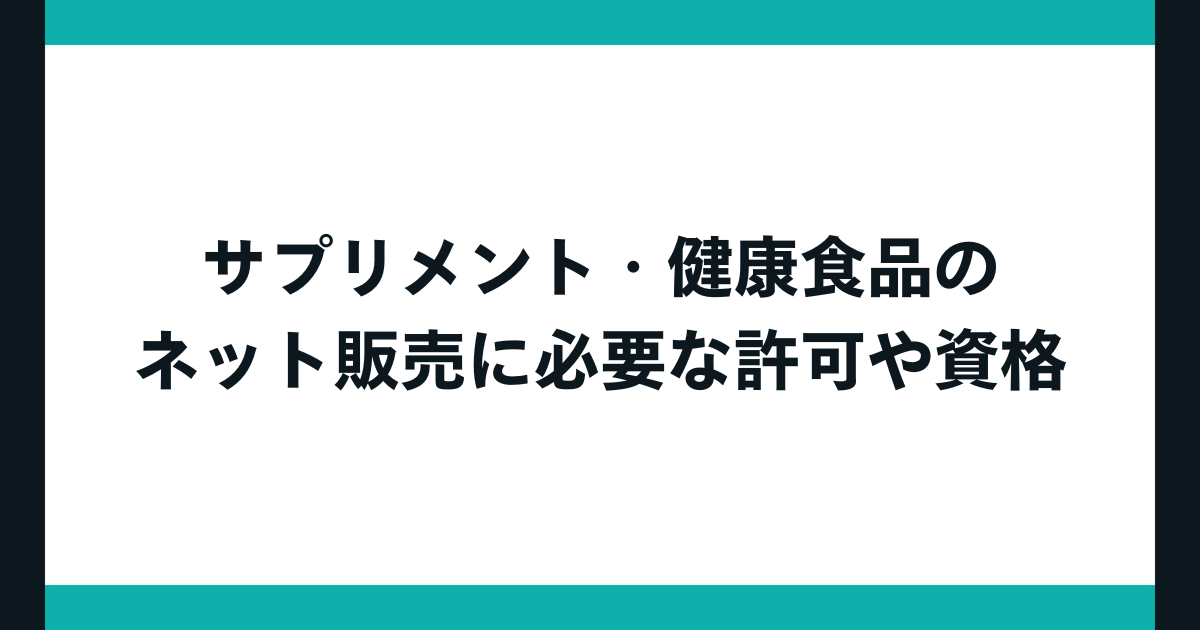
健康効果をアピールするサプリメントや健康食品などをネット販売する場合、食品衛生法、医薬品医療機器等法、薬機法などの法律が関わってきます。
オリジナル商品を扱う場合は、消費者の健康被害を防ぐために、形状に応じた製造許可の取得が必要です。自社で製造する場合や、OEMを実施する場合には、事前に確認しておきましょう。
- ソフトカプセル・CBDオイルなど:食用油脂製造業
- 粉末・顆粒・錠剤・カプセルタイプ:粉末食品製造業
- 液体・ドリンクタイプ:清涼飲料水製造業
- グミや飴、クッキー、バー、ゼリー、チョコレートなどのお菓子タイプ:菓子製造業
- 乳酸菌飲料や乳製品など:食品等販売業
ただし、これらの許可を得たとしても、厚生労働省の医薬品リストに掲載されている成分をオリジナル商品に使用することは禁じられています。
サプリや健康食品に使用できる非医薬品リストも掲載されているため、商品の企画や仕入先の検討時によく確認しておきましょう。
※参考:医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト
輸入品のサプリメント・健康食品を販売する場合
海外から仕入れたサプリメント・健康食品を扱う場合は、厚生労働大臣へ届出が必要です。
事前に検疫所の輸入食品監視担当窓口に相談し、サプリメント・健康食品の原材料に医薬品成分に該当するものが含まれていないかどうか確認してください。
その後、輸入届出関係書類を検疫所に届出をし、必要に応じて審査を受けるという流れで販売が許可されます。
海外からの仕入れで発生する税金
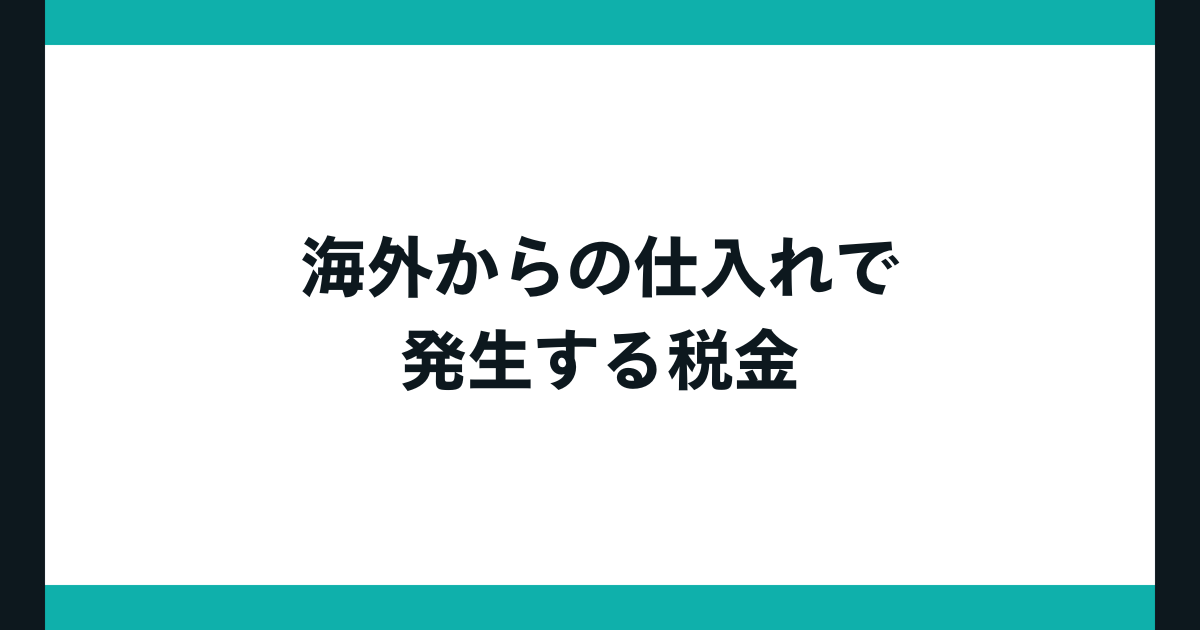
商品や資材などを海外から仕入れる場合、品目によっては関税が課されることがあります。
関税が課される品目や税率は、国によって変わってくるため要注意です。税関のHPには、税率の目安が次のように記載されています。
|
品目 |
関税率 |
|
|
衣料品 |
毛皮のコート |
20% |
|
繊維製のコート、ジャケット、 |
8.4~12.8% |
|
|
シャツ、肌着 |
7.4~10.9% |
|
|
水着 |
8.4~10.9% |
|
|
ネクタイ(織物) |
8.4~13.4% |
|
|
マフラー類 |
4.4~9.1% |
|
|
飲料 |
茶葉(ウーロン茶、紅茶) |
3~17% |
|
コーヒー豆 |
無税~12% |
|
|
ミネラルウォーター |
3% |
|
|
清涼飲料水 |
9.6~13.4% |
|
|
菓子類 |
チョコレート菓子 |
10% |
|
砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含む) |
24~25% |
|
|
クッキー、ビスケット |
13~20.4% |
|
|
アイスクリーム |
21~29.8% |
|
|
食品 |
チーズ |
22.4~40% |
|
ソーセージ |
10% |
|
|
魚類缶詰 |
9.60% |
|
|
かに缶詰 |
5% |
|
※参考:1204 主な商品の関税率の目安(カスタムスアンサー)|税関 Japan Customs
ネット販売には「特定商取引法」の理解が必須
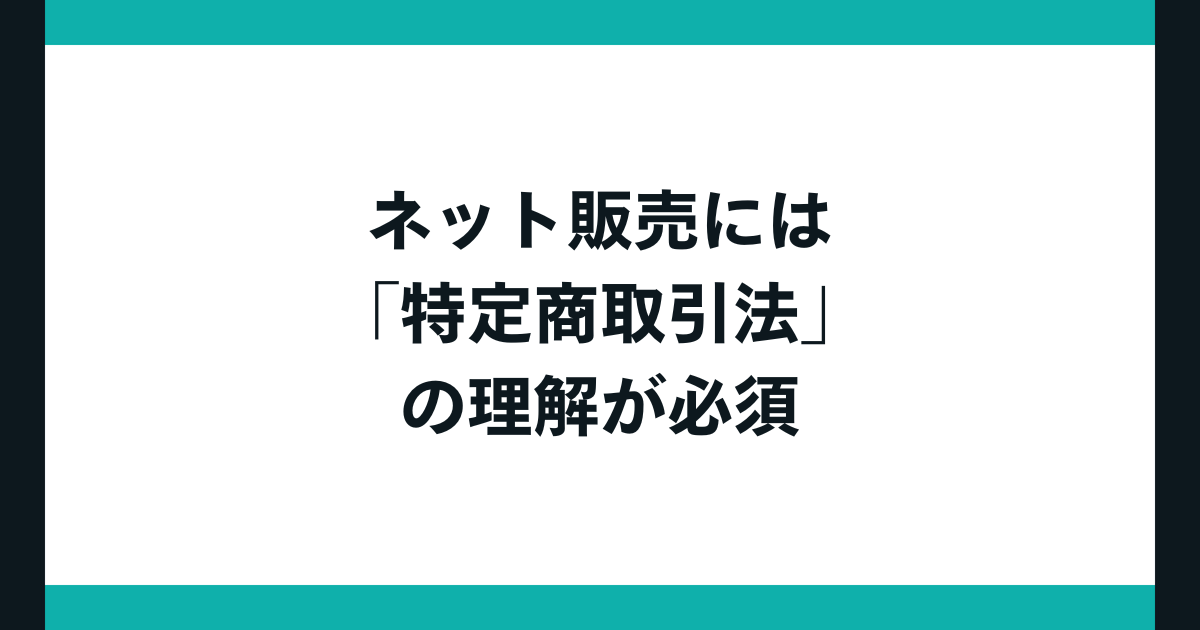
「特定商取引法」とは、消費者トラブルを防止するための法律です。
悪質な勧誘や実際の商品とは異なる誇大表現を防止するための規定が定められています。
たとえば、一度契約しても一定期間内であれば解除できる「クーリングオフ制度」も、特定商取引法によるものです。
ネット販売では、この特定商取引法により「特定商取引法に基づく表示」が必須となっています。
「特定商取引法に基づく表示」に必要な事項
ネットショップでは、以下の14項目の表示が必要です。
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払い時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 申込みの有効期限があるときには、その期限
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
- 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
引用:特定商取引法ガイド
このうちネットショップオーナーにとってとくに重要なのが、次の5つです。
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 販売価格、送料
- 代金の支払方法
- 支払い時期・商品の引渡時期
- 返品特約・瑕疵担保責任
それぞれ詳しく紹介します。
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
ネットショップ上に、事業者の氏名、住所、電話番号などを表示することが義務づけられています。表示しないとペナルティの対象となり、「業務改善の指示」「業務停止命令」「業務禁止命令」などの行政処分が課される可能性があります。
一方で、個人がかんたんにネットショップを開業できるようになった現在では、自宅を利用してネットショップを運営する人も増えました。その場合、本名や自宅の住所などの個人情報を公開せざるをえなくなり、悪用されるリスクがあります。
そうした不安を解消するために、ネットショップ作成サービスの「BASE」では、運営会社であるBASE株式会社の所在地・連絡先を表示できる機能を提供しています。そのため、個人情報を非公開にしたままネットショップを運営可能です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
販売価格、送料
ネットショップ内で価格は税込で表記し、送料も具体的な金額を記載することが義務づけられています。
送料は配送会社が同じでも、重さや地域によって変わってくるため、商品点数が多いショップでは商品を登録するたびに計算しなければいけないことになるでしょう。
そこで便利なのが、BASEの「かんたん配送(ヤマト運輸連携)」です。配送料が全国一律になるため、送料の表記に困りません。
代金の支払方法
特定商取引法により、ネットショップで利用できる決済手段を記載しなければいけません。注文画面に進まなくても決済方法がわかるように、ショップに導入している決済手段を明記しておきましょう。
なお、BASEでは次の7つの決済手段に対応しています。
- コンビニ(Pay-easy)決済
- 銀行振込決済
- クレジットカード決済
- あと払い(Pay ID)
- キャリア決済
- PayPal決済
- Amazon Pay
支払い時期・商品の引渡時期
注文から支払いまでの日数や、発送までにかかる日数などを明記してください。配送手段とともに商品ページに記載するとわかりやすいでしょう。
BASEでは、地域ごとのお届け日を自動で表示する「配送日設定 App」があります。顧客が自分の都合にあわせて商品到着日を変更するためにも使えますので、ぜひ活用してみてください。
返品特約・瑕疵担保責任
注文のキャンセルや、配送後の返品・返金対応についての規定を明記するよう定められています。
特定商取引法では、商品に欠陥があった場合は返品(クーリング・オフ)に応じなければいけません。このことを瑕疵担保責任と呼びます。
瑕疵担保責任について明記することを返品特約と言い、ネットショップ内に明記するよう義務づけられています。
瑕疵担保責任の範囲内でのみ返品を受付する場合は、「商品に欠陥がある場合を除き、基本的には返品には応じていません」といった文言を記載すれば大丈夫です。
ネットショップ開設時に必要な「開業届」
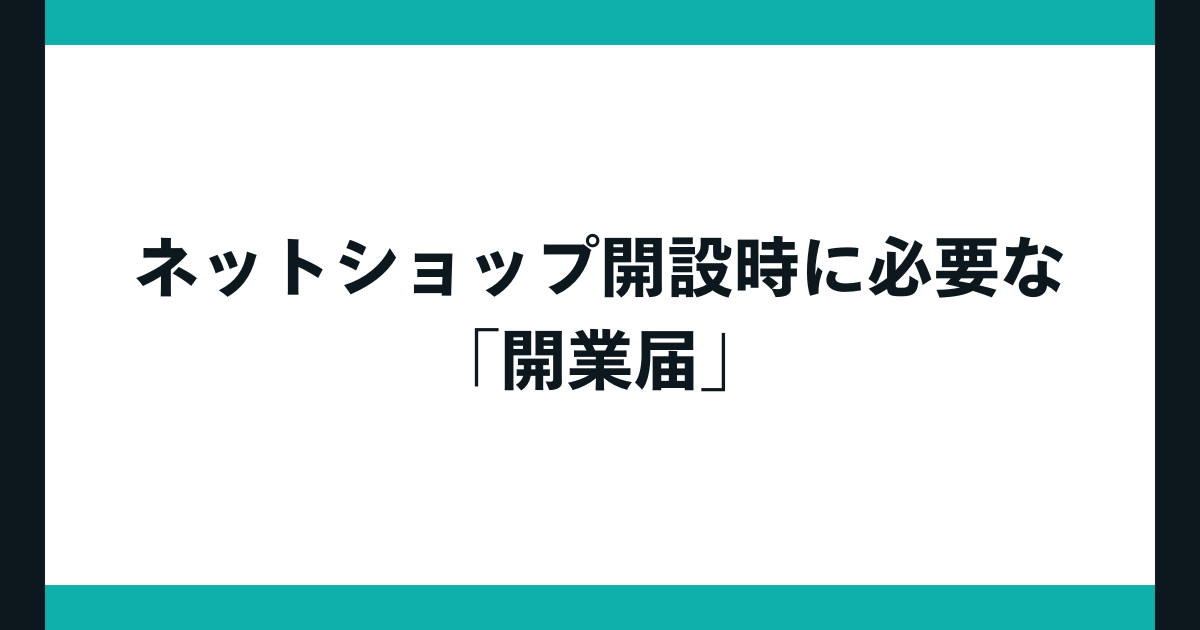
個人事業主としてネットショップを運営する場合、開業時に開業届を提出することでメリットを受けられます。
ただし、開業届はネット販売に必須なものではないため、メリットとデメリットをふまえて届出をするか決めるといいでしょう。
開業届を出すメリット
- 確定申告で青色申告が利用できる
- 利用できるネットショップ作成サービスの幅が広がる(楽天市場など)
- 保育園や融資の申請に利用できる
- 小規模企業共済制度に加入できる
開業届を出すデメリット
- 簿記の記録方法が複雑(複式簿記)
- 収益によっては税負担が重くなる
- 退職時に失業保険が受け取れない
開業届の提出方法
開業届を提出する場合、届出書(個人事業の開業・廃業等届出書)を税務署に持参します。
届出書のフォーマットは国税庁のHPからダウンロード可能です。以下のリンクからダウンロードしてみてください。
ネット販売の許可・資格に関するよくある質問
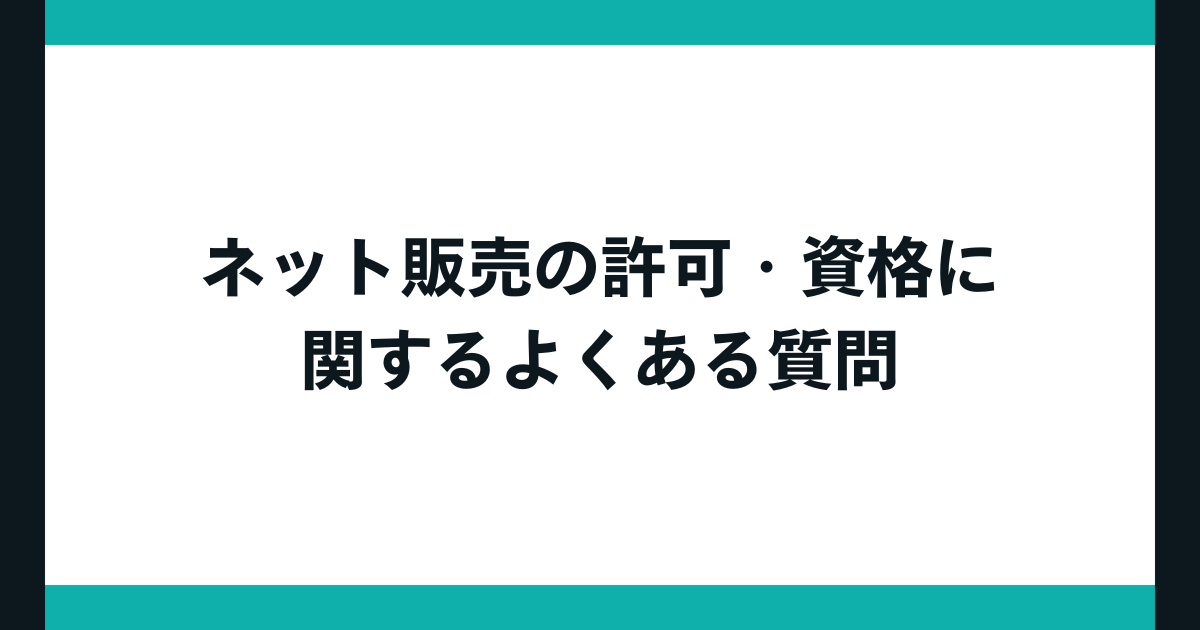
ネット販売に必要な許可・資格についての疑問にお答えします。
ネット販売ができないものはあるの?
犬や猫、不動産などのネット販売は法律で禁じられています。また、利用するプラットフォームごとに取り扱えない商品が異なりますので、規約を確認してみてください。
▶関連記事:販売不可・登録禁止の商品はありますか ヘルプ | BASE
自分で作ったものを売る場合に必要な資格は?
販売する品目によって必要な資格・許可が変わってきます。
■ハンドメイド雑貨・アクセサリー
許可は不要です。ただし、中古の材料を使用する場合は、古物商許可申請が必要なのでご注意ください。
■手作りの加工食品
・手作りスイーツ:菓子製造業営業許可、食品衛生責任者
・手作りジャム:都道府県によって異なる(製菓材料等製造業)
食品販売に必要な営業許可について詳しくは、厚生労働省のHPを確認してみてください。
参考:営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報|厚生労働省
■農業・漁業・畜産業を営む企業が販売する場合
・魚介類:魚介類販売業
・食肉:食肉販売業
・野菜・果物:野菜果物販売業
・米・豆類など:米穀類販売業
まとめ
以上、ネットショップの販売に必要な許可や資格についてまとめました。
ネットショップではさまざまな物を販売することができますが、食品や化粧品のように身体に影響を与える商品は、許可が必要なケースが多くなっています。
また、商品のジャンルを問わず、ネットショップを運営する際は特定商取引法に基づく表示が欠かせません。顧客のためにも、自分自身のためにも、しっかりと許可や資格について確認して、ネットショップ運営にチャレンジしてみてください。
BASEでは、特定商取引法に基づく表示を義務づけるために事業者情報の入力を必須に設定していますが、個人で運営する場合は住所と電話番号のみ非開示にすることも可能です。
また、取り扱える商品の幅も広いため、必要な許可・資格を取得するとさまざまなジャンルのネットショップを開設できることも魅力です。ネットショップ開設時の手間も最小限に抑えられるため、許可や資格の取得に専念できるでしょう。
ネットショップの開設を検討中の方は、ぜひBASEをご検討ください。
売れるお店を作る機能とサポートが豊富
BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。
ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。
また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。
プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。
さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。
ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。
個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。