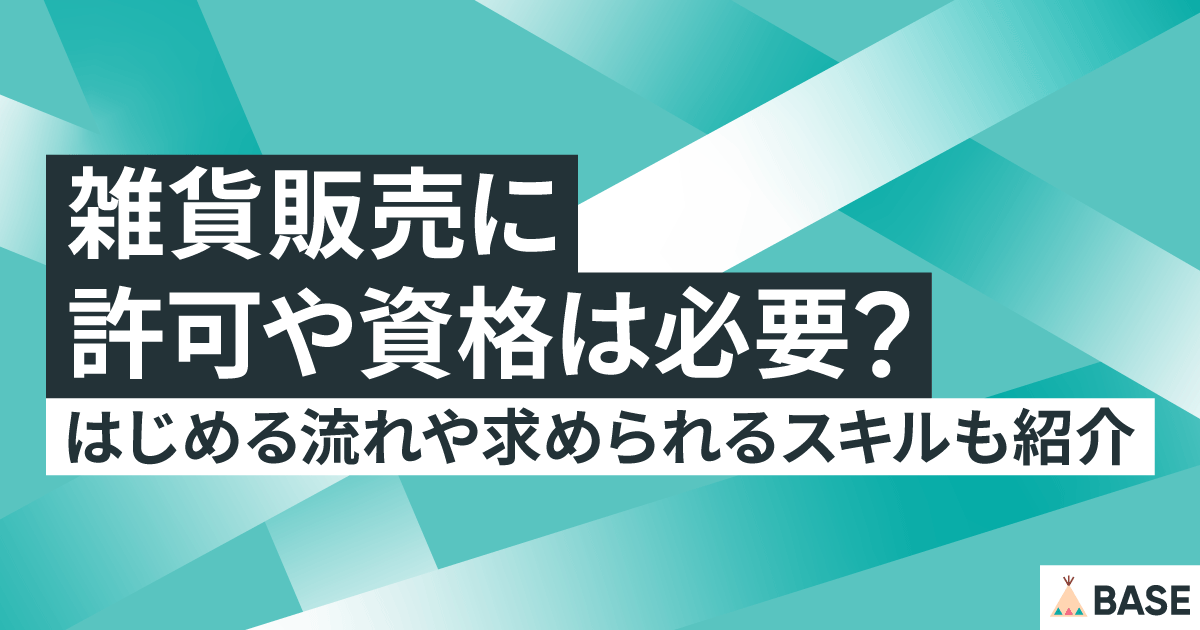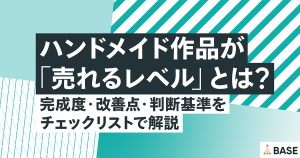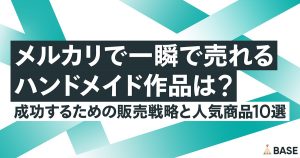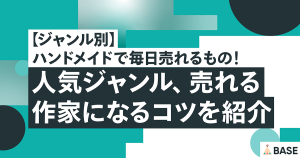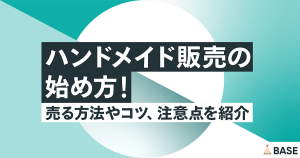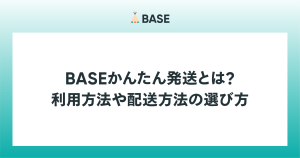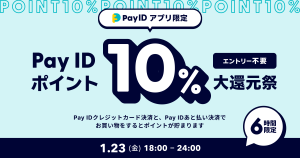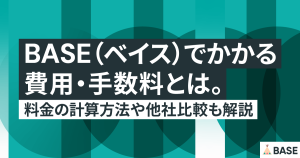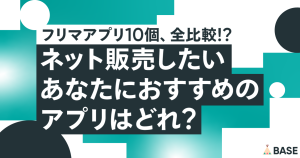実店舗であれネット販売であれ、これから雑貨販売をはじめたい時に「許可や資格は必要?」「求められるスキルや開業資金の目安は?」と不安な方は多いと思います。実際、雑貨販売においては、販売するものによって必要な許可や資格が異なるため注意が必要です。
そこでこの記事では、雑貨販売に必要な許可や資格、雑貨店を開業する流れ、求められるスキルや資金目安などについて解説していきます。
雑貨店の成功事例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
【開設実績7年連続No.1】のBASE(ベイス)にお任せ
- BASEは個人・スモールチームに選ばれているネットショップ作成サービスです
- 初期費用・月額費用いらずで、無料で今日からショップ運営をはじめられます
- ショップ開設後の運営サポートや集客支援も充実しています
- 「売上を伸ばしやすいネットショップ作成サービスNo.1」に選ばれています
雑貨販売をはじめるのに許可は必要?
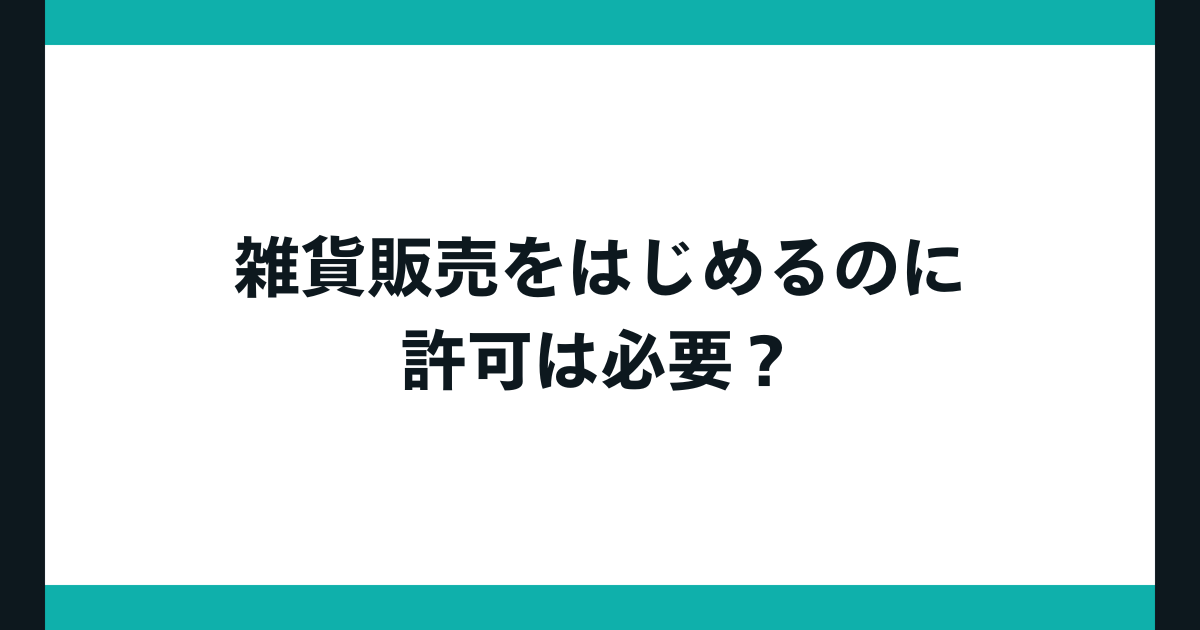
冒頭でもお伝えした通り、扱う商品の種類や販売方法によっては許可が必要となります。(必要ないものもあります)許可を取らない状態で販売を開始してしまうと違法となり、罰金が課せられる可能性も。
場合によっては、申請から取得までに時間を要するものもあるため、開業前にしっかりと情報収集を行い、準備を進めていく必要があります。
以下の5つのパターンに分けて解説していきます。
- アンティーク雑貨、中古本や古着などを扱う場合
- 雑貨店でカフェを出す場合
- パン、クッキーなどを出す場合
- 輸入品を販売したい場合
- 洋服を扱う場合
アンティーク雑貨、中古本や古着などを扱う場合
アンティーク雑貨や中古本、古着を扱う場合は、「古物商許可申請」が必要です。
新品未開封品であっても、一回取引が行われたものは「古物」になります。この部分を知らずに「アンティーク雑貨ではないから」と、未申請で販売をはじめてしまうと違法となるため注意が必要です。
アンティーク雑貨は、愛好家であれば一般的には高額であっても買いたい人が多いので、全国の人に商売できるネットショップとの相性が非常に良いと思われます。
「古物商許可」の申請方法
古物商許可は各都道府県の公安委員会に申請しますが、実際には所轄の警察の生活安全課に書類を提出することになります。
最寄りの警察署に行けばいいというわけではなく、必ずご自身のショップや営業拠点のある場所を管轄する警察署に足を運ぶようにしましょう。
県警などに電話で問い合わせて、古物の販売を行うショップの所在地を伝えれば、管轄の警察署の住所や電話番号を教えてもらえます。
申請方法に関しては、所轄の警察署へ足を運べば申請に必要な用紙一式を受け取ることが可能です。事前に電話予約をした方がスムーズです。このさい、申請について不明点があれば、聞いておくとよいでしょう。
ちなみに申請用紙については、インターネットからダウンロードすることもできます。ただし古物商許可申請は、場合によって必要な書類が変わることもありますので、実際に相談しながら準備を進めることをおすすめします。
なお申請の処理にかかる期間としては、一般的に約40日(行政庁の休日は含まない)となっていますので、時間には余裕を持って申請しましょう。
雑貨店でカフェを出す場合
自分でセレクトした雑貨を見てもらったり、雑貨を購入したあと併設のカフェスペースでゆっくりしてもらったりしたい、とカフェを出すケースもあるかもしれません。
カフェを出す場合は飲食物の提供になるため、飲食店営業許可が必要となります。
飲食店営業許可の取得方法
飲食店営業許可を申請には、「人的要件」と「設備要件」を満たした上で申請する必要があります。
人的要件について
人的要件として、「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が実施している講習を受講することで取得できます。
こちらの東京都福祉保健局のページにくわしい説明などが記載されているので、ご確認ください。
加えてカフェの規模が収容人数30人を超える場合、「防火管理者」の資格も必要になるためご注意ください。
設備要件について
設備要件を満たすには、製造場所(キッチン)の図面が必要となります。キッチンや空調設備、食器棚、食品の保管場所など、店舗設備に関わる細かい規制が設けられています。
図面は、事前に設計士と一緒に管轄の保健所に行き相談を受けておくとスムーズです。店舗の図面が完成したら、上述の食品衛生責任者の証明書と申請書類をあわせて保健所に提出します。
パン、クッキーなどを提供する場合
雑貨の他にパンやクッキーなどを出したりネットで販売したりする場合は「菓子製造業許可」が必要です。菓子製造業許可を取得しておけば、パンやクッキーのほかにケーキ、餅菓子、飴菓子、干菓子などを製造販売することが可能です。
ただ実店舗でパンやクッキーなどを提供する場合、「カフェ」として扱われる場合もありますので、まずは保健所に相談してみましょう。
菓子製造業許可の取得方法
菓子製造業許可申請については、ショップを所轄する保健所に相談します。施設基準を満たしているかどうかを前もって確認するために、工事着工前に図面などを持参して保健所の食品衛生担当へ相談しましょう。
また食品を扱いますので、きちんと衛生的な管理運営を行わなくてはなりません。そのために「食品衛生責任者」の設置も必要です。
くわしくは下記の記事で解説していますので、ご確認ください。
輸入雑貨を販売したい場合
雑貨を輸入して販売するさいには「古物商の許可」が関わってきます。古物商は基本的に国内の取引を対象としているため、海外から仕入れる場合は必要ないとされています。
ただし、第三者が輸入し、それを国内で仕入れる場合などは古物商が必要だったりと判断が難しいのが現状です。そのため、不安な場合は所轄の警察署の生活安全課に相談してみることをおすすめします。
化粧品などの輸入は注意
海外から輸入した化粧品を販売する場合は、仕入れ方法によって、許可が必要なケースとそうでないケースがあります。
「化粧品製造販売業」を取得している問屋や輸入販売会社から仕入れた化粧品を、販売だけするのであれば、「化粧品製造販売業」の許可は不要とされています。
ただし、輸入方法によっては、やはり許可が必要になる場合もあるため、くわしくは所轄の都道府県薬務主管課に相談しましょう。
化粧品の販売に関しては下記の記事も参考にしてみてください。
洋服を販売したい場合
古着ではない新品の洋服を販売する場合は、とくに営業許可や資格は不要ですが、「家庭用品品質表示表」に基づいた表示が必要となります。
洋服に使われている繊維の名称やその混合率、表示者名、連絡先、洗濯方法などを表示しなければなりません。
とはいえ日本国内で仕入れる場合は、仕入れた時点で品質表示のタグはつけられている場合がほとんどだと思われます。
家庭用品品質表示表については、消費者庁が取り締まっています。洋服を販売するにあたって不明点などがあれば、消費者庁の公式ホームページを確認したり実際に問い合わせてみましょう。
※参考:家庭用品品質表示法|消費者庁
雑貨販売をはじめる流れ
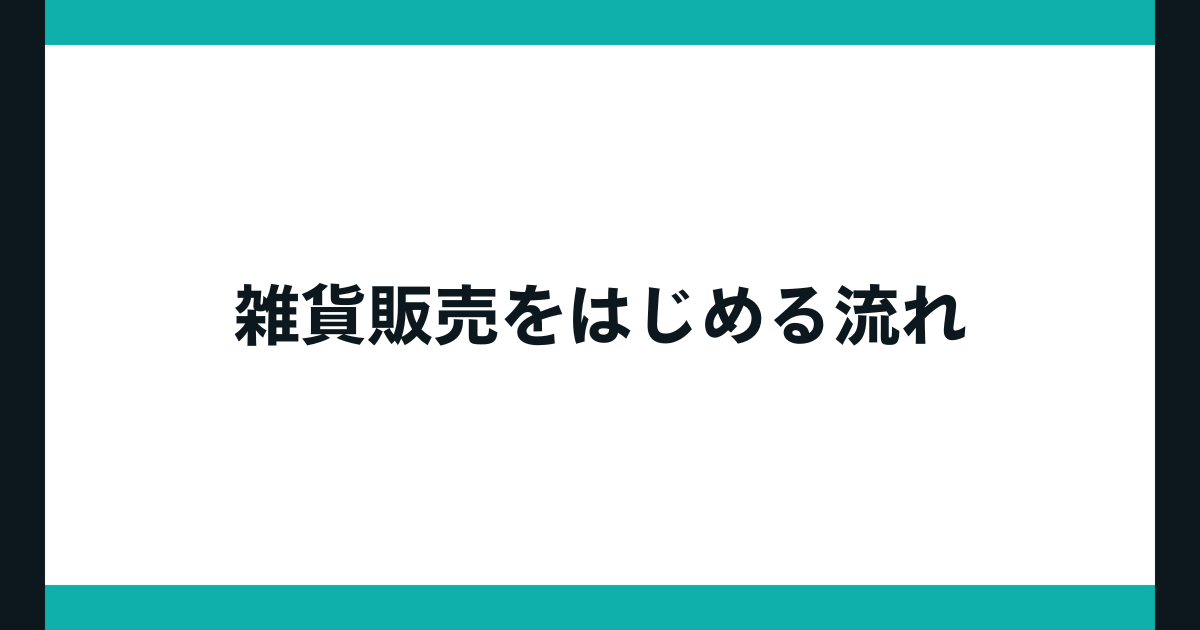
雑貨の販売をはじめるために、必要な工程は次の通りです。
- コンセプトを決める
- 商品を準備する
- ショップの開業方法を決める
- 開業に必要な許可・手続きを行う
- 集客する
それぞれ紹介していきます。
コンセプトを決める
まずは、雑貨店としてのコンセプトを決めることが大切です。ターゲットを明確にした上で、こだわりたい部分を決めていくことで、他の雑貨店との差別化要素が浮かび上がるでしょう。
たとえば、「自分好みの雑貨を集めてショップを開きたい!」という場合、自分の好みを深堀りしていきます。白やベージュ、パステルカラーを基調としたガーリーな雑貨であれば、韓国風のテイストが好きな若年層の女性と相性がいいでしょう。
ただし、韓国風雑貨は流行しているからこそ、競合も数多くいます。そうした場合には、商品自体だけでなく、販売方法で個性を出すのもおすすめです。
もし友達へのギフトとして贈りやすい低価格な雑貨を揃えて、セット販売や梱包サービスを充実させれば、それにより独自性をアピールできます。
このように、ターゲットやコンセプトを明確にした上で、扱う商品や販売方法への落とし込み方を探っていきましょう。
商品を準備する
販売する雑貨を用意する方法は、次の5つです。
- 卸売業者・卸サイトから仕入れる
問屋街にある実店舗や、卸価格で仕入れられるサイトなどを活用して仕入れる方法です。仕入れ価格を抑えやすい一方で、他のショップと商品が被りやすいことが懸念されます。
- 海外から仕入れる
海外の問屋街やブランドショップで買い付けした商品を販売する方法もあります。国内の卸売業者から仕入れるよりも商品の希少性が高まりますが、自分で足を運ぶ場合はその分コストも必要です。そうしたコストや手間を削減する方法として、海外の買い付け代行サービスを活用するという選択肢もあります。
- OEMを利用する
OEM(Original Equipment Manufacturing)とは、製造ラインを持つ企業が他社ブランドの商品の製造を受託するビジネスです。設備投資の負担なく、専門スタッフのサポートを受けながらオリジナル商品を作れます。
- ハンドメイドする
ハンドメイドした雑貨を商品として販売する方法です。個人で雑貨をハンドメイドする場合は販売数が限られてしまうものの、趣味を活かした副業として自分のペースで進められることは魅力でしょう。
- 作家やブランドと交渉して仕入れる
コンセプトにあった雑貨を作るブランドと直接交渉して、仕入れる方法もあります。仕入れ価格や数などを提案して交渉することになります。作家やブランドにとっては大事な商品を託すことになるため、ある程度の販売実績を持った上で交渉するのが望ましいでしょう。
おすすめの仕入れサイト
おしゃれな雑貨が揃うおすすめの仕入れサイトを紹介します。仕入れ商品を扱う予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。
- スーパーデリバリー
インテリア雑貨や生活雑貨をはじめ、アパレル、食品、電化製品など幅広いジャンルを扱う卸サイトです。ネットショップ作成サービスの「BASE」と連携した仕入れサイト スーパーデリバリー Appを活用すると、仕入れた商品のデータをBASEの管理画面に自動で反映できるため、商品登録の手間を大幅に削減できます。 - 自由が丘マーケットプレイス
雑貨専門の卸サイトで、アロマやバス用品、インテリア、キッチン雑貨、ファッション小物などさまざまな商品が集まっています。ただし、会員登録できるのは法人のみで、個人は利用できない点には注意してください。 - ザッカネット
名前の通り雑貨を中心とした総合卸サイトです。ペットグッズやシニア向け商品、ベビー用品など特定のターゲットに向けた商品にも力を入れています。また、既製品にロゴやオリジナルデザインを印刷する、オンデマンドサービスつきの商品を扱っていることも特徴です。
- shesay(志成販売)
大阪発祥の貿易会社・志成販売のオリジナルブランド「shesay(シセイ)」の商品を扱う卸サイトです。環境に優しい原料を使った商品や、職人の手作りならではの風あいを大切にした商品を取り揃えています。楽天市場には個人でも利用可能なショップも設けています。
- Cmall
トレンド感のある商品を1点から仕入れが可能で、中国輸入代行サービスも提供する卸サイトです。中国輸入代行サービスは初期費用・月額費用ともに無料で、日本語でのサポートや簡易検品などのサービスも受けられるため、はじめて輸入代行を利用する方にもぴったりでしょう。
- 淘宝網(タオバオ)
タオバオは、アリババ・グループが運営する中国有数の巨大ECモールです。日本語の対応はしていないため利用ハードルは高いものの、代行サービスを利用すればかんたんに仕入れられます。
BASEでもタオバオの輸入代行サービス「タオバオ新幹線」と連携しています。タオバオ新幹線 Appでは、たったの月額500円で、商品情報の連携や、顧客への発送代行などのサービスを受けられますので、ぜひ活用してみてください。
ショップの開業方法を決める
雑貨店の開業方法は、対面販売とネット販売に大きく分かれます。
対面販売は実店舗を持って常設販売する方法と、ポップアップストアや展示会など期間限定で販売する方法があります。実店舗を開業するには初期費用・ランニングコストともに高額になるため、個人には負担が大きいでしょう。
ネットショップの種類はさまざまですが、モール型とASP型が代表的です。ただし、はじめて雑貨店を運営する場合、開業後の業務量を予想しにくいケースも多いでしょう。
そこで、雑貨の仕入れや接客に注力するためにも、「売上を伸ばしやすいネットショップ開設サービスNo.1(※)」に選ばれたBASEのように豊富な機能をかんたんに使えるサービスを選ぶのもおすすめです。
※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)
開業に必要な許可・手続きを行う
販売する商品にあわせて、必要な許可を取得しましょう。
また、確定申告で青色申告を検討しているのであれば、開業1ヶ月以内に開業届を提出するのも忘れないようにしてください。
集客する
準備した商品を売るためには、ショップへの集客は欠かせません。
とくにネット販売の場合は実店舗のように「偶然通りがかった人が入店する」といったことがないため、積極的な集客が必要です。
集客方法には、InstagramやYouTube、TikTok、Googleのショッピング広告などさまざまな手段がありますので、予算と相談しながら複数の方法を組み合わせつつ集客していきましょう。
雑貨販売に活かせるスキル
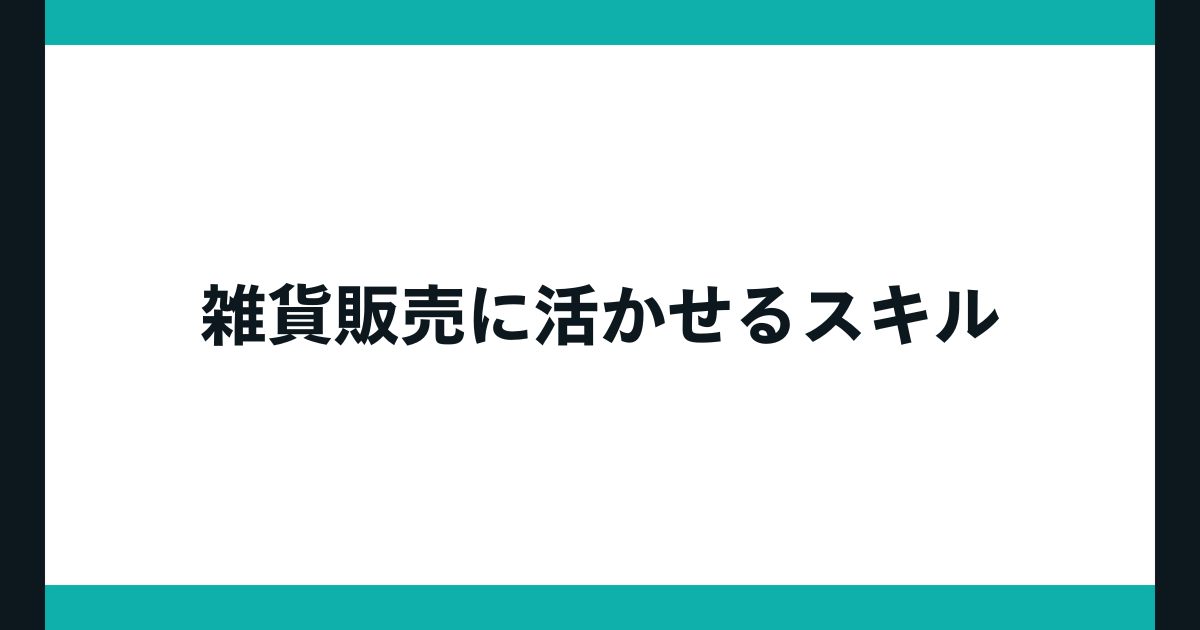
雑貨販売をはじめる上で、身につけておきたいスキルは次の4つに分けられます。
- マーケティングスキル
- 接客スキル
- 会計スキル
- デザインスキル
それぞれのスキルが雑貨販売で活きてくる場面を紹介します。
マーケティングスキル
ターゲットを見極めて適切な商品選びを実施したり、SNSや広告などの集客施策を計画・実行したりするためのスキルです。ネットショップの管理画面などからショップの状況を分析するスキルも、マーケティングスキルに含まれます。
ネットショップにおけるマーケティングについては以下の記事でくわしく紹介していますので、チェックしてみてください。
接客スキル
開業方法を問わず、接客スキルは重要です。
実店舗の場合は、来店する顧客を対面で接客するためのコミュニケーション能力が挙げられます。また、会員登録してくれた顧客に送るDMに一言手書きのメッセージを添えたりする取り組みも、接客に含まれるでしょう。
一方でネットショップでは、問い合わせメールに対応したり、リピーターに送るメルマガを作成したりする際などに接客スキルが求められます。文章スキルがそのまま接客の品質につながるため、文章力アップのための取り組みを実践してみてください。
会計スキル
会計スキルは、ショップの収益に直結します。たとえば、バランスのいい利益率を見極めて値付けをしたり、売上や経費をまとめて帳簿をつける経理業務を行ったりする場合に必要です。また、従業員を雇う場合は給与計算も必要になってきます。
最近では便利な会計ソフトが数多くリリースされていますが、会計の基礎を理解するために簿記にチャレンジするのもおすすめです。
デザインスキル
実店舗の内装や商品の配置、ネットショップのデザイン、商品写真の撮影などで求められるスキルです。雑貨はデザインセンスの問われる業種なので、顧客に商品を買ってもらうためにも重要になってきます。
デザインスキルに自信がない場合は、内装デザインを専門会社に依頼したり、Web制作会社にネットショップのデザインを委託したりするのも1つの方法です。
また、ネットショップ作成サービスによっては、デザインテンプレートを豊富に取り揃えていたり、AIを活用してデザインを自動で作成したりするサービスも備わっています。BASEでもショップデザインの提案機能を搭載したBASE AIアシスタントが備わっていますので、ぜひ活用してみてください。
雑貨店の開業にかかる費用
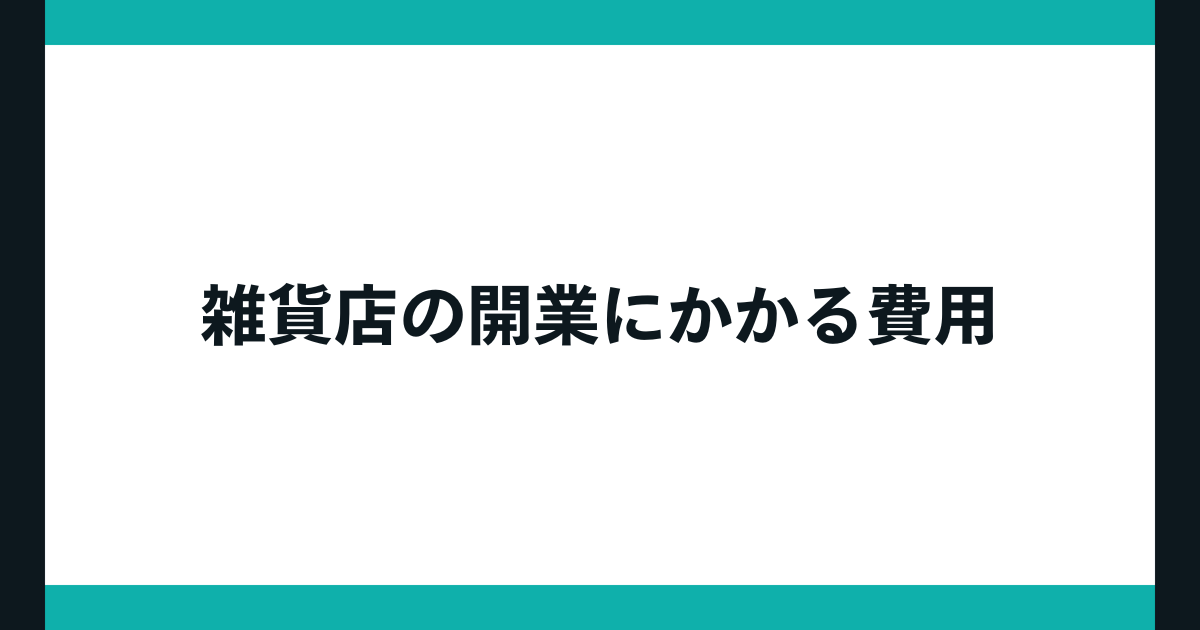
雑貨店をはじめるために必要な資金は、開業方法によって変わってきます。
実店舗の場合とネットショップの場合の資金目安は、次の通りです。
|
開業資金目安 |
初期費用 |
固定費 |
|
|
実店舗 |
400万〜1,000万円 |
物件取得費 |
家賃 |
|
ネットショップ |
10万~500万円 |
ネットショップ構築費 |
サーバー代 |
なお、ネットショップ作成サービスの「BASE」では、初期費用・月額費用ともに無料でネットショップを開設することもできます。BASEのスタンダードプランを利用した場合、以下の費用が無料です。
<BASEのスタンダードプランを利用すると0円になる費用一覧>
- 初期費用:ネットショップ構築費
- 固定費:サーバー代、ドメイン代、ソフトウエア更新費
さらに、BASEでは無料で使える機能が豊富に備わっていますので、費用を大幅に抑えられるでしょう。
▶関連記事:BASEの料金プラン・手数料
雑貨店を運営するなら実店舗とネットショップの同時運営がおすすめ
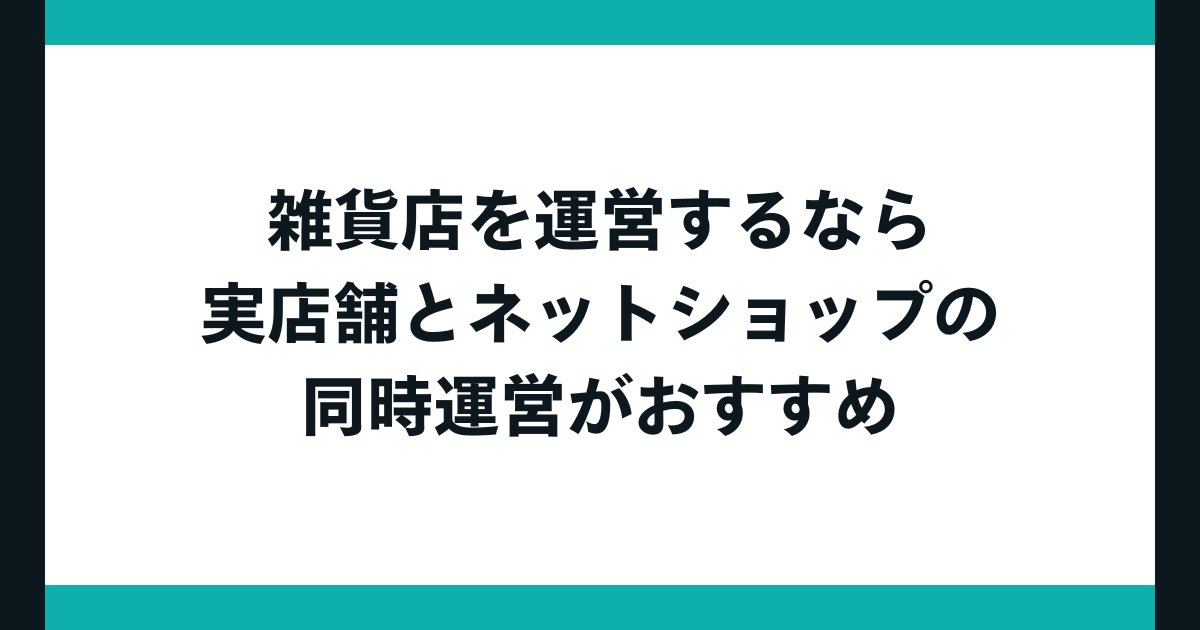
実店舗をお持ちで雑貨販売を考えている方は、実店舗だけでなくネットショップも同時に運営するのがおすすめです。
実店舗とネットショップを同時運営するメリットとしては、主に以下の2点が挙げられます。
- ECと実店舗の相乗効果が期待できる
- ネットだからこそ売れる商品がある
ネットショップと実店舗の相乗効果が期待できる
ネットショップと実店舗を同時運営することで、以下のような相乗効果が期待できます。
- 全国の顧客を対象にできる
- ネットショップをキッカケに来店や売上が増える
- 実店舗での購入者がファンになりECのお客さんも増える
BASEでネットショップを開設した雑貨店オーナー様の中には、Instagram広告を使ってネットショップで販売したところすぐに、多額の売上が上がったとの声を上がっています。このようにSNSでリーチした顧客がすぐに商品を購入できるのは、実店舗にはない魅力です。
またネットショップでショップを知った顧客が、実店舗にも来店いただけるようになったなど、相乗効果も感じているとのことでした。
ネットだからこそ売れる商品がある
実店舗では売れにくい商品も、ネットであれば売れる可能性があります。
ネットショップと実店舗で扱う商品を棲み分ければ、在庫消化の効率化につながり結果売上アップにもつながる可能性があります。
<ネットショップの特徴>
・全国の人に商品を見てもらえる
・マニアックな商品でも売れる可能性がある
・サイズの大きなものでも購入につながりやすい
ネットショップには上記のようなメリットがあり、店頭では手に取りにくいマニアックな商品やサイズの大きな商品も、ECであれば欲しいという人が見つかるかもしれません。
ネットショップでの雑貨販売の成功事例
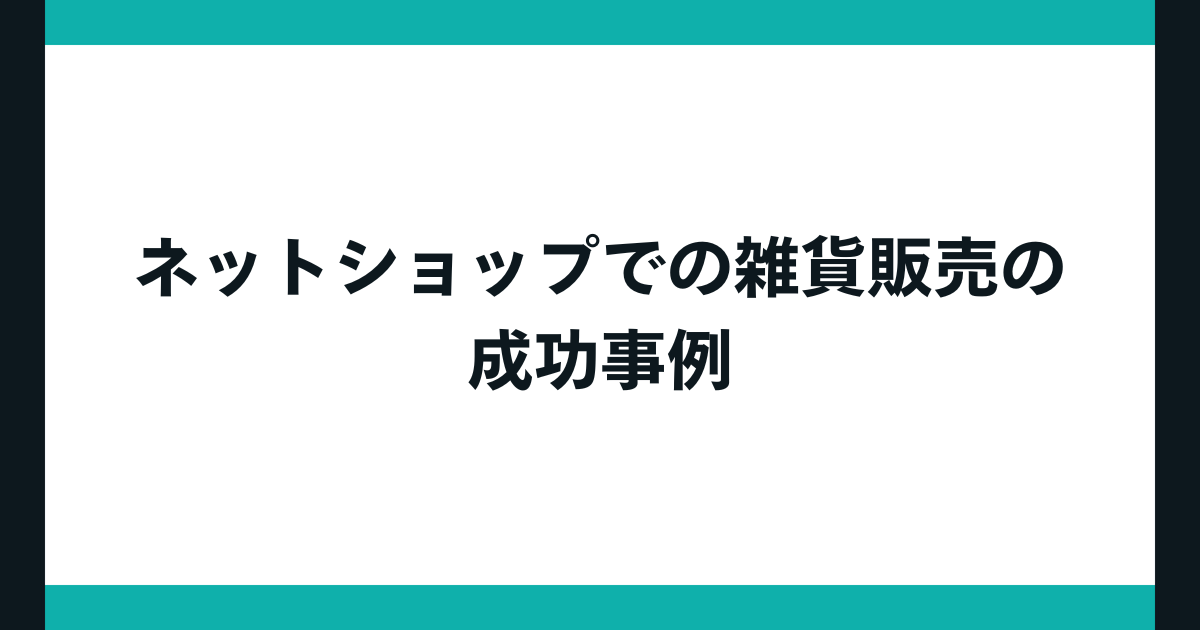
さいごに、BASEのネットショップで雑貨を販売するオーナー様の事例を3つ紹介します。
LAND(セレクト雑貨)
東京・国分寺にある、国内外から仕入れた生活雑貨、服、インテリアを扱うセレクトショップです。ネットショップも開設した当初は売上が伸び悩んでいたものの、Instagram広告をきっかけに実店舗の3倍の売上を記録するまでに成長しました。
kin.iro.hitode(オリジナル雑貨)
美大出身の作家がアート作品を身近に感じてもらうために立ち上げた、イラストを用いたオリジナル雑貨を扱うネットショップです。BASEのネットショップとハンドメイドマーケットを利用して、オンラインのみで販売しています。
Print creative(アート雑貨)
螺鈿を使ったスマホケースやミラー、名刺ケースなどを取り扱うショップです。ハンドメイドマーケットでのオンライン販売からスタートし。BASEでショップを開設し、現在はポップアップイベントにも多数出店しています。
【オーナーズインタビュー/天然貝のキラキラ螺鈿アート雑貨 Print creative 】オススメBASE Apps活用術
まとめ
雑貨店の運営に必要な許可や資格について解説しました。雑貨店では販売するものによって、必要な許可や資格が変わってきます。基本的に「人体に何らかの影響があるもの」は許可や資格が必要だと考えておきましょう。不安な場合はまず各都道府県の然るべき場所に相談することをおすすめします。
また、雑貨販売をはじめるなら、実店舗とネットショップを両立するのがおすすめです。ネットショップ作成サービスの「BASE」なら、初期費用・月額費用0円で自分のネットショップを作れるため、コスト面でのリスクを抑えて運営できます。
集客機能が充実していて、「売上を伸ばしやすいネットショップ開設サービスNo.1(※)」にも選ばれているため、実店舗との売上の相乗効果を狙えるかもしれません。雑貨を扱うネットショップの開設をお考えの方は、ぜひBASEも検討してみてください。
※最近1年以内にネットショップを開設する際に利用したカート型ネットショップ開設サービスの調査(2024年2月 調査委託先:マクロミル)
売れるお店を作る機能とサポートが豊富
BASEのネットショップは、開設手続きは最短30秒、販売開始まで最短30分。
ネットショップ開業によくある面倒な書類提出や時間のかかる決済審査もなく、開業までの手続きがシンプルでわかりやすいのが特徴です。
また、売上を左右するデザインや集客の機能も充実しています。
プログラミングの知識がなくても、プロ並みのショップデザインが実現できる豊富なデザインテンプレートをご用意しています。
さらに、集客に必須のSNSの連携も簡単です(Instagram・TikTok・YouTubeショッピング・Googleショッピング広告)。
ショップ開設はメールアドレスだけあれば、その他の個人情報やクレジットカードの登録も必要ありません。
個人が安心して使えるネットショップをお探しなら、開設実績No.1のBASEをまずは試してみてください。